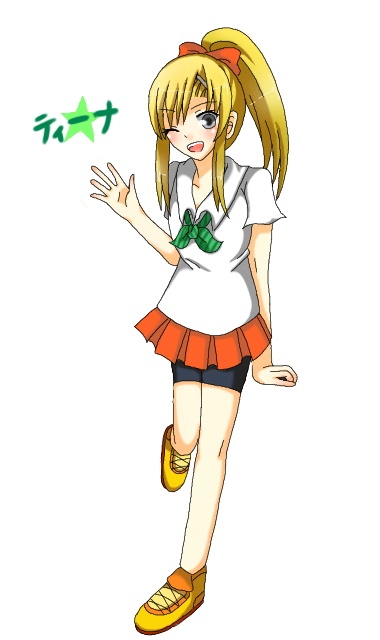28.ガールandガール
もう一つ、ちょっとした出会いのお話をしましょう。
この物語の主役はミリー。彼女が、箒に乗って買い物に出かけていたときのことです。越えようとする木の幹近くにシザーの横顔が見えました。高度を落とし近付いていくと、違う誰かの姿も見えてきます。ポニーテールとミニスカート。目に映ったのがそれだけでも、その主が女性だと理解するには十分でありました。
ミリーの表情が変わり、咄嗟に軌道を変えると元の高さまで戻ってその木の斜め上で止まります。二人が何を話しているのかは聞き取れず、表情も見えません。しばらくその場で様子を窺っていると、やがて少女の方が葉の陰から出てきました。
言ってしまえばその人物はティーナであったのですが、この時のミリーは彼女のことを知りません。もしかすると喫茶店でウェイターとして働く彼女と顔を合わせたことはあるかもしれませんが、それしか関わりがない人の顔をわざわざ記憶しているのはあの店長さんくらいでしょう。
間もなくしてシザーも動き出し、ティーナとは反対の方へ歩いていきました。彼女が向かっていった方角にあるのは、今まさにミリーも向かおうとしている商店街です。きゅっと口を結んで二人がいた木の下に降りると、周囲に人がいないことを確認しつつショルダーバッグの中から杖を取り出しました。そして小声で呪文を呟き、頭上に掲げます。
杖の先から真っ白な光が、花火のように噴き出しました。螺旋を描きながら下へ広がって、彼女の全身をすっぽりと包み隠します。その光がぱっと弾けて消えたとき、中から現れたのは全く違う容姿をした人間でした。
両耳の上で可愛らしく二つにまとめていた桃色の髪は、真っ赤でチリチリなショートカットに。身に付けていたキャミソールとキュロットスカートは、ポロシャツとジーンズに。サンダルはスニーカーに変化しました。心なしか背丈も伸びたように見えます。何よりも大きいのは人懐っこさを感じせる大きな目が細く鋭いものへなったことで、アイドル・ミリーとはまるで真逆の雰囲気を纏っていました。
その少女が、唯一どこも変わっていないショルダーバッグから手鏡を出すと自らの顔を映し、口を歪めて息を吐きます。
「……やっぱり、“ワタシ”じゃないみたいで嫌だなぁ」
そう零した声も、いつもとは違う低いものでした。
変身の魔法を終え、箒に乗り直したミリーはそのまま商店街へ飛びました。大して時間は経っていなかったので、道中で容易く追いつきます。ゲート付近で箒をしまいその後ろをついていくと、ティーナは数メートル歩いた先で手を振りながら駆け出しました。
「待たせてごめんね、メアリー!」
広場のベンチに、メアリーと彼女の日傘を持った黒服の男性がいます。ティーナの声に気付くと、男性はメアリーに日傘を渡し一礼して去っていきました。
「執事さんは帰るの?」
「うん、ティーナが来るまで待っててくれただけ」
ミリーは交通人のフリをして足を止めないまま彼女たちを視界の隅に留め、どうするか思案していました。ただ観察するのは不審ですし、かといって話しかけるにしても、会話のきっかけをどうしていいかわかりません。
すると、メアリーと目が合ってしまいました。慌ててふいっと視線を逸らしたミリーでしたが、彼女の方はじっと不安気な顔で見つめています。ティーナの腕を掴んでぼそぼそと言うのを聞くと、彼女はメアリーを背中に隠すようにぐるりと振り向きました。直前までの笑顔から一転し、探るような険しい目つきをしてミリーを見据えます。
「………?」
視線に気付き、思わず顔をしかめました。するとティーナに呼び止められて、話は予想もしなかった方向へと流れてゆきます。
「何かこの子に用でも?」
「いえ、“私”は……」
「誤解なら悪いと思うけど、ちょっと確認したくて。『そんな姿』してるから」
「え」
ティーナはスッと目を細め、声のトーンを落として周りには聞き取れない声量で続けました。
「……それ禁術候補のでしょ。普通に過ごしてれば使う機会は無いし、そもそも世間に出回ってる魔導書にも滅多に書かれてないってのに、どうして使えるの?」
「っ!?」
頬を引きつらせ狼狽し、言葉を失います。術を見破られたのはこれが初めてだったのです。
「……なんで……」
「わたしも偉そうに言える立場じゃないけど……そういうの見抜ける人って残念ながらいるんだよね。で、どうなの」
素の姿で行くより変装して行った方が安心できるだろう、ただそう考えただけだったのですが、かえって思わぬ事態を引き起こしてしまったようでした。
術を解いて説明しようにも、それには他に人の目がない所へ行かなければなりません。しかし今の状況で二人を連れていこうとすれば、ますます警戒されてしまうことは目に見えています。困ったミリーは、あまり気は進まなかったそうなのですけれど、ある考えの下おもむろにバッグを探りました。
手の平サイズの手帳を開き、後ろの方のページのメモ欄にさらさらとペンを走らせます。すぐ書き終えて怪訝そうにしたままの二人に差し出すと、ティーナの顔いっぱいに驚きが広がりました。
彼女が書いたのは「わたしはミリーです」のたった一文と、自身のサインだったのです。
「? え? ……えっ!?」
目の前の人物の顔とサインを何度も交互に見比べて目を丸くするティーナに、ミリーは苦笑いで答えます。
「……人のいないところ、いいですか?」
ティーナの後ろではメアリーが手帳を覗き込んで疑問符を浮かべていました。
商店街を抜けたところにある原っぱ。三人はそこへやってきました。人混みと喧騒はすっかり遠くなり、みーん……と鳴くセミの声だけが残っています。日陰になるのは木陰くらいで、日光を直に受けていました。歩きながらメアリーはとある一本の木を目に留めます。
「木が焦げてる……? 火事でもあったのかな……」
普段のティーナならばどんな呟きであろうとメアリーの発言には言葉を返していましたが、この時ばかりはその余裕もなかったのかもしれません。ミリーの手には既に杖が握られており、ティーナはそれを凝視しています。
杖が弱く光を放ち元の姿に戻ると、彼女は文字通り跳び上がり、ひとしきり感激した後謝罪の言葉を述べました。
「わたし大ファンなの! あんな態度とって本当にごめんなさい!」
「いいよ、そんな。ワタシも悪かったから」
「ティーナ、この人は……?」
その後方で、メアリーはまだ身をすくませミリーに怯えた目を向けていました。ティーナが大まかに語ると、「知りませんでした」と口元を手で押さえて控えめな驚嘆を示します。それを見てミリーははっとしました。
「そっか、そうだよね。ワタシのこと知らない人だっているよね。ちょっとうぬぼれてたな」
「この子が元々世間の流行りに疎いだけから、気にすることないよ。……それで、ミリーちゃんがわたしたちに一体何の用?」
「あ。えっ……と」
突然の出来事に対応するだけで、ミリーは精一杯だったのです。つい先程まで色々と考えていたはずのこと全てがどこかへ飛んでなくなってしまっていました。
結局、ごまかすことはやめにして、素直に訊きました。自分とシザーが同じクラスで、友達であること。彼と話しているところを見かけて、どんな人か気になったこと。声をかけられたときの視線の意味は、興味心から無意識に目が向いてしまっていたものとしました。
「じゃあ見てたのはこの子じゃなくて、わたし?」
「か、勘違いで疑ってすみません……!」
「平気平気!」
平謝りするメアリーに内心では戸惑いを覚えましたが、その目を見つめてにっこり笑います。
「――わたしとシザー、別に仲良くないよ。家が近所の幼馴染ってだけで、あいつが寮入ってからは全然会ってなかったしね。今日はたまたまバイトの助っ人探して声かけたんだけど、めんどくさいから嫌ってばっさり断られたの。昔っから言葉遣いも態度も乱暴! ミリーちゃんあいつにいじめられたりしてない? 大丈夫?」
あまりにも真剣な顔で尋ねてくるものですから、吹き出してしまいました。彼女からしてみれば、シザーの評価は「図体だけ育って中身は子供っぽいまま」とのことです。ミリーの懸念もすっかり晴れて息をついたところで、元々遊びの用事で待ち合わせていた二人は商店街へ戻ると言いました。頷くと、ティーナはどことなくかしこまった様子で、恥ずかしそうに頬を掻きます。
「あのさ、最後にお願いがあるんだけど……さっきのサイン、もらえたりする?」
彼女のその姿、言葉に何を見たのか、ミリーの瞳は僅かに揺れました。
そっと瞼を閉じて微笑み、暗い鞄の中に手を入れ、
「これで良いなら、どうぞ!」
取り出した手帳のページをピッと破いて笑顔で手渡したのでした。