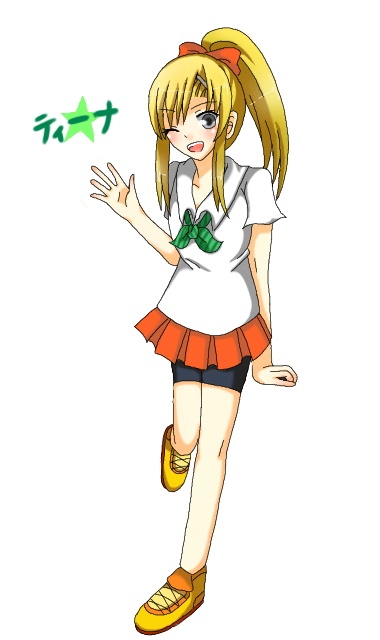89.マリーゴールドは風を起こす
遊び終えた後もティーナはしばらく教室に残って、手が空いている私たちと雑談をしていました。クラスメイトの中には以前からティーナを知っていた人も何人かいて、商店街では少し有名なのだとエレナが話していたことを思い出します。
成績優秀者の飛び級制度がある学校は少なく、スズライト魔法学校では認められていません。また、実際にその制度が適用される機会も稀です。そのため、皆ティーナに興味があったのでしょう。ですが、彼女がスズライト家に出入りしているということは知られていないようでした。
普段からそのように尋ねられることがあるのか、ティーナの応対は慣れた様子です。時に笑顔ではぐらかしながら、移動の準備を始めました。
「わたしそろそろ行くね。絶対混むから、早めに行って待ってたいんだ」
「何かあるの?」
「隣の――」
「あっ、ギアー先生! ちーっす」
ティーナが出ようとしていた扉の前で、受付の生徒が椅子から腰を浮かせて手を振ります。
廊下からひょっこりとギアー先生が顔を出しました。
「やあ、どうも。楽しそうで何より」
先生は手ぶらで、ミリーと同じ橙色のクラスTシャツを着ています。パルティナ先生ほどではありませんが、いつもより少し若々しく見える印象です。近くの生徒たちの気さくな呼び込みに応えると、丸眼鏡の奥の目を優しく細めました。
「暇だったら先生も一回どうです?」
「先生もそうしたいところなんだけど、残念ながら暇ではなくてなあ。シザーさんを捜しているんだ。朝は確かにいたのに、当番の時間に来なかったそうでね。ここに目撃者はいるかい?」
その問いに皆が首を振ります。私も、この日シザーのことはまだ一度も見ていませんでした。
「そうか。校舎の中にはいないのかな? 情報提供ありがとう」
先生は皆を見渡し、お礼をして去っていきます。
傍で話を聞いていたティーナが、低い声でぼそりと呟きました。
「……何してんのあいつ」
振り向くと、喫茶店では見たことのない白けた顔をしています。
「シザーのこと知ってるの? 友達?」
「幼馴染。家が近くなんだ。まあ別に、それだけ」
ティーナはつまらなさそうに説明しました。
一瞬だけ何かに思いを巡らせるように視線を泳がせましたが、すぐに元の笑顔と明るい声色に切り替わります。
「前に聞いたことあるんだけど、確かシザーってミリーちゃんと同じクラスなんだよね? ってことは、隣の教室? わたしも軽く捜してみるよ。しょうもない理由だったら叱っとくから」
「う、うん」
「そんじゃね! キラにもよろしく言っといて! 賞品のこと、わがまま言ったのに聞いてくれてありがと!」
お菓子の袋を腕にかけ、空いた手をひらりと振って、ティーナは爽やかに去っていきました。
これより語るのは、学園祭の閉幕後に聞いて知った話となります。
シザーが皆の輪から抜け出したのは朝早く、開催セレモニーを終えて各自の教室へ戻る途中のことです。
長身のため最後尾に付いていたシザーは、クラスメイトに気付かれずに列を外れることができました。そうは言っても恐らく、その現場を目撃した他の生徒や教師はいたはずなのですが、彼を咎める人物は現れなかったようです。
講堂と校舎の間の連絡通路で横に逸れて皆と離れた彼は、壁沿いに講堂の裏へと回りました。そこに一本そびえ立っている木に寄り掛かると、何をするでもなく腕組みをして瞼を閉じます。講堂の中にはステージの裏方や設営係の学園祭実行委員たちが数名残っていて、時々話し声や物音が聞こえました。
そのまま、エレナによる開場アナウンスの時間を迎えます。扉を開け放った講堂の中から、小さく漏れ聞こえていました。
それを合図に目を開けると、開店したばかりの屋台が並ぶグラウンドへ出ます。フランクフルトを一本買って早々にそれを平らげ、続けて蓋付きの器に盛られた焼きそばを買い、こちらは開けずに手で持ったまま引き返していきました。
講堂の扉の手前には机が置かれ、アンケート用紙を集めるための投票箱が設置されています。ポストのような細い穴が上に開いている、高さ三十センチ程度の木箱です。シザーはその横で足を止めて講堂内を覗きました。
一組目の発表準備を進めているところのようです。まばらではありますが、周囲には既に観客が待機しています。壇上の幕は下りていて、その手前に制服姿の実行委員が一人だけ立って開演前トークを繰り広げていました。
幕が上がり、有志のパフォーマンスが始まります。一番手を飾るのは女子生徒グループによる華やかなステージです。シザーはそれを最後まで見ずに、スッと立ち去りました。
彼が身を隠していたのは、敷地の離れに立つ塔の裏手にある焼却炉の横です。この塔には元からあまり人が来ませんが、学園祭の日には完全に施錠されているため誰一人として近付かないのでした。
古びて錆だらけな焼却炉の背面に寄り掛かり、足を投げ出します。肩が擦れて、Tシャツに少し汚れが付着しました。
蓋をしたままの焼きそばを傍らに置いて、また眠るように目を閉じます。照り付ける日差しの熱さが瞼の裏を焦がすかのようでした。
「あんちゃん、こんな隅っこで何してるの?」
気配も足音もなく突然に、頭上から声が降ってきます。
バチッと目を開いたシザーの視界に映ったのは、しゃがみ込んで彼の顔を覗き込んでいる幼い男の子です。ぶかっとした丸い眼鏡をかけて、ニコニコと目を細めていました。
まだ中身が半分ほど残っているタピオカミルクティーを持ち、沢山の物が入りそうな大きいリュックサックを背負っています。夜空のように深い藍色のTシャツの中央には、鮮やかな黄色で大きく満月が描かれていました。
シザーはぱちくりと瞬きをします。口をついて出たのは率直な疑問でした。
「お前こそこんなとこ来て何してんだ。迷子か、ガキんちょ」
「違うよ。学校探検さ!」
えへんと胸を反らした少年が、リュックサックの重みで後ろへひっくり返りそうになります。
「おっとっと」とふらついた拍子に開いた瞳は、透き通ったマリーゴールド色をしていました。
元気が有り余っている様子の少年にふっと微笑みを向けると、シザーは上半身を起こします。
「ここは何もねーぞ。つまんねーから、早いとこ戻んな」
「あんちゃんはどうしてここに?」
「俺はサボリ」
「いけないんだ。そうか、あんちゃんは不良ってやつかい?」
人当たりの良いニコニコ顔を浮かべたまま、少年はズバズバと言いました。なかなか怖いもの知らずのようです。
「皆と協力するのが恥ずかしい? それとも、一生懸命頑張るのが恥ずかしい? そういう考えの方が格好悪いものだよ」
「あ? そんなんじゃねえよ」
「あれ? おかしいな。僕の知っている不良っていうのは、そんな人たちなんだけど。だったら何で?」
「ガキんちょには関係ねー話だ」
「そうか。うん、確かに、あんちゃんの言う通りだね」
つっけんどんな態度でシザーが突っ撥ねても、少年は平気な顔をしています。
思いのほかすんなり納得して引き下がったかと思うと、すとんと隣に腰を下ろしました。怪訝な顔をしたシザーをまるで無視して、体の向こう側にある焼きそばの器を指差します。
「その焼きそば、食べないなら僕にくれないかな?」
「食うから駄目だ」
「ちぇー」
シザーがサッと焼きそばの上に手をかざし、少年は冗談めかしながら口を尖らせました。
それは昼食にするつもりで買った物だったのですが、少し早く食べることにして蓋を開けます。取られてしまいそうだから、という訳ではなく、少年を連れて彼の保護者を捜しに行くべきかと考えたからです。
少年は迷子ではないと主張するけれど、本当のところはわかりません。彼が見栄を張っているだけかもしれませんし、まだ幼い子供が家族も友人も連れずにたった一人で来ているとは考えにくく、その行方を心配している人がきっといるだろうとシザーは思ったのです。
そのように思われているとは知る由もなく、少年はピンク色のストローを口に咥えて吞気にタピオカミルクティーを飲んでいました。
「僕はさっき、たこ焼き食べてきたんだ。出来立てでアツアツで美味しかった! でも、そういえば、係の人が一人来ないって話をしてたな。どうしたんだろうね?」
「……へー」
シザーが器を手に取ってフォークでかき混ぜると、内にこもっていたソースの香りと熱が風に乗って広がります。
焼きそばをすする音がし始めても、少年は気にせずに一人で話し続けました。
「その前にはヴァンパイアのお化け屋敷に行ったよ。僕は一人でもへっちゃらだけど、楽しかった! 特に奥のピアノが凄くって……おっと、まだ行ってないあんちゃんにこんな話しちゃいけないね。忘れてくれよ。この後お昼ご飯食べたら、次は講堂に行くんだ。本当は午前の部も全部見たかったんだけど、分身でもしないと体が足りないね」
「変なこと言うガキだな」
「だってそうじゃないか? 今日ここにしかないものが沢山あるんだ」
少年は体を捻ってシザーの横顔をじっと見つめます。それをシザーは無視し、黙々と焼きそばを咀嚼しました。
「こんな場所で、一人で寝てる暇なんてないよ。あんちゃんも気になってるだろう? ここでしか見れないものがあるってこと。学園祭で何かが起きるってこと。でも、それがいつどこで始まるかはわかんないんだ。パンフレットを見ても載っていないことだからね。でしょ?」
「……さあな。何言ってんだ?」
少年の曖昧な言い方に、シザーは眉を寄せました。とぼけているのか、本当にピンときていないのか、傍目には判別しにくいものがあります。そんなシザーの目を見て少年はころころと笑いました。
焼きそばはものの数分でなくなり、シザーの手に空の容器だけが残ります。
「行かないと見逃しちゃうよ。きっと後悔すると思うな。ここにいたって、何も始まらないだろう?」
少年はシザーの腕を引っ張って立ち上がりました。シザーが食べ終えるのを待っていたかのようでした。
小さく柔らかなその手には、何か魔法がかけられているような温かさがあります。二人の体格差を思えば少年の手を振り払うことなど容易かったはずですが、シザーはそうしませんでした。
「あんちゃんが本当にしたいのは、ここでサボることじゃないもんね? さ、行こうか!」
「何勝手に――」
「素直になりなよ、あんちゃん!」
そうして少年に引かれるまま、校舎の方へと連れ出されていったのでした。
楽しげな音と歓声が洩れ聞こえてくる講堂の近くまで来ると、だんだんと人の往来も見えてきました。
少年は時々振り向いて、シザーを見上げてはニコニコと笑みを浮かべます。対してシザーは不服そうですが、気にも留めていない様子です。
グラウンドへ向かう道のりの途中に設置されたゴミ箱に、シザーは片手で空の容器とフォークを投げ入れます。それを少年はにんまりとした顔で見ていました。その間もずっと、シザーのもう一方の腕は掴まれていました。
「何で俺にこんな構うんだよ? 何なんだ? ガキんちょ一人で来てるわけじゃねえだろ?」
「ん? ……うん、そうだね! 今日は四人で見に来てるよ。でもみんな自分の用事の方に行っちゃって、退屈なんだ」
そう聞いたシザーは、やはり迷子なのかと口には出さず心の中で思います。
「迷子じゃないってば」
光を湛えたマリーゴールド色の瞳がシザーを射ました。
不意に印象を変えた目つきと、まるで心を読まれたような一言にドキリとします。
すぐに少年はコロッと人懐こい笑みに戻り「顔に書いてあるよ、あんちゃん」と得意げに言いました。掴まれていない方の腕を振りかぶったシザーにギッと睨まれても、可笑しそうに笑い声を上げます。離した手で頭を庇うようにして、シザーの背後へ小走りで逃げ込みました。
はしゃいでばかりの少年にすっかり振り回されているシザーは、腕を下ろし小さな溜息をつきます。
そのとき、横から名前を呼ばれました。
「み……見つけた! シザー君!」
「ど、どこ行ってたのっ。朝の準備もだけど、お店の当番もサボったって知ってんだからね!」
皆お揃いの、橙のストライプ柄のクラスTシャツを着ています。同じクラスの女子生徒四人が並んでいました。
普段であればシザーのことを避けて話しかけることなどない彼女たちでありますが、人数で勝っているためか祭りの雰囲気に飲まれて気が大きくなっているためか、警戒しつつも詰め寄ってきます。
シザーは顔をしかめてすぐ立ち去ろうとしましたが、彼女たちから視線を逸らしたところで動きを止めました。
眼鏡の少年が姿を消していたのです。
先程シザーの死角へと回り込んだ後から見当たりません。どれだけ邪険に扱われようともくっついてきていたというのに、自分の傍にも少し離れた人混みの中にも少年はいませんでした。
「さっきまでこの辺ウロチョロしてたガキは、どこ行った」
「えっ? そ、そんな子いた?」
四人は顔を見合わせて首を傾げたり横に振ったりします。
シザーは乱暴に舌打ちをして、駆け足で彼女たちの横を通り過ぎました。
「あ! まっ、待ちなさいよ!?」
「無理だよリーン! も、もうやめとこ!」
「もうすぐ時間だし、私らまでサボりになっちゃう。教室行かないと」
「ああもうっ! せっかく見つけたってのに!」
追ってくる叫び声に振り向くことはありません。
少年は何かに興味を引かれ、その好奇心の赴くままふらりと一人で行ってしまったのかもしれません。この後は昼食を取って講堂に行くと話していたことを思うと、校内には入らず近辺の屋台を見に行っている可能性が最も高いはずだと推測を立てます。まだそう遠くないところにいるはずでしょう。
そう思い、シザーは陽を浴びているグラウンドの輪の中へと入っていきました。