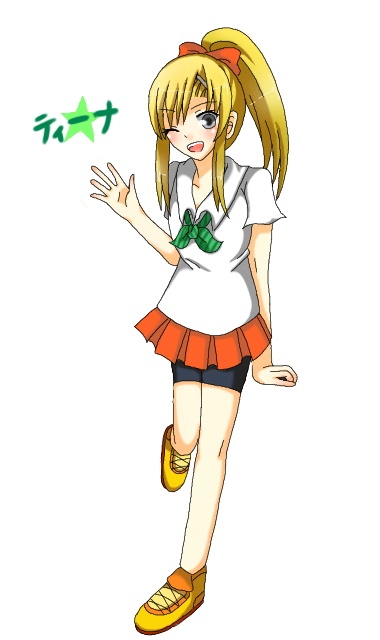90.探し人たち
シザーが迷子の少年を捜しに向かったのと同時刻。
昼食と休憩のために、ティーナは校舎三階の模擬店へ来ていました。一つ上の学年のクラスで、特徴的なテーマや凝った内装をしているわけではないけれど、豊富な種類の軽食を用意している飲食スペースです。
残り少ないグレープフルーツのジュースを飲みながら、空になった紙皿をよけたところにパンフレットを広げます。校内地図と出店紹介のページを開くと、付箋とペンで書き込みを始めました。
『入ってすぐ、唐揚げの匂い。お腹が空く!』
『ルミナとキラのクラス! みんな仲が良さそう。黒板に沢山ラクガキしてあった』
『お昼ご飯、お好み焼き。結構大きかった。メアリーには多いかも?』
ティーナは自分が行った順で番号を振って、記号やイラストも交えながらさらさらと綴っていきます。
このメモは、メアリーとネビュラのリクエストでした。
初めはティーナ自身が思ったことや二人に話したいことを走り書きしていたのですが、それを見た彼女たちが欲しがったため、今では丁寧に記録するようになったそうです。私が思うに、恐らくメアリーとネビュラにとって一番嬉しいお土産とは、世界にただ一つしかないそのパンフレットとティーナの話そのものなのでしょう。
パンフレットはどんどん賑やかに彩られていき、次の付箋を貼るスペースを探して手を止めます。すると、入口の方から少年二人の会話が聞こえてきました。
「おっす! 久しぶりだなあ、弟君! 食ってかないか?」
「……これから店番で、戻るところなんで。終わったらまた来ます」
一人は客引き中の生徒で、呼び止められているのはキラです。キラは友人たちと一緒ではなく、先輩に顔だけ向けて返事をしています。
弟君、という呼称に、キラは少しだけ表情を曇らせたようでした。その翳りを察したのかはわかりませんが、先輩が次の言葉をかけるまでに一呼吸分の間がありました。
「ま、なんだ、祭りの日なんだし楽しくやれよな!」
「はい……どうも」
朗らかな先輩に軽く頭を下げ、扉の前を通り過ぎようとしたときに、キラとティーナの目が合います。
しかし、二人とも何の挨拶も交わしませんでした。スッと顔を背け、壁の向こうにキラの姿が消えていきます。
ティーナは冷めた目で片肘をつき廊下から視線を逸らすと、指先でペンをくるりと回しました。
昼食の後もあちこちの教室を巡っているうちに、人通りの少ない静かな通路に出ます。職員室に面した廊下です。時間をやり繰りしてギアー先生のように学園祭の様子を見て回っている先生もいますが、平常通りの業務をしている先生もいたのでした。
前日から壁に貼られたままの掲示物を眺めて歩くティーナの横で、不意にガラッと職員室の扉が開いて女性が飛び出してきます。パルティナ先生でした。
ティーナは彼女を見たとき、教師ではなく生徒かと勘違いしました。普段の服装であれば違ったのかもしれませんが、私やキラたちと同じ水色のクラスTシャツを着ていたことから、クラスメイトなのかと思ったそうです。
パルティナ先生はやけに焦り、苛立った様子でした。肩を振って大股で、ギリッと宙を睨みながら、左右には目もくれずに脇をすれ違っていきます。その剣幕はティーナも少々気になったものの、特に後を追うことはしませんでした。
直進を続けて、誰もいない廊下の端が見えるところまで歩きます。客人の姿もなければ、出店も特にない場所です。左手首に巻いた腕時計で現在時刻を確認すると、来た道を引き返して角を曲がります。
次に通ったのは、来場者の出入り口になっている靴箱の前でした。すぐ傍の唐揚げ店が行列を成し、通路の半分が塞がっています。ティーナがやってきた当初よりも混雑が増していました。
長い列を何気なく目で追いながら横を歩いていると、列の最後尾に一人で並んでいた若い女性と視線が合いました。鮮やかなコバルトブルーの瞳と、まるで私の母のように腰まで覆う長い金髪が特徴的です。耳元で三日月型の控えめなピアスがキラリと光ります。
「えっと、な、並びますか?」
女性はどこか慌てた様子でふいっと視線を逸らし、前方に詰めようとしました。
「ああ、いえいえ、行列だなあって見てただけですー」
ティーナは手を振ってにこやかに断り、ササッと列から距離を取ります。
その際に列の反対側へ目をやったとき、外にシザーを見つけました。
前髪を上げて額を出した頭部と橙のTシャツが、人々の隙間からちらちらと見えています。彼は何かを探すように首を左右に振って、実行委員の受付テントがある方へ向かっていました。
昇降口の外側にも生徒や来客は大勢いますが、中ほどの混みようではありません。ティーナはすぐにパンフレットを閉じて来場者用のスリッパを履き替え、彼の下まで早足で向かいます。途中で向こうも彼女に気が付いたようでしたが、シザーは人に紛れて無視しようとしました。
「ちょっと」
横から無遠慮に腕を掴まれて、シザーは舌打ちをします。
「んだよ。来てたのか」
ティーナも先程の女性に見せた愛想の良さから一転して、ムスッとした顔になりました。面倒くさそうな態度の彼をじろりと見上げると、挨拶らしい挨拶もせず単刀直入に切り出します。
「クラスの当番サボったんだってね? 一応言い訳は聞いてあげる。何があったの」
「あぁ? んなことどうしてティーナが」
「いいから」
「関係ねえだろ。離せ」
シザーは腕を振り上げてティーナの手を払いました。体を斜めに背けて、不機嫌に顔をしかめます。
そうした態度を取られても、昔馴染みのティーナは全く怖気づきません。むしろ、彼女はかえってムキになったようです。
「言えないようなことなの? お祭り好きで約束だけは絶対守るあんたが、理由も無しに来ないわけ――」
ティーナがまだ話していましたが、シザーはその途中でサッと目の色を変えました。今度は彼の方から腕を掴み上げます。
「ちょっとこっち来い」
「何、いたっ、痛いんだけど!」
遠慮がないのはシザーも同じでした。掴んだ腕を強引に引っ張って、他の生徒や来場者から離れていきます。並木の裏で解放されたティーナは、掴まれていた箇所をもう片方の手で痛そうにさすりました。
恨めしげに睨む彼女に対し、体を向き合わせたシザーの目は木陰になった地面を睨んでいます。
「俺は学校じゃ、『問題児』やってっから」
「はあ?」
ティーナの眉が怪訝に曲がり、口が歪みました。
普段のシザーの学校での様子をティーナは知りません。彼女は同じ学校に在籍していませんし、シザーから特に話すこともなかったのでしょう。
シザーは自らの態度をもって大人たちを試しているのだと、以前ミリーにも語ったことのある内容を手短に説明していきます。学園祭でクラス出し物に協力をしないのも、彼にとってはその一環。自分の素顔が教員に知られることがないようにするためでした。
説明の間ティーナは無言でしたが、事あるごとに口を開きかけては出そうになる言葉を飲み込んでいたようです。
全て聞き終えて、ようやく捻り出されたのは非常に簡素な一言でした。
「馬鹿じゃん……」
包み隠さず辛辣な評価を下し、呆れ切ってげんなりした表情で続けます。
「え、ほんと何? 意味わかんない。まさか去年も同じことしてた? 自己満足……いやそれ以下でしょ。昔から馬鹿だとは思ってたけど、さすがに馬鹿すぎない? 何やってんの?」
「うるっせーな。ティーナには関係ねーっつってんだろ。だいたいてめーだって似たようなモンじゃねーか。さっさと学校辞めて」
「一緒にしないで。てか辞めてないし」
ティーナはズイッと身を乗り出しました。
「確かにわたしは、早く卒業したかっただけだけど。でも勉強や部活だって全力出して本気でやった。楽しかったよ。シザーは変なプライドで引っ込みつかなくなって意地張ってるだけでしょ」
何か言い返そうとしたシザーのことは無視してまくし立てます。
「自分のしてること、胸張って人に誇れる? 卒業した後、大人になってから、本当に後悔しない? そんなことも想像できないほどの馬鹿だったわけ?」
開きかけていた彼の口からは、何の反論も出てきませんでした。
シザーは唇を噛むと眉間に皺を寄せて、顔を横へ向けます。ティーナの問いには答えずに、話題を逸らしました。
「お前の説教に付き合ってる暇はねえんだよ。俺は急いでんだ。早くしねえと、あのガキがどこ行ったかわかんなくなる。迷子がいんだよ」
「迷子? 悪ぶってクラスの手伝いはサボるくせに、迷子捜しはいいんだ。適当だね」
棘のある嫌味が再びシザーを襲います。こちらに対しても、無視を決め込みました。
ティーナは一歩前に出していた足を引き、溜息と共に肩をすくめます。ちらりと、腕時計の針が示す時刻を気にしました。
「その子の特徴は? 校舎側はもう捜したの?」
「眼鏡かけてリュックしょった、半袖短パンのやかましいチビ助だ。捜したのは外だけ、中はまだ見てねー。でも校庭か講堂にいるはず――」
「馬鹿、同じ場所ばっかり捜したって時間の無駄だよ。教室の方も見ないと。ほら、わたしも手伝ってあげるから」
「いっ、いでででっ、引っ張んじゃねーよ!」
「さっきのお返し!」
ティーナはシザーの耳たぶをグイっと摘むと、真上からさんさんと陽の光が降り注いでいる昇降口の前まで彼を連れ出していきました。