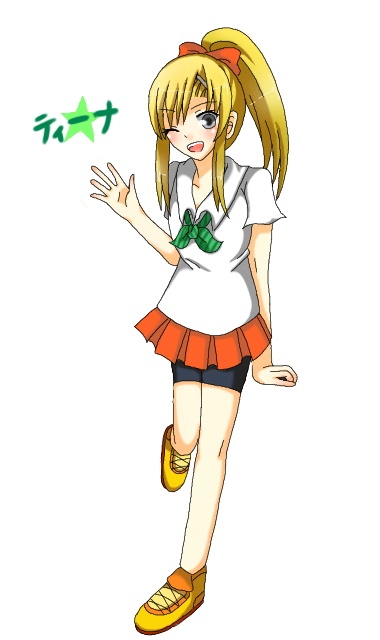105.gift&blessing(7)
確認を取りつつ、リハーサル通りの開始位置に立つ。エレナはステージ袖へ去っていった。
照明の落ちた広いステージの中央に一人。
騒めいていた講堂の中が、徐々に静まっていくのがわかる。
閉じている垂れ幕の向こうのみんなは、ここにワタシが立っているとは気付いていない。考えてもいないはず。
向こう側の景色を想像すると、緊張に足がすくんで震えそう。
だけど、バレッドさんが見せてくれたみんなの顔を思い描けば、そんな気持ちは消し飛んでいく。
何度も何度も挫けそうになってしまったワタシだけど、あれだけの想いをもらった後だもん。
不安に負けてなんかいられないよ。
ワタシには、何の力もない。
バレッドさんみたいな魔法の力も持ってないし、エレナみたいな頭の良さや自信もない。自分のことばかり考えて、無力で、弱い。
でも、そんなワタシにも、ワタシだけにできることがあるってパリアンさんは言ってくれた。ワタシの歌は力を持ってるんだ、って背中を押してくれた。
そして、それを伝えてくれたのはパリアンさん一人だけじゃなかった。
クレアと、レルズ君。
二人の言葉を思い出し、目を閉じる。
――あなたは、わたしの太陽でした。
――わたしは、ミリーの歌にいっぱい元気をもらいました。これからもずっと、ずっと、応援しています。
クレアが最期に遺してくれた言葉。
レルズ君がワタシにくれたのも同じ言葉だった。
――いつだって何回だって、俺は答えるっす!
――ミリーちゃんは、俺の太陽だって!
太陽。
二人はワタシを太陽だと言う。
でも、ワタシは今でも自分をそんな風には思えない。
太陽みたいにいつでも、一人でも明るく強くあり続けることなんて、ワタシにはできないもん。
ワタシがそんな風な人に見えるのだとしたら、それは他でもないみんなの前だから。
ワタシがいるのは晴れやかな青空の下じゃない。いつだって、この暗く閉じたステージみたいに先の見えない夜道の中。
太陽に照らされているのはワタシの方で、みんながワタシの進む道を示してくれているんだ。
ワタシがしているのは「本物」の真似事に過ぎない。
ピアノを奏でるクレアの光り輝く瞳に憧れた。
あんな風になりたいと願った。
ワタシが目指しているのは、今もクレアなんだよ。
レルズ君もワタシに光をくれた。
君はワタシのことを太陽だって言ってくれたけど、ワタシは逆だと思う。
弱気に負けそうになるワタシのことを信じ続けてくれた。ワタシよりもワタシのことを信じてくれていた。
あの放課後、丸い頬を夕陽で真っ赤に染めながらひたむきに、熱い想いを瞳に宿して伝えてくれた。
どれほど嬉しかったか。支えになったか。
君こそ、ワタシの太陽だよ。
なんて言ったら、君はどう思う?
俺はそんなんじゃないです、って慌てるのかな?
ワタシが自分のことをそう思えないのと同じように。
自分自身が何と思っているとしても、誰だって、誰かにとっての「太陽」になれるのかもって思う。
案外、人から見た自分のことってわからない。だから、自分に自信がないのなら、自分を信じてくれる相手のことを信じてみよう。
ワタシはそうやってここに立っている。
そんな風に信じてくれる人がいるだけでも、幸せなこと。
みんなにとってもワタシがそういう存在であればいい。みんなには人を照らす力があるんだよって、伝えたい。
どうか、この想いがみんなへ届きますように。
ワタシの歌がみんなの光でありますように。
深呼吸を一つ。
魔法で指先に光を纏わせて、最後の準備が整う。
端で控えているエレナにちらりと視線を向け、光の軌跡を描く指でハンドサインを送った。その合図は、エレナからステージの演出係と司会進行役へと伝わっていく。
始まりを告げる鐘が鳴った。
カラカラと音を立てながら、幕がゆっくり上がっていく。
シンとしていた講堂の空気がザワッと揺れ、幕が上がり切ったときには大きなうねりとなっていた。全身に感じた振動は、ワタシの決意を固めさせるには充分すぎるくらいだった。
頭上のスポットライトが点灯し、歓声とも悲鳴ともつかない声の波の上へ被せるようにレコードが再生される。
そのポップなメロディが弾けるのに合わせてパッと目を開け、自然と零れてきた渾身の笑顔を向けてみせた。
客席の方は明かりが点いていないけど、みんなの姿はちゃんと見える。それぞれのクラスTシャツや発表の衣装を身に付けていて色とりどりで、一様に、何が起きているのかと驚き顔。どよめきも止まない。
ワタシはリズムに乗ってステップを踏みながら、両腕を大きく広げて手招きした。
みんな、もっとこっちに来て!
その表情をもっとよく見せて!
みんなの喜ぶ顔が、ワタシの力の源なんだ!
全校生徒のカラフルな列は途端に崩れて混ざり合い、波のように一斉に集まってきた。奥半分に用意された一般来場者向けの座席からも多くの人が立ち上がって、前方へ駆けてくる。
あの冬以来のライブ。
――大丈夫。
大丈夫!
ステージライトと指先の光が、視線の先を照らし出していく。
座席に残った人たちの中にシズクちゃんの姿を見つけた。最前列の椅子の前で、興奮を抑え切れずにピョンピョンとジャンプしている。歌が始まると飛び跳ねるのをやめ、代わりに左右に体を揺らしてリズムに乗った。
その近くにはティーナちゃん。椅子の前に立ち尽くし、斜め掛けしたショルダーバッグの紐をギュッと握りながら、煌めいた目でこちらを見つめている。
シザーはいるかな、と目を凝らすと、ステージ前に集まった生徒たちよりも数歩後ろのところに一人立っているのを見つけることができた。他に誰の視線も無いからか気が抜けていて、口を丸く開けてぼうっとしたような顔をしている。
ワタシと目を合わせた瞬間が確かにあったし、シザーもそれに気付いていたのは明らかだった。ハッとした表情を見せた彼に、パチリとウインクを向けてみせた。
シザーのいる辺りが元々の整列場所なんだろう。人の山から離れたその付近には、ルベリーも立っていた。彼女は常に人の心の声が聞こえているというから、これだけの人数がいる場で気分を悪くしていないかと一瞬不安がよぎる。だけど思いのほか顔色は良さそうに見えた。ライブ中の皆の心の中って、どんな風に聞こえているのかな。
ルミナのことも見つけた。その場に立ち止まっている二人とは違って、みんなの後ろで左右にひょこひょこと揺れて顔を出そうとしている。本当は前に来たかったのかもしれないけど、最初の流れに乗り遅れちゃったような様子だ。
ステージのほぼ真下、最前列に駆けつけてくれた人たちは息ピッタリだった。曲とワタシの呼びかけに合わせて、腕を高く突き上げて応えてくれる。何人かの友達と一緒に並んだレルズ君が気恥ずかしそうに、けどしっかりと、ちゃっかりと抜け目なく参加していて、その一生懸命な表情が面白くてこっちも笑みが零れた。
予想していなかったのは、ネフィリーも前列に加わっていたこと。いつも大人しくって、こういうので前に出るタイプじゃなさそうなのに。今朝、大勢の人に囲まれたワタシを助けてくれたときも印象違ったし、まだワタシの知らないネフィリーがいるのかも。
ネフィリーは活動休止前のワタシを知らないと言っていたから、ライブも初めてのはず。きっとコールのことも知らない。でも、周りのみんなを真似て一生懸命合わせようとしているのが見て取れる。その気持ちが嬉しいし、ネフィリーも楽しんでくれてたらいいなって思う。
ワタシのライブを知らないのは、隣国から今年引っ越してきたルミナも同じだろう。もう一度見ると、ルミナは舞台から視線を外して横の観客たちを見ていた。やっぱり、返し方をわかっていなくて戸惑っていたみたい。
この後も何回かあるけど、付いてきてくれるかな。ごめんね、あらかじめ教えておけたら良かったんだけど、ライブの計画は秘密だったからできなかったんだ。なんて、ここから伝わるはずもないけど、心の中で謝りつつ言い訳した。
今はまだ、スズライトの街の中でしか歌ったことがない。だけどいつかは国を超えて、海を渡って、もっと沢山の人にもワタシの歌を聞いてほしい。
そんな感情がすっと自然に胸に浮かんだことは、自分でも意外だった。
元々はワタシとクレアのものでさえあればよかった、ワタシの音楽だけど。
クレアは今のワタシの気持ちを聞いたら、喜んでくれるかな。笑って応援してくれるかな。
もう、想像することしかできない。
だけど、そうだったらいいな……。
デビュー曲の「twinkle eyes」を選んだのは、シズクちゃんが一番好きな歌はこれだと話していたから。
でも、ちょうどよかった。この日が本当の意味でワタシのスタート地点だと思って挑んでいるから、デビュー曲はおあつらえ向きだ。
それにこの歌は、今のワタシ自身の気持ちにもよく合致していた。
きっといいことがある、だから一緒に頑張ろうってみんなにエールを送る歌。その歌詞に込める真っ直ぐな思いに変わりはない。
だけど実のところ、今はちょっと違う。思い描いている感情はそれだけじゃない。
歌いながら、自分の歌に勇気をもらう。ワタシ自身のことを奮い立たせている。
一時期は、その明かりが眩しすぎて遠ざけていたこともあった。自分で詩を書いた「ピアニスト」がワタシそのものなら、「twinkle eyes」もまたワタシ自身を象徴するような歌だ。無邪気で幼く、それ故に間違いを犯して、責め続ける一方で突き放すこともできず共に生きてきた、過去のワタシだった。
「twinkle eyes」を素直な気持ちのままでまた歌えるようになったことって、ワタシの中では大きな一歩なんだ。
みんなには内緒。
ワタシだけの秘密。
ワタシもみんなと同じ人間だから、みんなと同じように悩んだり、苦しんだり、立ち止まったりするよ。
そんなときは一緒に思い出そう。大好きな人たちのことを、おいしいご飯のことを、温かくて綺麗な陽の光のことを。
そうしたら、もう大丈夫。
先の見えない夜道の中でだって、きっと歩いていける。
今日この場限り、たった一曲だけのライブは、あっという間にクライマックスへ迫る。
コール&レスポンスに不慣れそうだったネフィリーやルミナも、何度か繰り返すうちにタイミングが掴めたみたいだ。
スティンヴやキラみたいに、あんまりライブに興味なさそうだったり騒いだりしなさそうな人も中には当然いるけど、みんなに合わせて控えめながら腕を上げたり手拍子を入れたりしてくれている。
シザーは身動きしていない。でも、片時も目を離さずにじっとステージを見つめていた。
ドキドキと高揚感に満ちていく身体は、最高のコンディションだ。喉はしっかり開けていて、足取りも軽い。音楽に乗って身体は自然に動く。
全身が火照り、胸がいっぱいになる。
最後の一音を、ありったけの全力で出し切った。
手拍子と、歓声と、どこまでも続きそうなアウトロに包まれる。
スポットライトの光と流星のような煌めきが幾重に重なって、辺り一帯を照らす。みんなの姿まで輝かせている。
大喝采を浴びて、ワタシは観客席の隅から隅まで全員にしっかりと届くように、腕を高く上げて手のひらを広げた。
「ただいま!」