第1話→★
はてなダイアリー時代から書体など一切いじっていないので見づらいかもしれませんが、ご案内だけ。
*2023-11-16…BOOTHリンク追加*
第一巻の文庫版と電子版の通販を始めました。詳細は商品ページをご確認ください。
(※2024-6-8…諸々落ち着くまで一旦閉じてます※)


[執筆状況](2023年12月)
次回更新*「暇を持て余す妖精たちの」第5話…2024年上旬予定。
110話までの内容で書籍作成予定。編集作業中。(2023年5月~)
自席で書類仕事をしているギアーの元へ、つかつかと一直線に迫る。受け持つ学年も科目も違うこともあり、就業中にパルティナがギアーに接近することは少ない。険しい表情でやってきたパルティナを、ギアーは物珍しげに見上げた。
「どうしました、これから一年生の会議なのでは? ……何だか、怒ってらっしゃいます?」
「会議にはまだ時間があります。それより、どうも妙な噂を耳にしたものですから、ギアー先生に心当たりはないかと思って。私とあなたの関係について、生徒たちが好きに想像を膨らませているようなのだけど」
「と、言うと」
ギアーは椅子を回して体の正面をパルティナに向けた。眼鏡のつるに手を添え、とぼけた顔をする。
「口にすることすらつまらないような、根も葉もないことばかりですよ。……その、私たちを、恋仲だということにして、勝手なことを。詳しく聞いてみれば、あなたが私を慕っていることになっているそうですが」
「ああ、どうやらそのようですね」
「知っているのなら、なぜ止めさせないのです?」
「止めさせる必要がありますか? ご自身のイメージアップを図るのに都合がいいじゃありませんか」
ギアーはけろりと言いのけて笑った。
「僕としては、むしろ好都合だと思いますが」
「他人事のように言わないでちょうだい」
マイペースを崩さないギアーと対照的に、パルティナは少しずつヒートアップしていく。
ちらちらと周囲の視線を感じて、僅かに熱が引き冷静になった。見れば、席近くの教師も、素知らぬ顔で手作業をしつつ聞き耳をそばだてているような雰囲気を纏わせていた。
パルティナは咳払いをした。ギアーは意に介した様子もなくにこやかに笑顔を浮かべたままだ。
「僕は本気ですよ。パルティナ先生に叱られた一部の生徒は貴女を怖がっているようですが、この噂に便乗してその印象を払拭してしまいましょう。そうなれば僕も嬉しいです」
「事実でないことを言いふらされて、ギアー先生は不快ではないのですか?」
「そんなまさか。僕はパルティナ先生を尊敬していますから」
「冗談はやめて、真面目に答えて。つまらないわ」
「こうも即座に斬り捨てられてしまうのも、悲しいものですね」
一蹴されたギアーは、眉を下げて困ったような笑みを浮かべる。困っているのは自分の方だと、パルティナの胸の内にじわじわと苛立ちが滲んで語気が荒くなった。
「あなたが私をどう思っているかなんて、とうの昔からわかっているもの」
ギアーの眉がぴくんと動く。
ちらりと職員室内を見渡し、自分たちのやり取りが他の教員たちの関心を引いていることを確認すると、パルティナはわざと一語一句をはっきり区切るようにして強調してみせた。
「あなたの本当の想い人。それを私が知らないとでも?」
途端、聞き耳を立てていた周囲の教員がギアーへ注目した。誤魔化す気を無くした無遠慮な視線が彼一点へ集中する。
いち早く食いついてきた女教師をけしかけ、駄目押しをした。
「パルティナ先生! そ、その話詳しく聞けませんか……!」
「私の口から勝手には言えません。本人に聞いてみてはいかがです? ねえ、ギアー先生?」
彼女を皮切りに、次々と他の者たちも集まってくる。パルティナは押しのけられ、ギアーは椅子の周りを取り囲まれて見えなくなった。
人影の隙間から、ギアーの弱々しい瞳が覗く。パルティナは無言で呆れた視線を向けて立ち去った。
ギアーとて、彼女に思いを知られていることなど百も承知だ。何しろ二人は――セレナーデとプレリュードは、千年来の長い付き合いなのだから。彼にとって問題なのは、質問攻めに遭うこの状況を作り出されたという一点のみである。
教師陣からの詮索はひとまずこれで収まるだろう、とパルティナは一息をつく。
残るは生徒、特にエレナの誤解は解かねばならない。
成人たちの喧騒を横目に、夕焼け色のアイスティーを紙コップへ注ぐ。取り囲まれたギアーを置いて、我関せずと自分のデスクへ戻って古めかしい椅子に背を預け、それを飲み干した。ほのかな甘みと苦みが混ざり合ったまろやかな味がした。
パルティナはすぐにでも事実を声高に語りたい衝動に駆られていたが、それが無意味であることも承知していた。彼女は半ば諦め気味だった。誰も味気ない真実など望んでいない。強い否定はかえって怪しまれ、迂闊な行動は藪蛇だ。
しかし、顔を合わせる度にからかわれるのではたまったものではないとうんざりしていた。エレナは授業の前後でこそ真面目さを崩さずにいたものの、放課後に二人きりになると依然として好奇の目を向けてきた。一過性の噂話に過ぎないとしても、この場を乗り切る術は必要だった。
いつものように、放課後の校庭で魔術の実技練習を行う。その最中も、パルティナはいささか集中できずにいた。
水分補給を促し、数分間の休憩を挟む。斜めに傾いた夕陽が眩しく、校舎の陰に入った。
「先生、今日こそはギアー先生との関係について詳しく聞かせてください!」
早速、エレナが詰め寄ってくる。パルティナは息を吐き、努めて冷静に答えていった。
「はっきり言っておきますけれど、私と彼の間には本当に何もないわ」
「でも、同じ学校出身で昔からの知り合いなのは嘘じゃないですよね?」
「だからこそ、彼が私を好きではないと知っているの」
「その言い方、やっぱり怪しいです! じゃあパルティナ先生の方は――」
「私も! 何とも思っていませんから! 彼はただの友人よ!」
つい熱くなって、声を荒げる。エレナは平然として、友人と談笑するときのように楽しげだ。一呼吸を置いて気を落ち着けてから、改めてパルティナは口を開く。
「……ギアー先生がそのような感情を抱く相手は私ではなく、他にいます」
「!」
「けれど」
明かすまいか否か逡巡していたことだったが、自分以外の女性の存在を提示しなければエレナは止められない。そう判断して発言した。案の定エレナの瞳孔が大きく広がり、パッと表情が輝く。それを制止するように、パルティナは間を置かずに切り出した。
「何というか、それは……叶わぬ恋というものです」
「……え」
エレナの顔色が、さっと曇る。
「彼の個人的なことですから、これ以上は言いません。ですが……決して結ばれない相手だとわかっていても忘れられないような、あの人はそんな『恋』をずっと続けています。だから、たとえ噂話でもあまりからかわないようにしてあげてちょうだい」
そう説明してから、言い方を間違えたと気付いた。これではまるで悲恋の脚本で、ますます若者の興味を引いてしまいそうではないか。
しかし、パルティナの予想に反してエレナは異様に静かだった。急速に熱が冷えて、神妙な顔で口をつぐむと、視線を落とす。
「……わかりました」
元より本質的には素直で従順な娘ではあるが、それにしてもあまりにしおらしく聞き分けがよすぎるようにパルティナには映った。伏せたその目の奥には、言葉以上の思いが何か沈められているように感じられた。
妖精はこの世のあらゆる魔術を行使することができる。その中には、他者の心の内を覗くものもあった。
しかし、セレナーデはそうした介入を良しとしない性分であった。何の術をも施さず、パルティナはただの人間として、黙ってエレナの隣に座っていた。
「ギアー先生には、何も聞かないようにします」
「ええ、そうして。わかってくれればいいの」
俯いたままエレナがぽつりと零す。顔を上げると、縋るような目でパルティナを見つめた。
「でもパルティナ先生の方は、本当にギアー先生のこと……」
「まだそんなことを言うのですか!?」
「そ、そうですよね! すみません!」
エレナに笑顔が戻る。取り繕ったようなぎこちなさの残る表情で、努めて明るい声を出していた。
「えっと、それじゃあ、先生はどんな男性だったらタイプですか?」
「もう、休憩はおしまいです!」
話を打ち切るように、パルティナは立ち上がって手を叩く。エレナも素直に水筒を置いて後に続いた。パルティナは振り返らず、彼女がどんな顔をしているのかは見ないようにした。
この日以降、エレナがパルティナとギアーの関係について尋ねてくることは二度となかった。だが、パルティナの心には小さな空洞が空いたままだった。
プレリュードは、セレナーデには理解し得ない感情を知っている。
彼はある一人の人間を今も愛している。それ故に、ギアーとパルティナとは決して交わらない間柄であると断言することができた。
人間と妖精では、生態も時間の流れもかけ離れ過ぎている。老いることも死することもない妖精は、必ず人間に先立たれる。
決して逃れられないその虚しさは、何度経験しても慣れるものではない。人間を人間のように愛することができる者たちにとっては、尚更深い悲しみを伴って襲いかかってくる運命だ。
それでもただ一つの想いを大事に抱え込んでもがくプレリュードの姿を、セレナーデはずっと横で眺めてきた。
かつてプレリュードが愛した人間の女性は、彼ではない人間の男の元へと嫁いだ。そして二人の血を受け継いだ子を産み、プレリュードの傍を離れて別の土地へ移り住んだ。
プレリュードがどんな思いで彼女らを見送ったのか、セレナーデにはわからない。誰に何と尋ねられても彼は薄く微笑んでいた。その話題のときには彼の言葉がいつも以上に軽く口先ばかりであること、心がこもっていないことは察していたが、その壁の一歩向こうへ踏み込む術がセレナーデにはなかった。
多くの場合、妖精が人間へ向ける愛情とは、人の親が自らの子供へ向けるものに似ている。妖精たちの目から見れば、たとえどんなにしわがれた老人だとしても人間は等しく赤子のような存在だ。どれだけ姿形や感性を似せようとも、根本的に別々の存在だ。故に妖精が人間に恋情を抱くことは珍しい。
しかし、共感はせずとも理解はできる。理屈で御せないのがその感情だと、人間たちも妖精の仲間たちも皆が口を揃えて言う。
ならば、長い年月を過ごしても未だそのように感情を揺さぶられた経験のない自分は、何かの欠落した不完全な心の持ち主なのだろう。彼へ共感を示すことのできない自分の方が、世界に適応できていない存在なのだろう。
プレリュードにしろ人間たちにしろ、愛が故に苦しむ不合理さこそが世界の常識であるのなら、受け入れねばならない。それでも世界を愛していなければならない。
セレナーデがプレリュードを気にかけていることは確かだ。だが、エレナへ語った通り、二人の間には何もないこともまた確かな事実だ。
プレリュードも、セレナーデを特別視してはいない。二人は人間としても、妖精としても、単なる同僚に過ぎないのであった。



当初こそ一年後の未来に一抹の不安と恐れを抱えていたパルティナだったが、それは瞬く間に薄れていった。セレナーデにとっては決して初の経験ではないものの、教師という職の業務量と慌ただしさにより「セレナーデ」の思考は日々「パルティナ」の仕事に押し流されていったのである。
目まぐるしい毎日は、しかし彼女を充実させていた。
今年度一回目の定期試験を終えた頃には、パルティナは自身が受け持つ生徒の特徴を概ね把握してきていた。
一学年には三十人余りのクラスが計四つある。彼女が担任を務めるクラスの中では、ミリーという女子生徒が最も目立つ人物だった。全校生徒の中で一番、誰よりも注目を浴びていると言っても差し支えないほどだろう。
彼女は学業の傍ら芸能活動も行っており、少しばかり幼げだが愛らしい容姿をしている。今は正に絶頂期といったところで順風満帆な日々を送っているようだが、その反面、勉学を疎かにする傾向があった。現にミリーの試験結果は芳しくなく、前期末の試験もこの調子であれば一度個人指導が必要であるとパルティナは目をつけていた。
実のところ、ミリーのことはセレナーデもプレリュードも以前から認知していた。妖精は人間と同等の感性を持つため、あらゆる文化や芸術に好意的かつ興味津々だ。ミリーの歌声は妖精たちの耳にも届いており、ほとんどの妖精が彼女を大層気に入っていた。
そんな中、パルティナがミリーの担任教師となったのは偶然である。否、運命の神々が定めていたことではあったかもしれないが、少なくとも妖精たちが意図したものではない。
パルティナが授業を受け持つ範囲の生徒には、妖精としての観点を以て注視すべき人間はほぼいなかった。ミリーに着目しているのはあくまでも教師の「パルティナ」であって、妖精の「セレナーデ」ではなかった。
クラス担任を受け持っているのは別の人間だが、新入生のシザーも同様の例の一人である。入学当初から反抗的な態度ばかり取っていることから、彼は他の教師陣にも厄介者扱いをされていた。「パルティナ」も手を焼いているが、しかし「セレナーデ」の視点では別段気に留める必要はない相手だった。
にも拘らずパルティナがシザーへ熱心な指導を続けるのは、それが彼女には気晴らしであり娯楽だからである。
「生真面目で清廉潔白な新人教師」が「素行不良の少年」を更生させるべく奮闘する日々。何と物語性のあることだろう。
シザーは、セレナーデが教師を演じる「劇」において格好の登場人物だった。彼の処遇を巡って行われる職員会議もまた、彼女の日常生活を装飾する遊戯に過ぎなかった。
生真面目なセレナーデも、それくらいの「遊び」を楽しむ感性は持ち合わせていたのだった。
刺客は思いもよらない方向からやってきた。
それはシザーと同じクラスに属する一学年の女子生徒で、名をエレナといった。日頃の授業態度や課題の提出状況など、彼とは比べ物にならない模範的な優等生である。週に三、四回ある授業中と、時折廊下ですれ違う休憩時間や登下校の時間でしかエレナ本人の様子を見る機会はなかったが、一切問題のない生徒だと捉えていた。
ある放課後、そのエレナが職員室のパルティナの席へ質問にやってきた。しかし、エレナが持ち込んできたのは学校指定の教科書でもなければ先日の試験問題でもなく、一般向けに書店で販売されている問題集だった。現在の授業で教えている内容よりも進んだ単元のページを開いて見せてきたエレナに、パルティナは問う。
「これは、どうしたの?」
「ええと、わたし、将来は王立校に行きたいんです。それでこの本を買って勉強してたんですけど、自分で調べてもわからないところがあって……」
「見せて?」
「いいんですか? 授業と関係ないことですけど」
「どんな学習でも関係ないことはないですよ。それに、生徒の質問に答えるのも先生の務めです」
これまでのセレナーデの長い「人生」の中でも、この時期からエレナほどしっかりと学習意欲のある一年生は相当の珍しさだ。いたく感心した彼女には、エレナの申し出を断る理由など一つもなかった。
パルティナがエレナと一対一で会話を交わしたのは、この日が初めてである。近くで見たエレナの大きな黒目は、離れた教卓の上から見える様子よりもずっと爛々と輝いていた。
今でこそスズライト魔法学校と呼ばれているが、元々この校舎は学び舎として建てられた場所ではない。かつては、始祖の大魔導士を始めとする太古の人間たちが拠点にしていた研究施設だった。そうした歴史があることに加え、現校長の指針により、放課後の過ごし方は生徒一人一人の自由に委ねられている。つまりは、放課後は部活動に勤しまなければならないといった校則が存在しないのだった。
普段からこの教材で自主学習をしているのかとパルティナが尋ねると、エレナは頷いた。パラッと流れた真っ直ぐな茶髪を耳にかけて、気恥ずかしげに頬へ手をやる。
「つい遊んじゃったりして、あんまり進んでないですけど……でも、王立校に受かりたいなら今から勉強しておかなくちゃと思って、少しずつ」
「でしたらまた来週、今の単元を解いて持ってきてくれる? 答え合わせと復習をしましょう」
「えっ?」
「私も来週までにその問題集を用意しておきますから」
柔らかく微笑んで見つめると、エレナはパルティナの提案に感謝して屈託のない笑顔になった。
そうして毎週エレナがパルティナのデスクまで足を運ぶようになり、その問題集は二ヶ月ほどで最後のページが捲られた。
次は座学ではなく実技指導が始まった。問題集を一冊全て解き終えたがこれからも個人指導を続けてほしいと、エレナから頼んできたのだった。
教員の定常業務の他に仕事が一つ増えたも同然だったが、パルティナにとっては些細なことである。意欲的で将来有望な人間との出会いを、彼女は心から喜ばしく思った。頼む相手次第では、エレナの熱意に教師側が付いていけず厄介扱いされていた可能性もある。エレナにとっても、パルティナとの巡り合わせは幸運だったことだろう。
最初は数十分程度だった補習時間は、次第に一時間、二時間、と延びていった。それに比例するように、二人の仲も教師と生徒の垣根を越えて深まっていった。
互いに根が真面目な人物であるため、必要な礼節は勿論弁えている。その上で、勉学以外の話題でも談笑ができる程度の関係が築かれていった。
エレナの本性が発覚したのは、そんな折だった。
「――そう、今度は火の玉ではなく、火柱が立ったでしょう? それが『術の形状を変える』ことの一例です。今は火の魔術でしたが、水や土など、他のどのような術でも応用することができます。種類は膨大ですから、少しずつ慣れていきましょう。試験で頻発するものは限られるから」
「はい!」
魔術の実技練習は基本的に屋外で行う。外に出ているのはパルティナとエレナの二人だけだ。先日の衣替えでエレナは半袖の制服を着用するようになり、パルティナもまた涼しげなロングスカートと薄いブラウスを身に付けている。夏が近くなり、夕方の放課後も外は暖かかった。
魔術の媒介に用いる杖を携えたまま朗らかに返事をするエレナに、パルティナの表情も声も綻ぶ。
「そろそろ会議の用意をしなければならないから、今日はこの辺りで終わりにしようと思うのだけど……まだ元気そうね。ほどほどにするのよ?」
「わかりました。じゃあ続きは来週お願いします!」
エレナは素直に杖を仕舞った。
帰り際に、思い出したようにくるりと振り向く。
「そういえば、先生」
口角をにんまりと上げ、これまでパルティナには見せたことのなかった顔で悪戯な猫のように目を光らせていた。
「二年生の古典の、ギアー先生のことなんですけど」
「え? ええ」
「実際はどうなんですか? あの噂」
「……何の話でしょう」
眉を寄せるパルティナに対し、エレナはパッと笑顔を広げる。
「とぼけたって無駄ですよ。同級生同士で、卒業しても一緒に先生になるなんて運命みたいじゃないですか! みんな噂してるんですよ、先生たちのこと! 昔付き合ってたって本当ですか? それとも、今も秘密の関係? わたし的にはそっちの方がいいなって思ってますけど!」
「な……なっ!? 何ですか、それは!」
パルティナが動揺を露わにして声を荒げるのを見て、ますますエレナは上機嫌になった。
パルティナは知らなかったのだ。今までは、授業風景や放課後の自主勉強で出会う勤勉なエレナとしか話す機会がなかったのだから。
エレナの素顔とは、他人の恋愛沙汰を人一倍好む少女。
それは「パルティナ」と、その内に潜む「セレナーデ」には理解し得ない感情だ。
会議の時間だからと、パルティナはエレナを半ば追い払うように振り切って校舎へ戻った。途中でちらりと振り返ると、エレナは校門へ向かって歩き始めていた。
軽やかな足取りで下校するエレナの背中が、みるみるうちに遠ざかっていく。影が伸びて、心の距離も離されていったようだった。




スズライトは古い伝統を重んじる国である。他国ではとうの昔に廃れた魔術の力を現在も行使し、その源となる自然を守り、そこに棲まう妖精の加護を信じている。
元来、魔術とは人間に制御できるものではなかった。無秩序で、定められた法則がなかった。その理論を確立して体系化させ、誰にでも制御を可能にした人物は始祖の大魔導士と呼ばれている。その魔術の研究が行われていたのが、スズライトと名付けられたこの土地だ。
魔術の研究とはすなわち、世界の理を書き換えるに等しい行為であった。
妖精たちは魔導士とその協力者たちに手を貸し、人の世に多大な知恵と新たな文明をもたらした。文明を滅ぼされた事件の後のことである。妖精の力無くして世界の復活は成し得なかったことだろう。
一度滅びた文明を立て直す中で、世界は東西で大きく二分されたと言っていい。西に位置するスズライトでは、始祖の大魔導士らとその子孫たちが魔術体系を完成させた。一方、海を隔てた先にある東大陸はまるで異なった発展をしていった。彼らは魔術を介さずに別の手段で世界の法則を読み解き、科学文明を発達させた。
東西どちらにも共通して言えることは、長い年月がかかったということ。そしてその時の流れと共に、人間が妖精を知覚できなくなっていった点である。今や一体どれだけの人間が、妖精を信じているだろうか。彼らの存在を感じ取れているのだろうか。
どんなに敬虔で信心深いスズライト国民であろうとも、ほとんどの人間が妖精と交流する力を失っている。他国の状況と同じように、妖精の姿は認識されなくなり、声は届かなくなり、ついには存在そのものすら忘れられつつある。
要因は様々だ。人間の王が君臨するようになったこと、海を隔てた先にある大陸で魔術に代わって発展した幾つかの技術がスズライトにも取り入れられたこと、それによって魔術が淘汰されていったこと――総合するならば、人の世と文明の発展に起因していると言える。故に妖精は人間を責められなかった。
しかし、淋しさが募ることも止められなかった。妖精は人間と同じ心を持っていた。
二種族が共存していた時代は戻らない。それでも、少しでも、人間の傍に。昔のように。隣人でありたい。妖精たちはそう望むようになった。
妖精は森の中に住処を持つが、一定の周期で一人の人間に化けて外へ出てくる。そして、そのまま数年の間は人間として暮らす。
当初は人間を陰から守るために行われていたことだが、それが妖精自身の娯楽へと変化していった。破滅の日の再来に身構えることを忘れた日々はさながら、ままごと遊びのようだった。
彼ら六人の妖精たちも、満月の晩に年二回の情報共有会を実施してはいるものの、近頃は雑談をするばかりである。それが腑に落ちていないのは、六人の中でセレナーデのみであった。
彼女は仲間内の誰よりも生真面目だ。潔癖と言ってもいい。妖精たちの目的がすり替わっていく中、セレナーデはただ一人その風潮に馴染めずにいた。それほど気張る必要などないと仲間たちは言うが、セレナーデにだけはそうした楽観視ができないままだった。
興味のある人間、親しい仲になりたい相手にあらかじめ目星をつけ、それに合わせた立ち振る舞いをすることは妖精たちにとって珍しくない。だがセレナーデのそれは、他の者たちと比べると感情に乏しい事務的なものだった。
人間に好かれることが目的ではない。自身の役目はあくまで、人間たちの舞台が存続するよう守ること。そのために必要な人格や業務、立ち回りを吟味するのがセレナーデのやり方だ。
当然この考えは悪ではなく、立派な心がけであると言える。セレナーデと顔を合わせれば決まって口論を繰り広げてばかりのメヌエットも、彼女のそうした姿勢については異を唱えない。ひとえに人間たちを大事に想うが故のことで、その想い自体はセレナーデもメヌエットも皆変わらないものだ。
しかし、セレナーデは自分自身を不完全だと捉えていた。
昔も今も変わらずに、彼女は妖精として人間を愛している。
その一方で、恋焦がれるという感情が理解できないのだった。
パルティナは、年若い女性の新任教員である。
教育学部を修め、本年度からスズライト魔法学校に着任したばかり。担当する科目は魔術。ライトブルーの長髪をすっきりと一つにまとめ、二本クロスさせた紫のヘアピンをトレードマークとしている。好きな料理はシーフードパスタ。品行方正で正義感と責任感が強く、髪と同じ色の澄んだ瞳を光らせて鋭い物言いで指導をする。その姿は時に生徒から恐れられるようだが、臆することなく自分を貫く頑ななところもある。父も他校で教職に就いており、母は専業主婦。つい先日には誕生日を迎えたばかりだ。
――という設定になっている。
事実、パルティナは学校に通っていなければ正式な教員免許も取得していないし、教師の父親も持たない。教員免許状は偽装しており、家族は実在すらしない。故に誕生日も捏造である。経歴も全て作り物で、でたらめだ。
彼女には過去そのものが存在しない。
セレナーデが演じる、架空の人物。それが彼女の正体である。
妖精たちの力をもってすれば、人間社会を欺くこと自体は容易かった。彼らが人間に扮して森を出るときに用意するのは、ある一定の情報量を持った人物像のみ。それがさも事実であり疑いようのないことだと、高度な魔術によって人々を錯覚に陥らせる。人間が同じことをすれば法に触れる行為であっても、その「犯行」は人間には到底暴くことができない。
「パルティナ」の人格は、妖精の「セレナーデ」に近しい面が多かった。また、教師という役柄と学校という舞台は、真面目で実直な彼女と相性が良い。セレナーデが「パルティナ」の行き場所にスズライト魔法学校の教師を選んだ理由は他にあったが、快適な環境であることには違いなかった。
人間に化けている間、妖精はその人物らしい言動を完璧に演じようとする。しかし全てが演技とは限らない。妖精としての素の性格も、思考と感情も、変わらずに備え持っている。内面まで徹底して別人格へ成り代わるような妖精は、セレナーデの知る限りではいない。
セレナーデの意思も記憶も携えた人物として、パルティナという女性はこの世に生み出された。彼女が人間社会へ現れたのは、つい最近の春のことである。
春からの新年度に合わせて住処の森を出たセレナーデは「新人教師パルティナ」として真新しいスーツを身に纏い、さも当然といった顔でスズライト魔法学校の門をくぐった。「セレナーデ」には古くから馴染みある建屋を、「パルティナ」は新鮮な気持ちで見上げる。始まりの日に相応しい快晴の下、薄紅色の花びらがひらひらと舞っていた。
彼女が一年目に受け持つことになった学級は、自分と同じ一年生のクラスである。入学式で全校生徒へ挨拶をした後、教室で改めて顔合わせが行われた。新生活への期待と緊張に揺れる生徒たちの顔には、まだあどけなさが残っている。
自身の外見の若さ故に第一印象で軽視されないよう、パルティナはキリッと表情を引き締めて自己紹介をした。
教師と生徒の年齢が近いことは良い方にも悪い方にも作用するものだが、この場では少々悪い方へと傾いてしまったようだった。質問を促すと、浮足立った様子の生徒が一人、挙手をしてパルティナへ軽い口調で質問を投げかける。
「先生は、恋人っていますか?」
想像の範疇ではあった。生徒から教師へこのような質問が飛ぶのはままあることだ。
「いませんよ」
「じゃあ今好きな人は? 告白されたことは!?」
「何もありません。いいですか、大人にそんな質問は――」
「本当っすかー?」
「嘘だ~! 先生美人ですもん!」
パルティナは毅然とした態度で答えるが、続々と他の生徒たちも声を上げてくる。これ以上何と答えても無駄だと早々に悟り、自分への質問を強制的に切り上げさせた。この一件でクラスの生徒たちには親しみに欠ける印象を与えたようだが、致し方ないことだと諦めた。
職員室へ戻り、次は職員へ向けた自己紹介だ。自分ともう一人の若い新人に皆の興味が注がれているのがパルティナにはわかった。
「お二人は学生時代の同級生で、出身地も同じだそうですね」
ベテランらしい雰囲気の漂う女教師が尋ねる。
パルティナと肩を並べた眼鏡の男が、和やかな雰囲気で微笑みながら平然と答えた。
「はい。一人ではなくて嬉しいです。彼女は昔から優秀でしたから、僕は密かに憧れていたのですよ」
女教師が口元に手を当てて「まあ」と零し、彼女を含めた数人の先輩職員が目を丸くして二人を交互に見た。パルティナは居心地が悪かったが、無視して平静を努めた。
パルティナの同期となる彼の名はギアーという。紹介された通りパルティナとは学生時代からの知人であり、気心の知れた仲だ。
無論、これもまた「ギアー」の設定にすぎない。
ギアーは、妖精の仲間のプレリュードが構築した人格だ。プレリュードの外見年齢をそのまま引き上げたような、温厚そうな青年の容姿をしている。飄々として笑顔で煙に巻く言動も、素のプレリュードとほぼ変わらない。教員として受け持つ科目は古典ということになっている。
セレナーデとプレリュードは同時にこの学校へ「着任」した。それは互いに示し合わせた上でのことだった。
ギアーが丸眼鏡の奥に光るマリーゴールド色の瞳をスッと細める。
「今後ともよろしくお願いしますね、パルティナ先生」
先輩職員たちから向けられる好奇の目を意にも介さずにこやかに告げるギアーに、パルティナは内心頭を抱えたい思いだった。
一年を担当するパルティナに対し、ギアーは二年の授業をすることになっている。これは妖精たちによってあらかじめ決められた通りのことだった。そうなるように、彼らの魔術によって人知れず仕向けられていた。
どのような人間を演じ、どのように生きるのか。それらは各々の自由だ。だが時折「神」の啓示が下りることがあり、その際のみは例外である。
とある日暮れに、何の予兆もなく「神」は現れた。実に数百年ぶりのことであった。
一年後、スズライト魔法学校で「面白いこと」が起こる。
たったそれだけを告げると、「神」は地上を嘲笑いながら高みの見物へと戻っていった。
妖精と同様に遥か古代から世界を俯瞰している、運命の神々が気まぐれに命じる言葉。それは神託と呼ぶにはひどく曖昧であり、同時に意地が悪い。しかし、その預言は常に真であり決して抗えないことだと、この数千年で妖精たちは思い知らされていた。六人は緊急会議を開いた。
定例会に参加する六人は一つのチームのようなものだ。彼らの中には、常に必ず一人は人間に扮することなく妖精のまま待機するというルールが定められている。それはこうした突然の事態にも対処できるようにするためだ。発案者はセレナーデだった。
この時点で既にメヌエットとレクイエム、ラプソティーの三名は「人生」を始めており、商店街にそれぞれ店を構えていた。残っていたのはセレナーデ、プレリュード、ボレロ。そして、次に待機するのはボレロの番だと決まっていた。
「二人共スズライト校に行くのがよろしいですわね」
「それがええやろなあ。ほな、セレナーデは二連続で学校かいな。飽きひん?」
ラプソティーが話を振り、ボレロが少々げんなりした様子を見せる。セレナーデは静かに答えた。
「飽きるということは別にないけれど……」
「”前”は城下町んとこで学生やっとったな。せやったら”次”は先生でどや?」
「そうね。勝手もわかっているし。元々あそこにはソラがいたから、どちらかが行かなければならないとは思っていたわ」
セレナーデがこれまでに教師の人間を演じた経験は何度もあった。また、国内の様々な学び舎に新入生として紛れ込んだ経験も数え切れないほどあった。それはスズライト魔法学校に限らない。国内で最も難関とされる王立魔導学校。北部の山奥に佇むティンスター教会学校。商業科や医学科で専門的な学習ができるウェルシィ一校及び二校。異国文化を進んで取り入れているサンローズ学園。国内あらゆる地域の、学校と名の付く全ての場をセレナーデは制覇していた。
「では、僕も先生にしましょうか」
情報共有をしやすいようにと、プレリュードも教師として共にスズライト魔法学校へ潜り込むことが決まる。
話題は「神」の預言が意味するものの推測へと移った。
「珍しく口を出してきたかと思えば、いい加減もいいところだわ」
「何が『面白いこと』なの! ぜーったい何も面白くないの! 良くないことに決まってるのー!」
セレナーデが溜息混じりに愚痴を零し、メヌエットも後に続いて声を荒げる。妖精たちは皆総じてかの神々が好きではなかった。
「あの人らの感性はホンマにウチらと別物やからなあ。どうせ碌なことにならないんやろうけど……やっぱソラが危ないんやろか」
「そのことならレクイエムがいるのっ。ビシーッと守ってくれるから心配いらないの! ね!」
「………」
メヌエットが飛びつくようにしてレクイエムの手を取る。彼の左腕にぶら下がっている手枷が揺れて乾いた音を立てた。
ラプソティーは桃色の光を柔らかく明滅させ、セレナーデとプレリュードの二人に微笑みを向ける。
「今回の件について、お二人にだけ任せることはいたしませんわ。この一年間は、わたくしたちもあの学校に属する人間には特に注意いたしましょう」
「ウチはいつでも準備万端やからな! 何かちょっとでも気になったらすぐ言うてや! 任しとき!」
ボレロの赤色が激しく瞬き、燃える炎のように揺らめいた。
こうして、パルティナとギアーの教員生活が始まった。






かつて世界は一度壊れた。
ある一つの文明が滅び、人の世は根底から覆された。
だが世界は、その理を作り変えられて息を吹き返した。
新たな理を生み出した者たちは、ある者は始祖の大魔導士として後世へ長く語り継がれ、ある者たちは始まりの三賢者として星になり、ある者たちは時の流れと共に人々の記憶から忘れ去られていった。
滅んだ文明。再構築された理。存在した証が途絶えて歴史の闇に消えた数多の人間たち。
これらは記録が残っておらず、事実を知る者はいない。
悠久の時を過ごし続ける彼らを除いては。
崩壊と再誕から幾千年の月日が流れ、現在。
彼らはスズライトと呼ばれる土地に棲んでいた。
あたたかな月の光が暗い室内を照らしている。
満月が最も美しく輝く秋の晩、人間が寝静まった商店街。その一角の喫茶店に彼らは集う。シンとしたフロア内に、スズムシの羽音だけがかすかに聞こえていた。
並べられたカフェテーブルにもカウンター席にも人影はなく、月明かりが差し込む窓辺の隅にだけ六色の光が輪を作っている。
窓枠の最も近くに、桃色。そこから時計回りに橙、赤、黄緑、黒紫、青と並ぶ。光の中にはそれぞれ小人らしき影が浮いていた。
桃色の光がスッと高く浮かび上がる。光に包まれた小人は少女の容姿で、光と同じ色をしたボリューミーなロングウェーブの髪が波打っていた。ゼリーのように透明感のある瞳を細め、優雅に小首を傾げる。
「定例会を始めますわね。何か報告はありまして?」
「はいはーい、アタシから~♪」
黄緑色の光が正面でチカチカとまたたいた。中の小人は元気に挙手をしており、くるりと巻かれたポニーテールが左右に揺れる。
「はい、メヌエット」
「こないだのスズライト校のお祭りのことなの! 今回はかなり楽しかったのっ、ミリーが立派だったの~! ミリーはみんなの人気者だからずっとお友達に囲まれててね、アタシとおしゃべりはできなかったけど。でもでも、毎日いーっぱい練習頑張ってたの知ってるから、お歌のとき泣きそうになっちゃったの。あとねあとね――」
「黙って、もう結構よ。ここはあなたの個人的な感想を喋る場ではないと注意しなくてよくなる日は、いつになったら来るのかしら」
話を遮ると共に、水色の光が一際鋭く発光した。小人はサラリとしたショートカットを掻き上げて、小さな口から刺々しい言葉を放つ。
「それは別に必要のない情報でしょう。あなたはいつもいつも遊んでばかりね」
「セレナーデうるさい! アタシちゃんとやってるの! うーっ、こんな性悪女が担任の先生なんてミリーが可哀想なのっ」
「いつまで経ってもろくな知能がないあなたには言われたくないわ。せいぜい反面教師にはならないでちょうだい」
「ほんっとアンタはいちいちイヤミなの! そんな言い方しかできないの!? 大ッキライなの!」
「ええなあ、ミリーちゃんライブ。ウチも行きたかったー」
火花を散らす二色の向かい側から、赤色の光がマイペースな調子で割って入った。小人は内巻きのショートボブで、右耳の上に小さなサイドテールを作っている。メヌエットとセレナーデはほぼ同時に顔を背けて言い争いをやめた。
女性型の四人は、スカートの付いたレオタードのような格好で揃っている。ぼたついている大きめのアームカバーに腕のほとんどが包まれていて、人間に比べて細すぎる身体を一層華奢に見せていた。
「ボレロは学園祭の日どちらに?」
「同じとこにばっかし集まるわけにもいかへんし、海の辺りをぶらついとったなあ。なーんもあらへんよ。他の日もだいたいそんな感じやで。っちゅーか今のウチはどっちかってーと話を聞く側なんやけど? ラプソティーさんは何かあらへんの?」
話を振られ、桃色の柔らかな光を帯びたラプソティーはおっとりと答える。
「わたくしですか? 世は事もなし、ですわね」
「言うと思たわ。聞いたのウチやけど。平和なんはええことなんやけど、待機しっぱなしなんもそろそろ飽きてきたなあ」
「ふふ……心中お察しいたしますわ。けれど、こればかりは順番ですもの。有事に備えて控える者の存在も大事ですわよ」
「”次”にやりたい役柄はあるんですか?」
橙色の光が月明かりの照り返しを受けて控えめな輝きを見せた。中の小人は少年のようで、人間が使うのと同様の丸眼鏡を顔に掛けている。
彼の服装は四人と違い、一枚の白い布を身に纏った装いだ。襷のように肩から掛けて腰で結んでいる帯は、彼の光と同じ色をしていた。
「”前”は男やったから”次”は女がええけど……んー、まあでも今はそんだけやろか。仲良うなりたい子も特には見つかってへんし」
「ああ、そうでした。ボレロはそういう周期でしたね」
「何年の付き合いやと思っとんねん、ええ加減覚えんかい! ホンマにアンタは適当やな!」
「皆が僕と違ってしっかりしているものですから、ついつい」
「へいへい、どーも。あ、男の方が都合ええっちゅーんなら別に連続でも男やったるで。せやから、ウチの助けが必要んなったら早よ教えてな!」
「ええ、頼りにしていましてよ」
「うぅーん、ボレロは変わってるの。アタシはアタシのままがいいの~。レクイエムだっていつも男の子なの」
「………」
黒混じりの深紫色の光がぼんやりと明滅を繰り返した。顔のほとんどが黒髪に覆われていて、その表情を窺い知ることはできない。
彼の容姿には、他の五人にはない彼だけの特徴が複数見られた。もう一人の男性型と同系統の衣服を身につけているが、彼の左手首には手枷がぶら下がっている。ただ、途中で鎖が切れており手錠としては機能していない。黒が混ざった鈍い光を帯びているのも彼一人だ。
また、五人の背には半透明の羽が四枚付いているが彼には二枚しかない。何よりも、形が明確に違っていた。楕円形の五人に対して彼の羽はコウモリのシルエットに近い。翼竜か、悪魔にも似ていた。
レクイエムと呼ばれた彼は、非常に無口だった。自分が話しかけられても周囲がどれだけ騒ごうとも、言葉を発することがない。
「あなたたちは性別以前の話でしょう。特にレクイエムは論外だわ。いい加減に態度を改める気はないの?」
「………」
「……メヌエットも。近い周期で人間と接することもあるのだから、少しは人格を演じることを覚えなさい」
「アンタに命令されたくないのっ。レクイエム~、セレナーデがいじめるの~」
「………」
「毎回セレナーデはマメですよね。まあ、レクイエムはまた別問題ですが、常に自然体のメヌエットも僕は好ましいと思いますよ」
「あなたはどっちの味方なのよ」
「おお、怖い怖い。敵も味方も何もないではありませんか」
「真面目なのはセレナーデの美点ですけれど、そこまで神経質にならずともよろしくてよ? 不審に思われることがあろうと、認識阻害でも記憶操作でもいくらでもやりようはありますもの。違くて?」
「ラプソティーまでそんなことを……」
「諦めや。こういう人やんか」
げんなりするセレナーデと微笑むラプソティーの間に、ボレロはするりと場所を移した。青と赤の羽が重なり、薄紫色を作り出す。その横でレクイエムにぴたりとくっついていたメヌエットはフフンと得意げな笑みを浮かべた。レクイエムは誰にも何の反応も示していなかった。
「まだ学校の話はあまり詳しく聞けていませんわね。他の日ではいかがでした?」
「アタシの知ってる子はみんな元気なの! ただ、でも……ミリーのお友達のクレアちゃんが、ちょっと前に倒れちゃったの。今はウェルシィに入院してお休みしてるけど、心配なの……あの病気は……」
「ちょっと、尋ねられているのはあなたではなく私たちよ。というか、それを報告するなら学園祭より先に話すべきでしょう。相変わらず馬鹿ね」
ラプソティーは話の軌道を元に戻そうと試みていたが、またしてもメヌエットとセレナーデの衝突が始まり苦笑いを禁じ得なかった。セレナーデの小言は続く。
「メヌエットの話には主観が入りすぎだわ。日々の様子を見るに、彼女たちはそこまで気を回さなくても問題ない範疇。それよりも監視すべきなのは、やはり――」
「うっわ、ヤな言い方なの。自分とこの生徒を監視なんてヒドイの、怖い先生なのー」
「話が進まないから黙っててくれないかしら!?」
レクイエムにしだれかかったまま煽るメヌエットに、ついにセレナーデが声を荒げる。猫が毛を逆立たせるように、水色の光の輪郭がブワッと膨らんだ。ボレロは呆れて頭を掻いたが、二人の間に挟まれているレクイエムは尚も無反応であった。
ラプソティーの右隣から橙の光が回り込んできて、困り眉で笑いかけながら申し出る。
「僕が話しましょうか」
「お願いしますわ」
「セレナーデが言おうとしたのは、ソラの件ですよね?」
「……ええ」
不服そうな顔をしながらもセレナーデは低い声で答えて頷いた。彼が代わりにラプソティーへ語り始めると、深く溜息をつく。ボレロが一言声をかけた。
「同じこと何百回やるねん。よう飽きひんなあ」
「私に言わないで」
セレナーデは唇を尖らせ、第三者のボレロにも苛立ちを隠そうとしない。だがボレロが気分を害した様子はなかった。
報告を聞き終えたラプソティーが感想を述べる。
「――つまりは、ひとまず彼の身には何事もなかったという結論でよろしい?」
「要約すればそうなるでしょうか。とはいえ、ソラには引き続き気を配っておくべきとは思います。皆も知っていてください。もし何かあればレクイエムの力も借りることになりますからね」
「……めんどくせ」
初めてレクイエムが返答をした。しかし、たったそれだけぼそりと言った後はまた口を閉ざした。先端の尖った羽が気だるげにゆっくりと上下する。ボレロはそれを視界の隅に捉えて僅かに眉を寄せた。彼女はレクイエムに近付きたくなさそうにしていたようだった。
「わかりましたわ。プレリュード、他に貴方個人からは何かございまして?」
ラプソティーの問いかけに、ニコリと笑顔を返す。
「いいえ。僕の生徒たちは平和そのものですよ」
プレリュードは終始自分のペースを乱さなかった。
窓の向こうで、星空の端が徐々に白んでいく。夜明けが近い。
「では、今日の定例会はここまでとします。お時間をいただいて感謝いたしますわ」
淡々とラプソティーが締めて、場は解散となった。
「次もおもろい話よろしゅう~」
「早く帰ろっ、レクイエム♪」
「………」
真っ先に消えたのはレクイエムの黒紫だ。メヌエットの黄緑がその後を追い、次いでボレロの赤。少し遅れてプレリュードの橙とセレナーデの青が同時に消え、ラプソティーの桃色だけが残った。
ラプソティーは一人、窓に振り向き満月を見上げた。無数の星に囲まれた満月が瞳の中で瞬く。彼女のその姿は、窓に映っていなかった。
妖精たちが世界に生まれ落ちて、およそ千年が経つ。
いつ誰に名を与えられ、どのようにして自我が芽生えたのか、彼ら自身も理解していない。しかしそれに疑問を抱くこともない。寿命や死という概念に捉われない彼らは、長年を過ごすうちに自己への頓着すら希薄になっていった。
妖精たちにとって、この世とは劇場である。
彼らが望むのは、舞台の共演者であること。
それはすなわち、人間と共にあること。
世界という名の舞台の上で、人間の真似事を演じながら、妖精たちは終わらない劇を繰り返している。
彼らの本能には、人間を愛し守護すべきであるという意思が刻み込まれていた。
かつての文明の崩壊の日に居合わせた妖精は、ただ一人。それは六人の誰でもないが、その無念と痛みの記憶だけが彼らには継承されている。無意識化に刷り込まれたとも言えるほどに、妖精たちの心の深くに根付いている。
元々妖精たちが「劇」を始めたのは、人間と人間の築いた文明が二度目の惨劇に苛まれぬよう守るためだった。
しかし、ここ数百年は平穏な日々が続いている。平和を脅かす一大事の起きることがなくなった今、妖精の加護はもはや不要となっていた。
妖精たちにはただ悠久の時が与えられた。
次第に妖精たちの「劇」の目的は変化し、人間の傍で人間と共に暮らすこと自体に意味が見出されていく。滅びなどそう何度も訪れはしないと、徐々に楽観的な思想へと傾いていく。
義務を見失った者たちは、遊び始めたのだ。
これは暇を持て余した妖精たちの、長い遊戯の記録。






娘の旅立ちは、胸に思い描いていたそのときよりもずっと早くに訪れました。
ザルドの森を抜けて、緩やかな坂を道なりに東へ下った先に、ウィードリードという町があります。王都ヴィオリダのような華々しさや国内最大規模の港町イリンレのような美麗さはないけれど、牧歌的なレンガの街並みと豊かな自然に彩られた素敵な町です。
私の娘は今日、ここの港から船に乗って国外へ旅立っていきます。
「お母さん! 港ってあっちだよね!」
駅を出る前から既に、娘はそわそわと落ち着きのない様子でした。町に到着すると跳ねるような足取りで先に行き、道の遠くを指差します。夫の髪質と私の髪色をそれぞれ引き継いだ、外に跳ねた金色のショートカットが春の日差しを浴びてキラキラと光りました。
「ルミナ待って、そっちはお父さんの造船所よ。船着き場は向こう。それに、先にお昼を食べてからって話でしょ」
「あっ、うん、そうだった!」
一人駆け出そうとする娘を呼び止めて、家の近くには無いお洒落なテラス付きのレストランへ向かいました。窓辺の小さなプランターに植えられた草花が風に揺られ手を振っているようです。
娘は隣国のスズライトで魔法について学べる日を心待ちにしていました。今朝もいつもならまだ寝ている時間に起き、夫の出勤に付いていきたがっていたほどです。
当初の予定では昼食を採ってからヴィードリード行きの機関車に乗るはずでしたが、娘が居ても立っても居られない様子で早く行きたいと言うので一時間半も早い便で来ています。笑顔の絶えない娘に、私は胸の内で吹きすさぶ寂しさを悟られないよう努めて微笑みかけていました。
デザートセット付きのランチを食べ終えて、賑わう港へ足を踏み入れます。新学期前の休暇期間を満喫している若者たちの姿が多く見られました。
ラグライドとスズライトでは、一年を十二ヶ月とする暦は同じですが新年度の始まりが異なっています。スズライトの方が一月早く、また、学校へ通わせる年齢にも違いがあり、スズライトの子供の方が一年早く通学を始めます。
スズライト魔法学校へ編入するための資料を取り寄せたときになってようやく、私はその差を思い出しました。
スズライトは私の生まれ故郷であり、娘が通うこととなる全寮制の学び舎もまた、私の母校です。
その名を見て、今のラグライドの家へ嫁いできたときに蓋をした数々の思い出が蘇りました。あの学校に通っていた頃、私はまだ今の娘のように純真に、真っ直ぐに、優れた魔導士を志していたのです。何にも気付かず、何も知らずに過ごしていたあの日々の思い出は、今も柔らかな光を湛えて私の胸の中に眠っています。
ですが、王立魔導学校に進学して研究を進めていく内に、私は一つの仮説に気付きました。自分が手に入れたと信じていた力など存在しなかったのだと知りました。
全ては人ならざる者の手のひらの上。それを認めなかった学会も、認めた上でそれを享受する両親たちも私には受け入れられず、そのときスズライトという国に私の居るべき場所はないのだと悟ったのです。
私は否定の言葉から逃げ出し、母国スズライトを見限りました。あれから十数年もの時が流れました。
そんな私の一人娘が魔術に興味を持ちあの国で学びたいと言い出すなど、一体何の因果なのでしょう。
娘を送り出すのは複雑な気持ちでした。しかし、親の私情で子の考えを否定することも断じてしたくなかったのです。
夫が私の心境を慮ってくれていたことは幸いであり、大いに支えられました。ただ、夫は私とはまた異なった意味で娘の留学を不安がり、気が気でない様子でした。
『スズライトに行くなんて、思い切ったことを考えたよなあ……』
『あなたったら、何度目? ルミナだっていつまでも子供じゃないのよ。やりたいことがあっていいじゃない』
『うん……そうなんだけどね……スズライトの魔術は立派なものだし……。ああでも、船を降りてから学校まで、一人でちゃんと着けるだろうか……? 仕事さえなければ僕が行けるのに……』
その呟きに、胸の奥で罪悪感がちくりと痛みます。勿論夫は純粋に娘が心配なのであり、他意はなかったのでしょうけど。
ですが、夫が何と言おうと、私は海の先まで娘に付き添うつもりはありませんでした。
『……ほとんど平原で複雑な道じゃないもの。地図もあれば、大丈夫よ』
学生時代の記憶を頼りに手書きで地図を作りながら、私は夫の顔を見ないようにしていました。
停泊している白い船の中に、一回り大きな客船があります。あれがスズライト行きの便のようで、予定より早く港へ着きましたが問題なく乗船することはできそうです。
暮らしに必要な生活用品の類は事前に向こうへ送り届けてありますので、娘の手荷物は全くありません。私はその手に子供料金の乗船券一枚と地図を持たせました。
「ちゃんと着いたら連絡するのを忘れないでね?」
「うん、わかってる! ちゃんと手紙書くし、夏休みにも帰って来るよ!」
娘は明るく船に乗り込んでいきました。新天地での日々に心配事などない様子であり、純真に育ってくれたことは喜ぶべきなのですけれど、かえってこちらが少々心配です。私が寮に入って初めて一人暮らしを始めることになったときは、もう少し緊張で硬くなっていたものでした。
出航の笛の音が響き、船がゆっくりと動き始めて、静かだった水面に波が広がります。
船の姿が小さくなって地平線の彼方へすっかり見えなくなるまで、私は見送り続けました。船の通った跡が弱く揺らめき、そして元の静けさへと戻っていきます。高い空から注ぐ日差しで煌めいた海は、船が進む先を祝福するように美しい光景でした。
母親として不安はあるけれど、恐らく案じることはないのでしょう。
推測ですが、今朝の夫の様子がそれを物語っています。
娘を単身スズライト行きの船へ乗せることに渋っていた夫が、ある日を境にぱったりと不安げな素振りを見せなくなっていました。それから、彼は私の目を盗んでどこかに手紙を送っていたようでした。これは彼の長所でもありますが、私の夫は隠し事があまり上手ではないのです。
あの人の行動が何を意味するのか、私には何となく察しがついていました。その上で、彼の優しい企みに気付いていないフリをしました。たとえ何の意味もない振る舞いだとしても、私は自身の意地とプライドのためにそうせざるを得ませんでした。
ウィードリードまで来たついでに、と、私は市場で夕飯の食材を購入しました。そして一通りの買い物を済ませた後、最後にもう一度海を眺めてから帰ろうと思い港の前に立ち寄りました。
そこに、夫が現れました。
「あ、あれ? マリさん一人なのかい? ルミナは……?」
「あら? あなた。まだ仕事よね?」
「今だけ抜けてきたんだ、せめて見送りはしたくて。三十六分の便だろう」
夫は仕事場の作業着姿で、走ってきたらしく息が上がっています。娘の姿を探す夫に経緯を説明すると、みるみるうちに落胆と焦燥を露わにしました。
「そ……そうなんだ……そうか……」
単純な寂しさから来る感情にしては焦りが色濃く見えました。
私が訳を尋ねると目を泳がせて、ぽつぽつと白状し始めます。
「……君は大丈夫と言うけど、一人で行かせるのはやっぱり心配だったから。どの船で着くのか教えて、迎えを頼んでいたんだ……」
誰に? と、聞くまでもありませんでした。夫がスズライトで頼れる人物の心当たりなど、一つしかないのですから。
「……お義父さんたちに」
「そんなところだと思っていたわよ」
「バ、バレてたのか……」
溜め息交じりに言うと、夫は本当に意外だったようで目を丸くしました。
「あなたはわかりやすいもの。そう……でも、二人にルミナを会わせたことは……」
「ないけど、でもお義父さんたちならわかるはずだよ。ルミナは君と顔がよく似ているから」
優しい声と表情で、夫は穏やかにそう言いました。
しかしそれも束の間、またすぐに不安を口にして、肩を落とし踏ん切りがつかない様子で職場へ戻ったのでした。
どこかで汽笛が鳴り、また船が一隻港を出ていきます。
十数年もの間、私は両親と連絡を取っていません。私がスズライトの土地に足を踏み入れることはもう二度とないのです。
夫は、二人に何と書いて伝えたのでしょうか。
二人は、夫の手紙に何と答えたのでしょうか。
娘から手紙が届いたのは、翌々日。スズライトには転移魔術を用いた郵便システムがありますので発送後にすぐ届くのが普通なのですが、国外への郵便物には対応できなかったようです。封筒に捺された印字は、引っ越し日の翌朝を示していました。
「お父さん、お母さんへ」から書き始められたその手紙には、祖父母に関する記載は一言もありません。しかし学生寮へは何事もなく無事に辿り着けたことが窺える内容で、夫は心底安心していました。
同時にもう一通届いていましたが、そちらの宛名は夫の名のみ記されています。夫は私の前では封を開かずにそのまま懐へ仕舞いました。私はまた何も気付いていないフリで、娘の手紙に意識を向けさせました。
「ね、心配いらなかったでしょう」
「そうだね。……もしかしたら、妖精が見守っていてくれたのかもしれない」
夫は少し躊躇いながらも、その言葉を口にしました。
私が返事に詰まると、眉を下げて微笑みます。
「君がこういう言い方を良く思わないのも、その理由も、わかってるつもりだけどね。それでも、僕は信じてみたいんだよ」
隠し事や嘘が上手ではない、純真な人。私の同意は得られないと想像できていたのだとしても、口に出さずにはいられなかったのでしょう。
「ルミナはあなたに似たわね」
きっと私も、彼と同じ表情をしていたのだと思います。
職場へ向かう夫を玄関先から見送った後、一人になった家の中で、私は改めて娘の手紙を読み返しました。そうしたところで、心の中の曖昧な感情が晴れることはないのでした。

暖かい春の日。
来店の瞬間から、わたしは彼女たちに注目していた。
スズライト魔法学校のセーラー服を着た二人組。わたしと同じくらいの年の女の子たち。二人は窓際のテーブル席に向かい合って座った。
業務の合間に、横のテーブルを片付けるフリをしてそれとなく近くへ行ってみる。立て掛けてあるメニューの角を揃えて綺麗に整頓しながら、顔に出さないようにしつつ耳をそばだてた。
「美味しいっ! 凄く美味しいねこれ!」
先日から新発売したばかりのパフェを嬉々として頬張っていたのは、ちょっと幼げな雰囲気の方の子。小さな体と桃色のツインテールが庇護欲を掻き立てるような容姿で、黒縁の野暮ったい眼鏡に隠し切れていない大きな瞳も愛くるしい。
声を弾ませて、パフェの感想を述べてくれている。
「これはさしずめ甘味の壺といったところね! 生クリームとアイスが上から蓋をしてて、その蓋がちょっとずつ開けてくると中のイチゴソースから香りが漂ってくるの。この刺さってるシュガースティックは、えーっと、そう! 鍵!」
ああっ、やっぱりこの声と喋り方は絶対ミリーちゃんだよーっ! みんな何で気付かないの!? 気付かないフリしてくれてるの!?
「何だかグルメリポートに来たみたいだよ」
一緒にいるのはきっと、ミリーちゃんの友達。穏やかな笑みが、ミリーちゃんと並ぶと少し大人っぽい印象の子だ。頭上で結わえたお団子が、実際より背を高く見せていることも理由の一つかもしれない。
わたしは彼女の言動にも注意を払う。
というか、実のところはミリーちゃんよりも彼女の方に強く気を配っていた。
ミリーちゃんの来店は大事件。でも別に、声をかけたりサインを頼んだりするつもりは全くない。わたしも業務中だし、何より今のミリーちゃんは、アイドル活動を休んで一般の女子学生として青春を謳歌している真っ最中だから。プライベートを邪魔するなんてファン失格でしょ!
だからミリーちゃんのことはいいんだ。楽しそうに笑う彼女のことは、そっと見守っていよう。
それよりも、このエメラルド色の長い髪をした女の子の方だ。
わたしは人捜しの手伝いをしている。その人物の身体的特徴と、彼女はよく合致していた。
名前はティティといって、わたしと直接の面識はない。一度だけ同じ場にいたことがあるらしいのだけど、顔も声もほとんど覚えていない。ただ、わたしの大事な親友たちが彼女の安否を心配しているから、わたしも彼女を捜している。
ある冬の日に突然の失踪をしたティティ。でも、まだこの国のどこかに生きているとあの子たちは信じている。それなら、わたしが手を貸すのは当然だ。
ティティに似ている彼女の顔をどうにかして正面から自然に見れないか、と思いを巡らせていると、後ろから呼びかけられた。
「ティーナ先輩! 注文お願いしまーす!」
「えっ。あ、みんな……!」
飛び級で入学と卒業をしたわたしのことを「先輩」と呼ぶのは、同じチア部の子くらい。振り向くと、サンローズ校指定のブレザーを着ている見知った顔が並んで笑みを向けていた。中には知らない子もちらほらいて、彼女たちはわたしが卒業した後に入ってきた後輩なのだろうということが察せられた。
雑談交じりの軽い感じでオーダーを取りながら、後輩たちと過ごした部活のことを思い返す。
年下の先輩なんて存在は面倒だっただろうな、と自分でも思うけど、みんなは嫌な顔せずにわたしと接してくれていた。今もこうして、一昨年卒業したわたしのことをまだ覚えていて親しげに声をかけてくれる。
それ自体は嬉しいんだけど、今だけはちょっと困るタイミングだったかも。……後輩の優しさをそんな風に思ってしまう自分は、嫌な性格だと思う。
オーダーを通した後にもう一度ミリーちゃんたちのテーブルへ近付こうとしたけど、また後輩たちに捕まってしまった。近いには近い場所だけど、こっちの席に向き合うと二人には完全に背を向けてしまう。
これじゃもう顔を見るどころじゃないや。
それでも、後輩たちの話に付き合うフリをしながら彼女たちの会話には聞き耳を立て続けた。
そして、他人の空似だろうという結論に至った。
この子の名前はネフィリーというみたいだし、親友たちの証言によればティティはだいぶ気が強かったそうだ。ミリーちゃんの話に優しく相槌を打っている大人しい彼女と同一人物だとは思えない。
チア部のみんなは同級生の男子の話に花を咲かせている。その間に、彼女とミリーちゃんは会計を終えて帰っていった。
こちらの会話に上の空だったのを勘付かれてか、軽く突っ込みを受ける。
「先輩聞いてる!? それで、その転校生が超紳士だったんですよ! 眼鏡もかっこよくって~!」
「うちにホウキレース部があれば良かったのに! そしたら部活で応援しに行けたよねー! いっつも一位らしいよ!」
どうやらみんなの間では転校生が話題らしい。知らない男子生徒の話で盛り上がるみんなを愛想笑いで流し、仕事を思い出したフリをして、わたしはそっとその場を離れた。
元々、わたしは昔から恋の話には乗れない性質だ。適当に調子を合わせつつ今まで過ごしてきたけれど、本当はみんなと同じ熱量を抱くことがどうしてもできなかった。
身近にいた男たちが原因じゃないかと自分では思っている。特に幼馴染のシザーは乱暴な悪ガキだし。最近ではキラのはっきりしない態度にもイライラする。
お父さんとお母さんだって、お互い容姿や人柄に惹かれて結婚したのではないだろう。お父さんが求めたのは”丘の上”の立場。お母さんはそんなお父さんの甘言に気を良くしているだけで、一番大事なのは自分自身だ。
現実から目を背け、恋に恋をすると言うように理想を描いて憧れたこともない。わたしにできるのは、せめてみんなの想いに水を差さないようにすることだけだった。
夜、店を閉めていつものように店長と二人で後片付けをしていたら、「後輩に会ったのは久しぶりなのかしら? 楽しそうだったわね」と微笑ましいものを見る目で言われた。
楽しそうに見えていたのなら良かった。
親友たちが捜している人は、もう一人いる。
ティティとほぼ同時期に消息不明となった少年。スズライト魔法学校の校長の孫で、スズライト家長女のメアリーとお見合いをするはずだった相手で、キラの兄。名前はソラ。
メアリーとの縁談の席には、本当なら彼がいるはずだった。
その名前以外、わたしは彼のことを一切知らない。どういった人物なのか何の情報も持っていない。それどころか、当のメアリーでさえソラとは面識がない。ソラが行方をくらませたのは、彼とスズライト家の顔合わせの日の直前だったからだ。
もしもそうならなかったら、今頃はどうなっていたんだろう。メアリーも、キラも、わたしも。
もしもソラが相手だったら、わたしは安心してメアリーを任せることができた?
もしもソラが見つかったら、今からでもメアリーの相手は変わるの?
そうして浮かんでしまう「もしも」を振り払うように、わたしは首を横に振る。
今更、考えたって無駄なことなのだから。
今日は珍しくキラが来店していた。その姿を見たせいで、嫌な感情が膨れ上がっているんだ。
キラは見知らぬ女の子と一緒だった。ただのクラスメイトだと彼は言った。だけど、自分から異性を誘うのに慣れているような人じゃないってことは屋敷での言動を見ていればわかる。メアリーとは一度だって出かけたことがないはずだ。
外向きに跳ねた金髪の女の子が、キラの隣に座って笑いかける。キラは時々彼女の方へ顔を向けて、目が合いそうになるとふっと逸らし、コーヒーカップに口を付ける。そうした一連の様子を、わたしは目にしてしまった。
その席にいるべきなのは、艶やかで美しい黒髪のメアリーだ。なのにどうして、別の女を座らせていられるの。罪悪感も何もないというの?
その程度の安い気持ちで踏み込んできて、メアリーと目を合わせないあの男が、わたしは憎い。メアリーはこの男のどこがいいのか、わたしにはさっぱり理解できない。
心が乱れて、今日の仕事は本調子が出ない。店長はどこまでお見通しなのか、わたしの表情をやんわりと指摘した。キラと彼女が出ていった後だった。
「眉間に皺が寄っていてよ」
「……すみません」
「珍しいわね。何か困ったことでもあるのかしら?」
「姿を消した兄の存在に甘えてメアリーと真面目に向き合おうとしないキラに腹が立っているんです」……などと、正直に話せるわけがない。
ソラの一件によるキラの心労はわたしも理解しているつもりだ。兄のことは諦めろ、と突き付けるのはさすがに酷だろう。
でも、それがわたしの本心。
だってそうでしょ。
ソラもティティも、いなくなった日からもう半年過ぎた。名家スズライト家も彼らの捜索に力を貸しているというのに、何の情報も出てこない。この状況で希望を持ったところで、それは逃避でしかないとわたしは考えてしまう。帰るかどうかもわからないソラより、今ここにいてキラを見つめているメアリーに目を向ける方がずっと建設的だ。
ソラの行方不明事件については、店長にも当然尋ねたことがある。さっきまでカウンター席に来ていたキラが彼の弟だということも、この人なら多分把握しているだろう。商店街をよく利用する近隣の住人や近辺の学生の顔はだいたい全部覚えていると話していたし、日頃の接客を見てもそれは誇張ではなく事実だと思うから。
店長は人が好きだ。一度でも接した相手のことは忘れないと豪語し、実際に顔が広い。そんな店長に向けて、わたしの冷ややかな胸中を打ち明けるのは憚られた。
「大丈夫です。仕事の後の予定が気になっちゃって。集中します」
「そう。ならいいけれど」
店長はわたしから視線を外し、カウンター裏の棚からグラスを取り出して並べ、アイスティーを注いだ。
「……ちなみになんですけど、ソラの件って何か新しい話はありましたか?」
「いいえ、残念ながら。悪いわね」
「そうですか。店長の情報網なら捜せない人はいないと思ったんだけどなぁ」
「一体私を何だと思っていて? 過度な期待はしないでちょうだい、情報網だなんて大それたものではないわ。私が知っているのは、全て単なる噂話よ」
「いやいや、案外そういうのって侮れないものじゃないですか」
店長とラフなやり取りをする内に、少しだけ調子を取り戻した気がする。残りの勤務時間は何事もなく過ぎ去っていった。でも、キラへの苛立ちが消え失せることはなかった。
『……六時、また来て。言い訳はそこで聞いてあげる』
『………』
店の前に立っているキラを見かけて声をかけたとき、先に約束を取り付けておいて正解だったな。あいつは一度問いただしておかないと、わたしの気が済まない。たとえあの子自身が許したとしても、わたしの心が許さない。
メアリーには何も頼まれてない。だから勝手なことだと自覚はしているけど。
でもこれは、メアリーのため。わたしが動かなくちゃ、メアリーは自分の想いを押し殺してしまうに違いない。
あの子の幸せのためならわたしは何だってやるし、何にだってなる。
仕事から上がってスタッフルームへ入ると、向かいの窓から夕陽が差し込んでいた。沈みかけた西日の真っ直ぐな明かりに、今はただ腹立たしさを覚える。カーテンを一気に引いて閉め、黒いリボンタイを乱暴に解いた。
向こうが逃げ出していなければ、外にキラが待っているはずだ。
全部はっきり言ってやる。わたしが言わなきゃ、メアリーは文句の一つも絶対に言わないから。
髪をきつく結い直して支度を整え、従業員用の裏口から店を出ると扉のすぐ横にキラが立っていた。顔を上げた彼と視線がぶつかる。
決まり悪そうな、自分も被害者だと訴えるような、情けない顔。それは日陰の下で鬱屈さが増していて。
ああ、本当に腹が立つ。
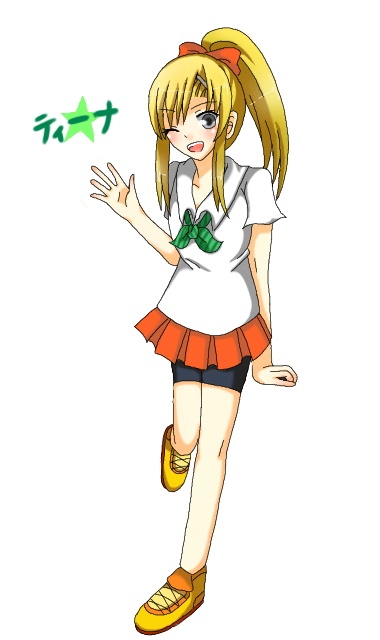





学校の敷地内を、当てもなく彷徨う。
声が聞こえない場所を探していた。
階段の下の空きスペースは身を隠せる場所の一つだけど、人通りがあると隠れていても意味がない。誰かが一人でも傍を通れば、その「声」は勝手に私の中へ流れ込んでくる。大抵は他愛のない呟きがほとんどだが、それがどんな些細な内容であっても耐え難いくらい、今の私はこれまでの心労が積み重なって疲弊しきっていた。
校舎から、中庭へ出る。ここにもぽつぽつと生徒の姿があった。初夏の日差しの下で弁当箱を広げて輪になり、楽しげに談笑している。弁当の他に、お菓子の袋のようなものも置いてあった。夏休み前の定期試験が先日終わったばかりだから、皆浮かれているようだ。
その能天気な顔を見ていると、昏い感情が渦を巻いて沸き出てくる。彼らから目を背け、頬を伝う汗を拭った。
俯いて足早に中庭も通り抜ける。講堂からは中で人がドタドタと走り回っている音がしていた。賑わう食堂にも当然立ち入らない。
どんどん敷地の隅へと逃げ込んで、ついには最奥にある石造りの塔の前にまで来てしまった。
大昔、元々この学校は別の施設だったらしい。この塔は当時の名残の一つで、創世紀時代のものだという古い本が数多く格納されている。けど、校舎の方にも広い図書室があるから、余程目当ての本がない限りこんな奥まで足を運ぶ機会はないと思う。
この塔なら、誰もいないかもしれない。
アーチ型の入り口の扉はほぼいつでも開放されている。中をくぐり、壁沿いの螺旋階段を反時計回りに上がっていった。
この学校に入学して二年目の夏だけど、初めて入る。
石の壁に触れると冷たくて、一定間隔で開いている窓からは柔らかな風が吹き込んでいた。
階段を上り切った先に一つだけ部屋があり、そこは図書室と言うよりも書庫と表現するのが相応しい場所だった。机も椅子も無く、ただひたすらに、棚の中から床の上にまでずらりと本が置かれている。床に縦積みされている書物の中には、人が腰を下ろせそうなほど大きく分厚い物もあった。重い表紙を持ち上げて開いてみると、掠れたインクでページ一面に大きな魔法陣が描かれている。添えられた文字は恐らく古代語で、読めない。古い魔導書のようだ。
私はゆっくりとその魔導書を閉じ、日陰になって薄暗い部屋を歩き回ってみた。物音や人の気配がしなくて、とても静かだ。張り詰めていた心が少しだけ解れるのを感じた。
壁際の棚に並ぶ本の背表紙の題名を眺めるが、そこにも古代語と思しき見慣れない言語が混じっている。読めそうな本を適当に一冊抜き取ってパラパラ捲ってみたものの、びっしりと綴られた内容は難解だ。魔法の授業の参考書とするにはレベルが高いように見えた。
魔術科の成績が優秀なエレナさんなら、こういった本も読めるのだろうか。
友人でもない彼女のことが頭によぎったのは、こんな私にも毎日声をかけてくれるような人だから。
先日も、他のクラスメイトに向けるのと変わらない笑顔で、夏休みに一緒に遊ぼうと私を誘ってきた。それは決して純粋な厚意のみではなく、表に出さない感情もあることが私には聞こえていたけれど。
エレナさんのことは信じられるのかもしれない……と、少なからず感じている。でも、返事をすることができなかった。
問題はそのことだけじゃない。夏休みの過ごし方自体、今も悩んでいる。こんなにも憂鬱な夏は初めてだ。
他人の心の声が勝手に聞こえてくるようになってから初の長期休暇。どこへ出かけるにしても大勢の人で賑わっているだろう。数十人程度の教室の中ですらも耐え難いのだから、それ以上に混雑している場所へ飛び込むなんて自殺行為だ。
帰省についても同じ。両親も弟も優しい人たちだから、話せばきっと相談に乗ってくれるだろう。でも、こんな得体の知れないものをどうすることができる? きっと、ただ心配をかけてしまうだけ。
それに、拒絶される不安と恐怖も拭えない。家族も、他の人々のように笑顔の裏に黒い感情を潜めていたとしたら。厄介事を持ち込んだ私のことを迷惑だと感じられてしまったら。
最後の拠り所にさえも裏切られてしまったら、信じられなくなってしまったら、私はもう、生きていけない。
でも、皆が皆悪意を抱いているのではないと本当はわかっているくせに、そうやって人を疑ってばかりの自分自身のことが何よりも心底嫌いだ。
重い本を抱いたまま、ずるずるとしゃがみ込む。その膝に顔を埋め、深く溜息を吐いた。
具合が悪いのか? と尋ねられたのは、そのとき。
男の子の声だ。
ガバッと顔を上げて振り向くと、背後に細身の男子生徒が立っていた。若干身を引いて、困惑よりも驚きが強く表れている瞳と視線が重なる。
サラサラとした真っ直ぐな銀髪。
隣のクラスのキラくんだった。
直接の面識はないものの、彼のことは知っている。同じクラスになったことはないし、目が合うことすら初めてだと思うけど、噂が「聞こえる」ことは度々あった。勉強も運動もスマートにこなして、そのクールさと中世的で整った顔立ちなどが密かに女の子から人気みたいだ。大々的に騒ぎ立てられてはいないようだけど、二クラスで合同の体育のときなどは特に、女子生徒たちの注目を集めていると知っている。
キラくんには一つ年上のお兄さんがいて、去年少し話題になっていたようだけど、その件については私にはあまりわからない。あの頃はまだ他人の心の声が流れ込んでくることはなく、私自身もその噂に対して強い関心は持っていなかったから。
何も言わない方が感じ悪いか、と先程と同じ声が聞こえてきた。
キラくんの口は開いていない。だから、これは彼の心の中の声なのだろう。
心の声とそうでない本物の声は、音だけでは区別をつけられない。その人の口や目の動き、表情の変化も見て初めて判別できる。最初に聞こえてきた「声」も恐らく彼の心の中での呟きで、口に出してはいなかったのだと思う。キラくんにしてみれば、私が人の気配だけで急に振り向いたように見えたに違いない。
キラくんは徐々に普段通りの冷静な調子を取り戻し、口を開いた。
「……どこか痛いのか」
「い……いえ、大丈夫です。す、すみません……」
「そうか」
言葉少なく、キラくんはそれだけ言って背を向ける。
けど、「声」は変わらず私の中に聞こえていた。
(……いきなり他人にそんなこと聞かれたって、素直に頼れる訳ないよな。何もないようには見えなかったが……でも、本人がああ言ってる以上、しつこいのも……)
彼が少し離れた本棚の方へ移動してからも、「声」は止まない。一部屋に二人しかいないから他に音を遮るものが何もなくて、はっきりと聞き取れてしまう。
(何回も声かけるのは、それこそ迷惑か。……一人になりたくて来てたのかもしれない。だとしたら悪いことをしたな。視界に入らない方がいいか? 別に大した用も無いし、戻った方が……いや、それもどうなんだ。あからさますぎる。自分がいたせいかって、かえって気を悪くさせるかもしれない。具合悪くないのが嘘だってこともあり得る。それなら離れすぎないで、もし何かあっても気付けるところで――……)
本棚に向かって真っすぐ立つキラくんの姿は、私に関心を持っているようには見えない。むしろ近寄り難そうな雰囲気もある。
しかし彼は本を手に取って探す素振りをしながらも、目の前の本棚にほとんど意識を向けていない。実際には私をずっと気にかけてくれていた。
それが心苦しかった。
私なんかに、そんなに気を遣わせてごめんなさい。
勝手に、一方的に盗み聞きしてしまうのを止めることができなくて、本当にごめんなさい。
私がここにいたから迷惑をかけた。余計な心配をかけさせた。全部私のせいだ。
でも、臆面もなく正直にそう告げられるはずがなくて、彼の方を見ることもできない。
私は教室へ帰ろうとした。抱えたままだった本を戻そうと焦っていきなり立ち上がったせいで、軽い立ち眩みに襲われる。
もしかしたら、よろめいたところを彼には見られていたのかもしれない。
(ソラ兄だったら、こんなとき……)
キラくんが息を飲む気配がした後、硬い声の呟きが聞こえた。
「おい。無理するな」
続けて聞こえてきた声は、明確に私へ向けて発せられた言葉だとわかった。さっきより声量も大きい。
キラくんが眉を寄せて私に近付いてくる。
「授業にはまだ時間あるし、保健室までオレも――」
「いえ、だっ、大丈夫……! ごめ、ごめんなさい……!」
「………」
「……あ、その……」
思わず過剰な拒絶になってしまい、慌てて声をすぼめた。キラくんは驚いた様子で少しの間動きを止めていたが、ふっと顔を背けると息を吐いた。
(……うまくいかないのは……愛想の差か……)
それは傍目には、私のおどおどした態度に呆れた溜息のように見える。でもその「声」が表していたのは、自身へ向けた落胆だった。
「あの……」
「悪かった。……ちょっと手出せ」
「え……?」
(……まだあったよな)
キラくんが、ズボンのポケットからガサガサと何かを取り出す。私の手のひらの上に置かれたのは、透明な包み紙にくるまれた淡い桃色の飴玉だった。
キラくんと可愛らしいお菓子のイメージが私の中で結びつかず、戸惑いを隠せない。目を白黒させて口ごもる私に、キラくんがぽつりと言った。
「……別に、ただの余り物だ。いらなかったら他の奴に譲っていいから」
言い終えるや否や、私の返答を待たずにつかつかと元いた場所へ引き返していく。
(……今のは、変だ。変だった……)
これ以上聞いてしまわないように、私も早々に外へ出た。
階段を下りながら少し思いを巡らせる。思考に伴って、足の動きはだんだんと遅くなっていった。
私が言えたことではないものの、キラくんの言動は決して和やかではなく冷たい印象を与えるものだったと思う。
だけど、その心情はずっと優しくて温かかった。
それに気付くことができた理由は……「声」が聞こえたから。
この力があったから。
改めて考えるまでもない、疑いようのない事実。
階段を下り切って外に出る。中庭の光景に大きな変わりはなく、太陽の光が眩く照り付けていた。
振り返って、石の塔と青空を見上げる。
私の胸の中にはある一つの思いが芽生えていた。
まだ迷う部分も大きい。怖い気持ちと、このままでいたくない気持ちが同じくらいの強さでせめぎ合っている。
でも、キラくんの心に少し触れたことで、前に進むための一握りの勇気を貰えたような気がした。
『夏休みに、他のクラスの友達中心で集まって遊ぶ予定を立ててるのよ。それで、もしよかったらルベリーにも来てほしい、って思ったの。あっ、途中参加でも全然オッケーよ。どう?』
(来てほしい……けど、無理強いは駄目。強制しないように。怯えさせないように……わたしは今ちゃんと笑えてるかしら……)
エレナさんのあの思いを信じられたら、私はその先で何かを得ることができるだろうか。
他人の心の声がとめどなく聞こえてしまう私。そんな私が、人の傍にいていいはずがない。
でも。だけど。
日差しの眩しさに目を細め、手のひらを開き、握ったままだった飴玉の包みを開く。
コロンとした丸い飴玉を口に含んだ。
じんわりと広がるその甘みが、仄かに心を癒していく。
私は口の中でそっと飴玉を転がしながら、校舎に続く中庭へと歩み寄っていった。

