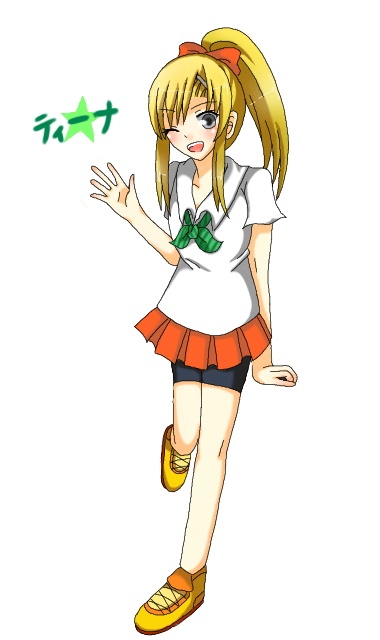番外09.メアリーの手紙
――キラさんへ
――先日は家までお越しいただいて、ありがとうございました。
――この頃は気温が落ち着いて、過ごしやすくなってきましたね。今年の夏も終わりが近いのかもしれません。
――私たちには夏休みというものがありませんが、学校のお休みも、あともう少しなのでしょうか?
――この夏、私とネビュラはいつもと変わらず、家でお勉強やお稽古をしてばかりでした。キラさんは、どんな夏を過ごされたのでしょうか?
――お休みが明けたら、きっとお忙しくなるのですよね。次にお話できるのは、誕生日会の日でしょうか?
――お会いできることを楽しみにしていますね。
――ルミナさんにも、よろしくお伝えください。
――追伸
――この手紙をお出しする少し前に、キラさんからのお手紙が先に届きました。
――直接お越しになられてお話していただいたのに、改めてお返事も書いてくださったのですね。お気遣いいただき、本当にありがとうございます。
――よければまた、キラさんのことをお聞かせいただけると嬉しいです。いつでもお時間のあるときで構いませんので、お返事をお待ちしています。
――メアリーより
* * *
――メアリーへ
――前の手紙、読んでもらえてよかった。
――ちゃんと返事しておきたかったから書いただけだけど。
――別に、夏休みも特には何もしてない。
――もう学校は始まってて、もうすぐ学園祭がある。最近は放課後ずっとその準備をしてる。
――学園祭には来るのか?
――知りたいことがあれば答えるから、聞いてほしい。
――キラ
* * *
彼の手紙はいつも、無地の真っ白な便箋と封筒で送られてきます。
硬く強張った文章は決して長くなく、便箋には多くの空白。強い筆圧で書かれたような、濃くて角ばっている文字。ティーナは「男の子の字って感じ」と称したけれど、私は彼以外の同年代の男性の字を知りませんので、その表現はあまり理解できませんでした。
およそ半年前、初めて彼の書いた手紙を目にしたとき、期待にドキドキと高鳴っていた私の心臓は急速に萎み、代わりに大きな不安に襲われたものでした。
「リアス、ど、どうしよう、キラさんに嫌われてしまったかもしれない……」
「おや、どうされたのですか?」
おろおろとうろたえながらリアスに泣きつくと、長身の彼は膝を折って私の顔の高さに合わせました。
執事長であるリアスは、私と双子の妹のネビュラが生まれたときからずっと傍で世話をしてくれている人です。執事ではあるけれど、家族同然と私たちは思っています。
私は空行ばかりの便箋に目を落とし、涙が滲んでしまいそうなのを堪えながらリアスに訴えました。
「お返事が届いたのでしょう? 先程はあんなに喜んでおられたではありませんか」
「それが、キラさんのお手紙、とても短くて……。私、何か気に障ることを書いてしまったのかな。本当は私のお手紙なんて迷惑だったのかも。嫌々付き合わせてしまっているのだとしたら、私……」
「それは違いますよ、メアリー様」
リアスは、便箋を手にして震える私の両手を優しく包むと、震えが止まるまで握ってくれました。皺の入った顔に穏やかな微笑みを浮かべ、私の瞳を覗き込みます。
「メアリー様は、幼き頃よりティーナさんとお手紙のやり取りをされていましたね」
「うん」
「ですが、恐らくキラさんにはそのような経験がございません。男の子は、友人同士でお手紙を送り合ったりしないものですから」
「そうなの?」
「一概には言い切れないかもしれませんが、少なくとも私の経験上は。ですからキラさんも、お手紙には不慣れなのでしょう。その上お相手が異性ともなると、何と書けばよいのかわからずについ素っ気なくなってしまうのですよ」
「リアスも、旅行先のお友達に初めてお手紙を書いたときは、そういうことがあったの?」
まるでキラさん本人に話を聞いてきたかのように語るリアスが気になり、私は尋ねました。
リアスは、この家の執事になる前は一人で世界一周の旅をしていたそうです。その際に知り合ったご友人と今でも時々手紙のやり取りをしていることを、私は知っていました。
リアスは微笑んだまま、眉を少し下げて頷きます。
「はい、お恥ずかしながら。ですので、わかるのです。照れくさいか、緊張していらっしゃるか、そのどちらかでしょう。ご安心くださいませ。メアリー様がご心配なさっているようなことはありません」
「……教えてくれてありがとう、リアス。それなら、キラさんにお手紙のお礼をしないといけないね」
「ええ、それがよろしいかと」
リアスは私からそっと手を離しました。そのときにはもう、私の中の心細さは消えていました。
自室の机に向かいます。まっさらな便箋を広げて、ペンを取りました。
まずは言葉を紡いでくれたことへの感謝。
返事をいただけたことの喜び。
一通目とは違い、私自身の周りの出来事はほとんど書かずに、彼への気持ちが伝わるように精一杯の表現を尽くします。
そして、数日後、再び返事が届きました。
やはり短く淡白な文章でしたが、その中に記されていた一文が私の胸を打ちました。
――手紙を書くのは初めてだから、書き方が悪かったらごめん。
すっと風が吹き抜けて、心が軽くなったようでした。
キラさんもきっと、私と同じように不安な気持ちだったのでしょう。
このお手紙を読んでからは、どんなに短いメッセージもぶっきらぼうな印象を受ける言葉も気にならなくなりました。
ぎこちない文面は、彼の緊張や恥じらいの表れ。リアスの助言のおかげでそう信じられるようになった私は、手紙を送ることも返事を待つことも怖くなくなっていきました。
この半年、私たちが送り合った手紙の総数は決して多くはありません。ですが、数は少なくとも、一通一通全て大切なものです。
お互いの近況を短く伝え合うだけの、ささやかな文通に過ぎませんが、私にはそれが心の拠り所でした。手紙の中の言葉だけが、私と彼の世界を繋ぐ唯一のものだからです。
もしも、私がスズライト家に生まれることなく、彼と同じ学校に通っていたとしたら……そのように空想したことも、一度や二度ではありません。
彼と同じ学級で同じ授業を学び、同じ本を読み、自由時間には言葉を交わし、下校時には少し寄り道もして共に過ごす日々を夢想し、一人胸を躍らせたことも少なからずあります。
ですが、少し後には冷静になって、そのように都合のいい日々を送ることはきっと不可能だろうとも想像します。仮に私たちが同じ学校の級友同士だったとしても、勇気のない私は彼に挨拶の一つもできずに、三年間の学園生活を終えたことでしょう。
現実の私たちの距離は離れているけれど、だからこそ、私は彼と手紙を送り合うことができました。彼が綴る文字を知ることができました。今以上など、私の身には余ります。
顔も見えない、声も聞こえない、手紙越しのやり取り。
私はいつもその手紙の文字から想像を広げ、数えるほどしかお会いしたことがないキラさんとの記憶を手繰り寄せ、彼の姿を思い浮かべます。
絹糸のような銀髪。長い睫毛と、聡明な光を湛えた深い藍色の瞳。物静かで落ち着いた振る舞い。
目を閉じて、それらの一つ一つを思い出しながら、時間をかけて読みます。そうしていると、それがたとえ十行にも満たない淡泊な文章であっても、温かな思いが広がってくるのです。
私はお気に入りの紅茶を淹れた後、安らいだ気持ちで返事を書き進めました。
書き終えた便箋の端に微量の香水を吹きかけると、ふわりとした香りが広がります。庭に咲いている夏の花たちで作られた、愛着のある品です。この香りがキラさんへ届くときを想像すると、私は期待に胸が膨らむようでした。
宛名を記入するときは、未だにとても緊張します。たった二文字のお名前を書くだけなのに、何故でしょうか。胸の中で彼の名前を唱えると、それだけで私の体は内側からじんわりと火照ってくるのです。一筆一筆に力がこもり、手先が震えて、無意識のうちに息を止めてしまっていました。宛名を書き終えて顔を上げたときには安堵の息が洩れました。
便箋を丁寧に折り畳んで、パウダーブルーの封筒で包みます。それを一度机の上に置き、指先で優しく撫でました。
勇気のない私は、彼の元へ会いに行くことはできません。上手にお話をすることも、自然な笑みを向けることも。
だから、想いは全て手紙に託します。一通一通に心を込め、丹念に、彼の心へ届くことを願って。
レースのカーテン越しに差し込む柔らかい日差しが、辺りを照らしています。皺一つ無い封筒は、滑らかで心地よい手触りをしていました。
* * *
――学園祭、素敵ですね。どんな楽しいことがあったのか、ぜひ教えてもらいたいです。
――残念ですが、私たちは学園祭には行けません。一般のお客様の中に混ざることを、お父様が許してくれなくて……。
――でも、当日のことはティーナが聞かせてくれます。毎年、楽しみにしているんですよ。私たちのために、パンフレットにメモを書き込んでいて、それを見せながら話してくれるんです。――……