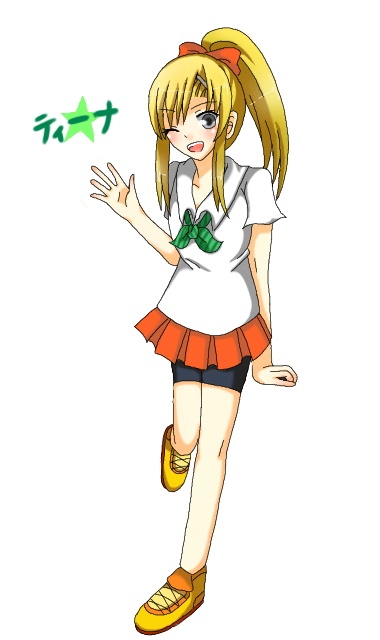番外13.あの日のティーナ ~心に根差すもの/日没の先~
暖かい春の日。
来店の瞬間から、わたしは彼女たちに注目していた。
スズライト魔法学校のセーラー服を着た二人組。わたしと同じくらいの年の女の子たち。二人は窓際のテーブル席に向かい合って座った。
業務の合間に、横のテーブルを片付けるフリをしてそれとなく近くへ行ってみる。立て掛けてあるメニューの角を揃えて綺麗に整頓しながら、顔に出さないようにしつつ耳をそばだてた。
「美味しいっ! 凄く美味しいねこれ!」
先日から新発売したばかりのパフェを嬉々として頬張っていたのは、ちょっと幼げな雰囲気の方の子。小さな体と桃色のツインテールが庇護欲を掻き立てるような容姿で、黒縁の野暮ったい眼鏡に隠し切れていない大きな瞳も愛くるしい。
声を弾ませて、パフェの感想を述べてくれている。
「これはさしずめ甘味の壺といったところね! 生クリームとアイスが上から蓋をしてて、その蓋がちょっとずつ開けてくると中のイチゴソースから香りが漂ってくるの。この刺さってるシュガースティックは、えーっと、そう! 鍵!」
ああっ、やっぱりこの声と喋り方は絶対ミリーちゃんだよーっ! みんな何で気付かないの!? 気付かないフリしてくれてるの!?
「何だかグルメリポートに来たみたいだよ」
一緒にいるのはきっと、ミリーちゃんの友達。穏やかな笑みが、ミリーちゃんと並ぶと少し大人っぽい印象の子だ。頭上で結わえたお団子が、実際より背を高く見せていることも理由の一つかもしれない。
わたしは彼女の言動にも注意を払う。
というか、実のところはミリーちゃんよりも彼女の方に強く気を配っていた。
ミリーちゃんの来店は大事件。でも別に、声をかけたりサインを頼んだりするつもりは全くない。わたしも業務中だし、何より今のミリーちゃんは、アイドル活動を休んで一般の女子学生として青春を謳歌している真っ最中だから。プライベートを邪魔するなんてファン失格でしょ!
だからミリーちゃんのことはいいんだ。楽しそうに笑う彼女のことは、そっと見守っていよう。
それよりも、このエメラルド色の長い髪をした女の子の方だ。
わたしは人捜しの手伝いをしている。その人物の身体的特徴と、彼女はよく合致していた。
名前はティティといって、わたしと直接の面識はない。一度だけ同じ場にいたことがあるらしいのだけど、顔も声もほとんど覚えていない。ただ、わたしの大事な親友たちが彼女の安否を心配しているから、わたしも彼女を捜している。
ある冬の日に突然の失踪をしたティティ。でも、まだこの国のどこかに生きているとあの子たちは信じている。それなら、わたしが手を貸すのは当然だ。
ティティに似ている彼女の顔をどうにかして正面から自然に見れないか、と思いを巡らせていると、後ろから呼びかけられた。
「ティーナ先輩! 注文お願いしまーす!」
「えっ。あ、みんな……!」
飛び級で入学と卒業をしたわたしのことを「先輩」と呼ぶのは、同じチア部の子くらい。振り向くと、サンローズ校指定のブレザーを着ている見知った顔が並んで笑みを向けていた。中には知らない子もちらほらいて、彼女たちはわたしが卒業した後に入ってきた後輩なのだろうということが察せられた。
雑談交じりの軽い感じでオーダーを取りながら、後輩たちと過ごした部活のことを思い返す。
年下の先輩なんて存在は面倒だっただろうな、と自分でも思うけど、みんなは嫌な顔せずにわたしと接してくれていた。今もこうして、一昨年卒業したわたしのことをまだ覚えていて親しげに声をかけてくれる。
それ自体は嬉しいんだけど、今だけはちょっと困るタイミングだったかも。……後輩の優しさをそんな風に思ってしまう自分は、嫌な性格だと思う。
オーダーを通した後にもう一度ミリーちゃんたちのテーブルへ近付こうとしたけど、また後輩たちに捕まってしまった。近いには近い場所だけど、こっちの席に向き合うと二人には完全に背を向けてしまう。
これじゃもう顔を見るどころじゃないや。
それでも、後輩たちの話に付き合うフリをしながら彼女たちの会話には聞き耳を立て続けた。
そして、他人の空似だろうという結論に至った。
この子の名前はネフィリーというみたいだし、親友たちの証言によればティティはだいぶ気が強かったそうだ。ミリーちゃんの話に優しく相槌を打っている大人しい彼女と同一人物だとは思えない。
チア部のみんなは同級生の男子の話に花を咲かせている。その間に、彼女とミリーちゃんは会計を終えて帰っていった。
こちらの会話に上の空だったのを勘付かれてか、軽く突っ込みを受ける。
「先輩聞いてる!? それで、その転校生が超紳士だったんですよ! 眼鏡もかっこよくって~!」
「うちにホウキレース部があれば良かったのに! そしたら部活で応援しに行けたよねー! いっつも一位らしいよ!」
どうやらみんなの間では転校生が話題らしい。知らない男子生徒の話で盛り上がるみんなを愛想笑いで流し、仕事を思い出したフリをして、わたしはそっとその場を離れた。
元々、わたしは昔から恋の話には乗れない性質だ。適当に調子を合わせつつ今まで過ごしてきたけれど、本当はみんなと同じ熱量を抱くことがどうしてもできなかった。
身近にいた男たちが原因じゃないかと自分では思っている。特に幼馴染のシザーは乱暴な悪ガキだし。最近ではキラのはっきりしない態度にもイライラする。
お父さんとお母さんだって、お互い容姿や人柄に惹かれて結婚したのではないだろう。お父さんが求めたのは”丘の上”の立場。お母さんはそんなお父さんの甘言に気を良くしているだけで、一番大事なのは自分自身だ。
現実から目を背け、恋に恋をすると言うように理想を描いて憧れたこともない。わたしにできるのは、せめてみんなの想いに水を差さないようにすることだけだった。
夜、店を閉めていつものように店長と二人で後片付けをしていたら、「後輩に会ったのは久しぶりなのかしら? 楽しそうだったわね」と微笑ましいものを見る目で言われた。
楽しそうに見えていたのなら良かった。
親友たちが捜している人は、もう一人いる。
ティティとほぼ同時期に消息不明となった少年。スズライト魔法学校の校長の孫で、スズライト家長女のメアリーとお見合いをするはずだった相手で、キラの兄。名前はソラ。
メアリーとの縁談の席には、本当なら彼がいるはずだった。
その名前以外、わたしは彼のことを一切知らない。どういった人物なのか何の情報も持っていない。それどころか、当のメアリーでさえソラとは面識がない。ソラが行方をくらませたのは、彼とスズライト家の顔合わせの日の直前だったからだ。
もしもそうならなかったら、今頃はどうなっていたんだろう。メアリーも、キラも、わたしも。
もしもソラが相手だったら、わたしは安心してメアリーを任せることができた?
もしもソラが見つかったら、今からでもメアリーの相手は変わるの?
そうして浮かんでしまう「もしも」を振り払うように、わたしは首を横に振る。
今更、考えたって無駄なことなのだから。
今日は珍しくキラが来店していた。その姿を見たせいで、嫌な感情が膨れ上がっているんだ。
キラは見知らぬ女の子と一緒だった。ただのクラスメイトだと彼は言った。だけど、自分から異性を誘うのに慣れているような人じゃないってことは屋敷での言動を見ていればわかる。メアリーとは一度だって出かけたことがないはずだ。
外向きに跳ねた金髪の女の子が、キラの隣に座って笑いかける。キラは時々彼女の方へ顔を向けて、目が合いそうになるとふっと逸らし、コーヒーカップに口を付ける。そうした一連の様子を、わたしは目にしてしまった。
その席にいるべきなのは、艶やかで美しい黒髪のメアリーだ。なのにどうして、別の女を座らせていられるの。罪悪感も何もないというの?
その程度の安い気持ちで踏み込んできて、メアリーと目を合わせないあの男が、わたしは憎い。メアリーはこの男のどこがいいのか、わたしにはさっぱり理解できない。
心が乱れて、今日の仕事は本調子が出ない。店長はどこまでお見通しなのか、わたしの表情をやんわりと指摘した。キラと彼女が出ていった後だった。
「眉間に皺が寄っていてよ」
「……すみません」
「珍しいわね。何か困ったことでもあるのかしら?」
「姿を消した兄の存在に甘えてメアリーと真面目に向き合おうとしないキラに腹が立っているんです」……などと、正直に話せるわけがない。
ソラの一件によるキラの心労はわたしも理解しているつもりだ。兄のことは諦めろ、と突き付けるのはさすがに酷だろう。
でも、それがわたしの本心。
だってそうでしょ。
ソラもティティも、いなくなった日からもう半年過ぎた。名家スズライト家も彼らの捜索に力を貸しているというのに、何の情報も出てこない。この状況で希望を持ったところで、それは逃避でしかないとわたしは考えてしまう。帰るかどうかもわからないソラより、今ここにいてキラを見つめているメアリーに目を向ける方がずっと建設的だ。
ソラの行方不明事件については、店長にも当然尋ねたことがある。さっきまでカウンター席に来ていたキラが彼の弟だということも、この人なら多分把握しているだろう。商店街をよく利用する近隣の住人や近辺の学生の顔はだいたい全部覚えていると話していたし、日頃の接客を見てもそれは誇張ではなく事実だと思うから。
店長は人が好きだ。一度でも接した相手のことは忘れないと豪語し、実際に顔が広い。そんな店長に向けて、わたしの冷ややかな胸中を打ち明けるのは憚られた。
「大丈夫です。仕事の後の予定が気になっちゃって。集中します」
「そう。ならいいけれど」
店長はわたしから視線を外し、カウンター裏の棚からグラスを取り出して並べ、アイスティーを注いだ。
「……ちなみになんですけど、ソラの件って何か新しい話はありましたか?」
「いいえ、残念ながら。悪いわね」
「そうですか。店長の情報網なら捜せない人はいないと思ったんだけどなぁ」
「一体私を何だと思っていて? 過度な期待はしないでちょうだい、情報網だなんて大それたものではないわ。私が知っているのは、全て単なる噂話よ」
「いやいや、案外そういうのって侮れないものじゃないですか」
店長とラフなやり取りをする内に、少しだけ調子を取り戻した気がする。残りの勤務時間は何事もなく過ぎ去っていった。でも、キラへの苛立ちが消え失せることはなかった。
『……六時、また来て。言い訳はそこで聞いてあげる』
『………』
店の前に立っているキラを見かけて声をかけたとき、先に約束を取り付けておいて正解だったな。あいつは一度問いただしておかないと、わたしの気が済まない。たとえあの子自身が許したとしても、わたしの心が許さない。
メアリーには何も頼まれてない。だから勝手なことだと自覚はしているけど。
でもこれは、メアリーのため。わたしが動かなくちゃ、メアリーは自分の想いを押し殺してしまうに違いない。
あの子の幸せのためならわたしは何だってやるし、何にだってなる。
仕事から上がってスタッフルームへ入ると、向かいの窓から夕陽が差し込んでいた。沈みかけた西日の真っ直ぐな明かりに、今はただ腹立たしさを覚える。カーテンを一気に引いて閉め、黒いリボンタイを乱暴に解いた。
向こうが逃げ出していなければ、外にキラが待っているはずだ。
全部はっきり言ってやる。わたしが言わなきゃ、メアリーは文句の一つも絶対に言わないから。
髪をきつく結い直して支度を整え、従業員用の裏口から店を出ると扉のすぐ横にキラが立っていた。顔を上げた彼と視線がぶつかる。
決まり悪そうな、自分も被害者だと訴えるような、情けない顔。それは日陰の下で鬱屈さが増していて。
ああ、本当に腹が立つ。