109.絡みゆく糸(2)
取り残された私は、しばらくそのまま立ち尽くしていました。
何と言えばよかったのだろうと後悔に苛まれながら、校舎一階へ降りる階段の前をのろのろと通り過ぎます。情けないことに、これだけ話を聞いても、彼の心を苦しめるものが目に見えていても、彼のために私は何をすればいいのか一向にわからないのです。
人気がなく寂しい雰囲気の廊下へ沈み込んでしまいそうになる私の思考を一時中断させたのは、通りすがった教室から一筋流れてきた冷たい風でした。
外に屋台を出していたクラスのため、掃除をしている生徒はいません。暗い教室の中はすっきり整然としています。机の上に椅子をひっくり返して重ねられた状態のものが、前方にずらりと寄せてありました。
誰もいないものと思いましたが、向かいの窓が開いています。覗き込んでみると、廊下側の端の机にシザーが腰かけていました。
シザーは天井を向いた椅子の足に腕を絡め、首を横に回して薄暗い窓の外に視線を向けていました。空になったゼリーの器を机の隅に置いたままです。私の気配を察して、静かな表情で振り返りました。
「ルミナか……」
「どうしたの? こんなところに一人で」
「待て、学校では俺のことは――……や、今日は何かもういいや……」
「……? 何の話?」
「あーっと……何つーか、色々あってな。何でもねーよ」
ガシガシと頭を掻き、少々疲労の滲んだ笑みを浮かべます。
当時の私は、彼が学校生活の中では不良のような言動を意識していることを理解していませんでした。
「後ろ、誰もいねえな?」
「え、うん。さっきまではキラと一緒だったけど。……シザーって、去年キラと同じクラスだったんだよね?」
「ん。それがどうした? キラがどうかしたのか?」
「ええと……」
キラとのやり取りをそのまま伝えることはためらわれ、言葉を濁します。まごついた私を見て、シザーは何かを察したのかもしれません。
「聞き方変えるわ。あいつが何か話したのか?」
「その、キラのお兄さんのことで、ちょっと」
「そうか。……ああ、あんときってまだルミナいねえのか」
「シザーは何か知ってる?」
「まあ座れよ。後夜祭まで少し時間あるだろ? あ、ドア閉めてくれるか」
言いながら、横の机の上をトントンと叩きます。同い年の男の子でありますが、そうした振る舞いには年上と言われても違和感のない風格がありました。
思えば、私がシザーと二人きりで話すのはこのときが初めてでした。出店の喫茶店でスティンヴと一対一になったときと違ってあまり緊張を感じなかったのは、シザーの気さくな言動によるところが大きかったのでしょうか。
私は言われた通り素直に扉を閉めて、シザーの隣の机へ浅く腰を下ろしました。
「キラの兄貴のことだったな? どこまで聞いたんだ?」
「えっと、お兄さんが行方不明だってことと……ホウキレースの大会にいたゼクスさんって人がそっくりなんだって」
「え、ゼクス? ゼクスってあの眼鏡の、スティンヴの宿敵の?」
シザーが意外そうな声を上げてこちらを向きます。
「だったらスティンヴかレルズがとっくに気付いてるはずだぜ、さすがに」
「シザーたちはキラのお兄さんと知り合いなの?」
「いや、別にそういうわけじゃねえが、全校集会で見かけたりしてっから顔はわかるだろ。俺も一応、何となくは覚えてるぜ。言われてみりゃ確かに、髪とか背はゼクスと似てるような気もすっけど……別人じゃねえの? そんな話、誰からも聞いたことねえぞ?」
「うーん……、キラ以外誰もずっと気付かないのはおかしいかも……だけど……」
私には何が正解なのかわからず、他の答えが浮かびませんでした。
引っ越してきたばかりの頃に、私も一度大会を見に行っています。そこでは彼らの他にエレナとネフィリーも一緒でした。エレナもシザーたちと同様に、ゼクスさんについては何も言っていませんでした。
一方のネフィリーは私と同じ編入生で、彼女がやってきたのは昨年の失踪事件よりも後です。そのため、学校でキラのお兄さんを見る機会はないと考えられます。キラに兄弟がいることすら知らない可能性もあり得るでしょう。それに、あの日ネフィリーが彼の顔を見て口にした名前は紛れなく「ゼクス」で、「ソラ」とは呼んでいませんでした。彼にお兄さんの姿を重ねて見ているのはキラ一人のようです。
「けど、実の弟のキラがそう言うんなら確かめる価値はあるかもな」
それらの事実を踏まえても、シザーはすっぱりと言いました。
「わかんないんなら本人に聞けばいいじゃんか。来月のどっかで大会があるはずだが何日だったか覚えてねーから、スティンヴに聞くついでにゼクスが出るか確認取っとく。で、キラに声かけてみるぜ」
「それなら、その日私も一緒に行っていい?」
「おう。じゃ、日程わかったら教えるわ」
シザーはさらさらと提案し、私の申し出も快く承諾しました。自然で頼もしい笑顔に私の心は軽くなります。キラが去り際に見せた暗い顔とはまるで対照的でした。
キラは、何故シザーにも誰にも教えていないのでしょう。あの会場でゼクスさんを初めて見た日から既に何ヶ月も経っており、お兄さんが行方不明になってからは半年以上経過しています。
私では頼りにならないかもしれませんけれど、もし早くからシザーたちにも事情を伝えて協力を仰いでいたならば。そうしていれば違う今日を迎えていた可能性もあったのではないか、と思わずにはいられなかったのです。
「キラはゼクスさんのこと、どうしてすぐに相談しなかったのかな……」
「兄貴のことは、キラは何も言ってこねえよ」
私が零した問いに、シザーは神妙な顔で答えました。片足の靴を脱いで机の上に乗せます。
「去年、あの頃のキラは学校には来てたが、見るからに元気なくて凹んでた。まあ元々騒ぐタイプじゃねえが。けど、レルズたちも声かけづらそうにしてたよ。そんな気遣った空気ってさ、気遣われてる側にはわかっちまうもんだろ? そういうの気にしそうな奴だし、また去年みたいにギクシャクすんのが嫌なんじゃねえかな、あいつは」
「でも、一人で抱えてる方が心配で私は気になるけどなあ」
「そこはアレだ、男のプライドってやつだな」
今度は冗談のような口ぶりで、ニヤリと笑みを浮かべます。そういうものなのだろうかと、私には内心あまりピンときません。
もしスズライト家の屋敷でメアリーに明かされることがなかったなら、キラは私にも何も伝えなかったのかもしれない……そんな想像が、ふと頭をよぎりました。そう思ったとき、私は冷たい木枯らしが胸を吹き抜けていくような寂しい感じがしました。
「よくわかんないけど……それじゃあ私、シザーに色々話しちゃったけど内緒にしてた方がよかったってこと?」
「普通にしてりゃ大丈夫じゃね? でもそうだな、今の話キラにはしばらく黙っとくか」
「……オレが、何だって?」
「わ!」
「お」
唐突にガラリと音を立てて扉が開き、キラが現れて会話に加わりました。出入口の横で足を止めて呆れたような顔をしています。
「いつまでも戻ってこないから捜しに来てみれば……」
「ごめんね、心配かけちゃったみたいで。シザーと話してたんだ」
「別に心配なんかじゃない。それより……珍しい組み合わせだな」
キラの訝しげな視線は私の横のシザーへと移りました。
「どういう心境の変化だ?」
「色々あって疲れちまった。誰もいねーし、今だけな」
「何だそれは……」
苦笑したシザーの答えは、キラの疑問を一層深まらせたようです。
彼らの間で去年どんなことがあったのか、事の経緯は私にはわかりませんが、シザーの裏表をキラは把握していました。学校行事の後で周囲に他の人がいないとはいえ、校舎内で私と普通にお喋りをしていたシザーに違和感を覚えたのでしょう。
「エレナと揉めたのか?」
「いや?」
「違ったか。ならいいんだが」
短い言葉で淡々と交わされる話の中身が見えず、私は二人の顔を交互に見ながらただ聞いていることしかできませんでした。キラが先程のことを気にしていなさそうだったことには安堵していました。
「そういえばシザー、今日の午前中ってどこで何してたの? ティーナには会ったんだよね?」
「何?」
「は?」
聞いた途端、二人は同時に振り返って声を重ねました。キラもシザーも目を丸くし、続けて互いの顔を見合わせます。
「シザーがティーナと……?」
「あいつのこと知ってんのかよ。しかも、キラもか」
世間狭いな、とシザーは苦笑いでぼやきました。
私が当番中にティーナと会っていたことを簡単に説明すると、納得した様子で頷きます。
「ティーナはシザーと家が近くて、幼馴染なんだって。そうだよね。私はティーナのバイトしてるカフェで仲良くなったんだよ」
「ああ、そういうことか。俺らは生まれる前から親同士が知り合いでさ。親に付き合わされた挙句、大人の話の間は外で遊んで待ってろってよく一緒に放り出されてた。その程度の仲だ」
「……前にオレの部屋で、あの封筒がスズライト家のものだってわかった理由は、ティーナか」
「ん? あー、夏休み前か。んなこともあったな」
キラは閉口し、何かを考えているようです。シザーも一度口をつぐみ、机に両手をついて背を反らし天井を見上げました。
「聞いてて気分いい話じゃねーけどな。スズライト家に、俺らと同い年の双子いるだろ? 名前は……メアリーとネビュラだっけ? 昔、ティーナの親父がそこに目を付けて、まだガキのあいつを――」
話の途中、シザーの声を遮るように、ワッと窓の下から歓声が聞こえてきました。
その理由に思い当たる節があり、私は机から飛び降りて窓辺に駆け寄ります。見下ろした先の校庭には人が集まっていて、キャンプファイアの炎が轟々と燃え盛っていました。
「ああっ、燃えてる!? 火付けるところ見たかったのにー!」
「……悪い。時間過ぎてたな。気付かなかった」
背後から聞こえるキラの声色は本当に申し訳なさそうです。大声を発してしまって悪かったと思いながら、気を取り直してキラに向き直ります。
「う、ううん、キラは悪くないよ! 気にしないで! 時計見てなかった私のせいだし、また来年もあるもんね! 後夜祭始まっちゃうから、早く行こう! シザーも!」
「や、俺はいい」
「えっ、あれ? 待ってたんじゃないの? キラは行くよね?」
「オレも別に行くつもりは……」
「ええっ!? 他に何も用事ないなら行こうよ!」
二人の反応は芳しくなく、特にシザーは困った顔をしていました。私ともキラとも目を合わせず、眉間に皺を寄せます。理由も言わずに口を閉ざしていました。
キラはそんなシザーの様子を一瞥し、改めて私に視線を戻して小さな溜息を一つつきます。
「……わかった、そこまで言うんなら行ってやる。少しだけだからな」
廊下へ出る直前で、キラは教室内を振り返りました。机に座ったままのシザーに呼びかけ、シザーは目だけを向けます。
「……なあ、シザー」
「………」
「オレはシザーの好きにすればいいと思ってるが、今日、レルズはお前のこと気にしてた。本当はお前と行きたかったんだと思う。多分、去年も。それだけ伝えとく」
「……そか」
シザーは一言だけ言葉を返し、キラもこの他には何も語りませんでした。
「言わなくても、お前もわかってるとは思うが。……エレナのお節介が移ったな」
そう言い残して、キラは静かに扉を閉めました。
不意に、悪寒に似た寒気を感じて肌がピリッと震えます。
私はシザーが一人残った壁の向こうのことが気にかかり、一度だけ振り返りました。視線の先は、何もない薄暗い闇が続くばかりでした。



108.絡みゆく糸(1)
この後に後夜祭が控えていたためか、校内の片付けはサクサクと滞りなく進んでいきます。
学園祭の形跡がなくなっていく校舎を見ていくうちに、私は少々感傷的な気分になりました。段ボールの看板を片付けに運んでいる間も、どことなく切ない気持ちでした。
廊下にはほとんど人通りがありません。壁のチラシやポスターは剥がされ、カラフルな画用紙や風船などの装飾も既にあらかた撤去されています。普段であれば下校時間間際の時刻で、窓の向こうの空は薄暗くなりつつありました。誰の姿もない、照明の消えた教室が何ヵ所か見られます。
「何か寂しいね」
「元に戻っただけだろ」
「そ、そうなんだけど」
「……まあ、わからなくもないが」
静けさに耐えかねて、運ぶのを手伝ってくれていたキラに話しかけましたが、素っ気ない返事ですぐに会話が途切れました。いつも通りのキラではあるのですが、無言の時間の空気が少し重く感じられました。
この段ボールを置き終われば、私たちのクラスの掃除もほとんど終わりです。私はこの後そのまま後夜祭へ向かうつもりでしたが、キラがどうするのかは聞いていませんでした。
一緒に片付けをしながらも、彼とはあまり話をできていません。その原因は、昼に一瞬だけ見えた黒い霧のことに他なりませんでした。
今日一日、あの瞬間以外にキラから異変は感じなかったけれど、だからこそその理由が私はずっと不可解でした。しかしその一方で、気になるのなら後で説明すると彼自身は言っていたけれど、話を切り出すことにも躊躇していました。
そうして私の口数が少なくなっているのは、キラから見れば「気になっている」と口にしているも同然のことだったのでしょう。キラは私の心の内を容易く見抜いて指摘し、店番を代わる直前に起きていた出来事について説明を始めました。
「お前は本当にわかりやすいな」
「ご、ごめん……」
「別に怒ってない。……今日、昼前に三年の教室の前通ったとき、顔見知りの先輩に声かけられてな。去年兄貴と同じクラスだった人なんだ。進級してからは会ってなかったんだが、向こうもオレを覚えてたらしい」
「お兄さんの……。えと、そ、それで……?」
「それで、終わり」
「えっ」
身構えていた私は話の短さに拍子抜けし、思わず声を洩らして振り向きました。キラが溜息を吐きます。
「言っただろ、大したことじゃないって」
「でも、なら何でそれだけで……?」
「……兄貴のことを考えると、訳がわからないんだ。それでモヤモヤしてるのがルミナの目に見えたんだろうな」
何を考えていたのか、キラは具体的には言いませんでした。しかし、心配をかけまいと感情を抑えているような彼の表情を見るとそれ以上詳しく尋ねることはできませんでした。
代わりにキラが語ったのは、私がまだスズライトにいなかった一年前の思い出です。
「あの先輩と初めて話したのは、ちょうど去年の学園祭だった。兄貴がオレたちの教室まで連れて来たんだ。前の日にわざわざオレが店番してる時間帯を確認してきたから来るのはわかってたが、他にも何人か友達連れて、誰も頼んでないのにオレのことを紹介しまくって……」
「お兄さんと仲良しなんだね」
「……向こうが弟離れしてないだけ。こっちはいい迷惑だ」
キラの話を聞いて、私は昨年の皆のクラスの様子を思い浮かべます。ぼんやりとした想像の中で、キラのお兄さんの姿は優しげな笑顔のゼクスさんになりました。
窓の前を通り過ぎて廊下の角を曲がり、周囲の暗さが少し深まります。
「それに、今はどうだか……」
「え?」
「……兄貴は不慮の事故や事件に巻き込まれて行方不明になったんじゃない。多分計画的に、初めから自分の意志で出ていった。オレに何も言わないで、黙っていなくなったんだ」
「えっ、そ、そうなの!? でも前はそんなこと一言も……」
昼のキラに感じた黒い霧の原因よりも、この話の方が私には強い衝撃でした。
キラのお兄さんは、昨年の冬から行方がわからなくなっています。私がそれを知ったのはほんのひと月ほど前の夏休みでのことです。
一つ年上の、ソラ先輩。箒による飛行技術と速さを競うホウキレースに出場していたゼクスさんが、キラのお兄さんの彼によく似ているということ。それについて確かめたいことがある、とキラが話していたのを私は聞いていました。
「はっきり証拠があるわけじゃない。ただ、行方不明になった直後、兄貴の部屋にはあるはずの物が全然無かったんだ。箒も、鞄も、教科書もノートも、服も、食べ物も……何も」
キラは段ボールを握る手に力を込めて目を伏せます。
事件当時、一週間もの間お兄さんが学生寮の自室へ戻っていなかったとキラが知ったのは、その週明けを過ぎてからのことだったそうです。
お兄さんの部屋は捜査のため立ち入り禁止にされていました。しかしキラは、兄弟の自分には関係があるからと潜入しました。そこで目にしたのが、もぬけの殻となった室内だったのです。
各部屋に備え付けの家具や閉め切られたブラインドカーテン、机とベッドの下に敷かれた絨毯などはそのままです。しかし、それ以外のものが何もありませんでした。クローゼット、机の上、引き出しや棚の中、全てが空っぽでした。
「今でも覚えてる。あれは、兄貴が自分で片付けたとしか思えない状態だった。……爺さんには取り合ってもらえなかったけどな」
キラのお爺さんは、私たちの学校の校長先生です。捜査の状況や結果などに関してはキラよりも詳しく聞いているのでしょう。
「爺さんの言ってることもわかるんだ。今日、先輩と話してますますそう思った。兄貴が出ていく理由がわからない……もしあいつが兄貴本人なんだとしたら、戻ってこないのも……」
話しながらキラの声はすぼみ、その体の周囲にじわりと黒霧が滲みました。勢いは弱く、大きく広がることもなく、すぐに宙へ溶けて消えていきます。しかし、私はそれをどうすることもできませんでした。
廊下の突き当たりに到着し、私たちは足を止めました。様々な出し物で使われた看板や張りぼての背景などが既に乱雑に立て掛けられています。キラは運んできた段ボールを私の分も引き取って置きました。俯きがちで、上に添えていた手をぐっと握り締めます。
「……今年は、ソラ兄にとって最後の学園祭だったのに」
「キラ……」
「勘違いするなよ。オレは別にあいつのことなんてどうでもいい。ただ、腹立ってるだけ。お喋りのくせに大事なことは何も教えないで、自分勝手でイラつくんだ」
そう話すキラの目の奥に見えたのは確かに、以前スズライト家の屋敷で見せたものと同じ怒りの感情でした。けれど怒りの一言で済ませるには痛ましく、苦しげであるように私は感じました。それもあの日と同じでした。
私たちの他に生徒の姿はなく、段ボールの擦れる音が消えると辺りはシンとしました。険しい顔のままキラが口を開きます。
「あの馬鹿兄貴のことはルミナが気にすることじゃない。オレらの問題だから、ほっといていい」
「でも」
「気遣われたくないんだ」
私を遮り、少し強い言い方で制しました。彼自身もそれほどきつく言うつもりではなかったのかもしれません。目を大きく開き、自分に驚いた様子でした。
サッと眉を寄せ伏し目になると、顔を背けます。
「……悪い。先に戻る」
私の返事を待たずに、キラは一人で廊下の暗がりに消えていってしまいました。


107.夢のあとに
閉会式が終わり、生徒たちが各自の教室へ向かいます。この間、花束を抱えたミリーは列近くのクラスメイトたちにずっと囲まれていました。
教室へ入ってすぐ、受付の机の裏にある沢山のプレゼントを見下ろし、笑顔で話しながら戻ってきたミリーは足を止めます。
「こういうのって、一旦事務所通して中身チェックしたりするの?」
「いっぱい増えたね! さっき一個くらいもらっちゃってもバレなかったかも」
「コラ」
「あはは」
ミリーは笑う皆に合わせて苦笑しながら、身を屈めます。
「でも、本当にいっぱい……大丈夫かなぁ……」
足元には空色のサテンリボンが結ばれた紙袋があり、二つ折りのメッセージカードが差し込んでありました。眩しいイエローが目に留まります。
抜き取って広げると、ラメが入ってキラキラとしたライムグリーン色のインクでこのように綴られていました。
――おつかれさま! がんばったね!
――これからもずっと、応援してるよ!
サラッとした筆跡の細い文字、その周囲を彩るように、鮮やかな青色の小さな星が散りばめられています。
ミリーは意表を突かれたように目を大きく開け、その後ゆっくりと、表情を和らげました。
皆は教室の片付けを始めました。ミリーのもらった花束は彼女の希望で教室内に飾ることになり、一時的にロッカーの上に置かれています。
クラスメイトが動き回っている中、シザーはキッチン側の裏手に置いてあった自分の荷物を回収してさっさと廊下に出ようとしていました。それにエレナが目ざとく気が付いて、遠くから手を伸ばします。
しかしエレナが呼び止めるよりも前に、シザーは扉の前でぴたりと足を止めました。
シザーが向かおうとしていた方向からギアー先生が顔を出します。
「おっと。楽しかったかい?」
「………」
掃除の手伝いをせずに帰ろうとしているのが明らかなシザーを見ても、先生は何も咎めません。一言だけ問いを投げかけて、返事を待たずにシザーの横をするりと抜けて教室の中へ入ってきます。睨まれていることも一切気に留めていませんでした。
シザーはその場に立ち止まり、先生の動きを注視しています。
「全員いるね。掃除の前に少しいい?」
先生はホームルームを始めるように教卓の前で立ち止まり、皆が注目したのを確認すると、指示棒のような杖を持った右手を教卓の上で一振りしました。
転移の煙に包まれ、ずっしりと重そうな音を立てて段ボール箱が現れます。
「さあ、どうぞ。先生のおごりで差し入れだ」
中に詰まっていたのは、人数分のオレンジゼリーでした。片手の手のひらに収まるくらいの大きさで、よく冷えています。
「さすが先生! 太っ腹ー!」
「神!」
生徒たちが、作業を中断してワッと群がりました。ギアー先生はニコニコと笑顔で箱からゼリーとスプーンを取り出し、一人一人に配っていきます。
シザーが立ち止まったまま先生の動きを観察しているのを確認し、エレナも教卓に向かいました。
自然な動作で先生側に立とうとしましたが、サクランボ柄のシュシュを巻いた腕が伸びてきてそれを制止しました。
「はい、エレナの分」
「あ、ありがと。リーン」
「こんなときくらい働くのやめなさいよ、実行委員さん」
「そうだね。エレナさんにはクラスのことをほとんど任せきりにしてしまってすまなかった。よく頑張りました、お疲れ様」
何も言わずとも、配布の手伝いをしようとしたのは見抜かれていた模様です。二人の言葉に、エレナは少し照れくさそうな笑みを零します。それを少し離れた後方で見守っていたルベリーの表情もまた、穏やかでした。
ルベリーは皆に行き渡って周辺が空くのを待っているようです。先生と手分けしてゼリーを配っていたリーンが途中でその姿を見つけ、一度はためらいを見せつつも傍まで持ってきてくれました。
快く受け取ったルベリーでしたが、言いにくそうにおずおずと口を開きます。
「ええと……ありがとう。でも、あの……これ、人に渡してきてもいいですか……?」
「えっ、ごめん、苦手だった?」
「い、いえ、その、違うんです、すみません。ゼリーは好きです……そ、そうじゃなくて……」
口ごもりながら、ルベリーの視線はリーンの横を抜けて扉の方へ向いていました。追いかけて振り返り、その先に立っている人物に気付きます。確かめるように向き直ったリーンの顔にははっきりと、戸惑いが広がっていました。
ですがルベリーはこくりと頷き、顔を真っ直ぐに上げて彼の元に一人で近付いていきます。近くにいた他の生徒も、何人かはその意図を察して動向を見守っていました。
先生へ向けたままの視界に横から入り込む形で、シザーの前に立ちます。
「……シザーくん」
彼は一瞬目を見開いて動揺を露わにしましたが、すぐに顔つきを引き締めて鞄を持つ手を握り締めました。
ルベリーがシザーへ声をかけたのを、クラス中の皆が心配や緊張の滲む面持ちで見ています。エレナとミリーも同様に手を止めて、シザーの顔色を窺っていました。
二人を気にする素振りを見せていないのはギアー先生ただ一人です。先生だけはそちらへ目もくれずに薄い微笑みを浮かべ、残り少なくなったゼリーを外に出して空にした段ボールを畳み始めています。その行動はまるで、あえて二人を見ないようにしているかのようにも映りました。
シザーもルベリーも互いに無言のまま、数秒ほど見つめ合います。皆も口を挟みません。
クラスメイトの胸の内にはどんな思いが渦巻き、それをルベリーはどんな思いで受け止めていたのでしょう。
シザーは心の中でルベリーに何を訴えかけていたのでしょう。
午後の出来事によって、同じ時間帯に当番をしていた生徒たちは少なくとも、シザーへの印象が少し変化していました。シザーはすぐに今まで通りの態度へ戻ってしまったけれど、借り物のエプロンと三角巾を身に付けてせっせとたこ焼きを焼き上げる姿には普段のような近寄り難さが見られなかったのでした。
その現場にルベリーは居合わせていませんが、シザー自身も含めた皆の心から流れ込んでくる思いの数々が、彼女にこの行動をさせるに至ったのです。
「……シザーくんも、一緒に食べよう」
両手を添えて、ゼリーをそっと差し出します。
堂々と目を見て、背筋を伸ばして。少しばかり強張ってはいるけれど、微笑みを向け続けて。
シザーは目を落としたまま黙りこくって、なかなかもらおうとしませんでした。床を睨みつけるようにしながら、その目線は左右に揺れていました。
「そんなんじゃ駄目だよー、ルベリーさん」
「えっ……」
二人の間の沈黙を破ったのは、ルベリーの斜め後ろからずっと様子を見ていた一人の男子生徒でした。
「ほら、大人しくもらっとけって」
「!」
彼はルベリーの手からひょいっとゼリーを取ると、流れるような動きでシザーの空いている手に強引に持たせます。
それを皮切りに、周りの生徒たちも男女共にわいわいと集まってきました。
「シザーのたこ焼き捌きは凄かったな! マジ助かった!」
「何の話?」
「え、手伝い来たの? いつ?」
「……! ほっとけ!」
「あ! 逃げた!」
無理矢理ゼリーを手渡された状態で固まっていたシザーは、バッと声を上げると皆に背を向けて廊下へ飛び出していきました。
変わらず先生だけは扉側を見ようとしないけれど、その賑わいが耳に入っていないはずはありません。眼鏡の奥の目を細め、口元を綻ばせていました。
シザーを囃し立てて賑やかになる扉付近の光景が、エレナの瞳に映ります。振り向くと、先程まで室内に漂っていた緊張感はすっかり鳴りを潜めていました。
このとき教室には、確かにクラス全員が揃っていました。皆が同じ思いを胸に抱いていました。
以前シザーに「クラス全員が揃ってほしい」と自身の願いを伝えていたエレナ。それはルベリーのためを思っての願望です。しかし実際にシザーを引き止めてこの教室を一つにしたのは、ルベリーでした。
振り向いた先でエレナとミリーの目が合います。
どちらともなく、二人はクスクスと笑みを零しました。
開放された窓から、爽やかで柔らかな秋風が吹き込んできます。ロッカーの上の花束が、丸く優しい橙色の明かりをゆらゆらと揺らしました。





106.gift&blessing(8)
ステージの中央で足を止める。
歌い終えてからずっと体中が熱くて汗も流れたままだけど、晴れやかな気分だ。
両手で胸を押さえて息を整え、ワタシの言葉を待っているみんなをぐるりと見渡す。
ワタシは、胸の中の想いを打ち明けた。
まず、ワタシのために時間を作ってくれた実行委員のみんなや先生たちに改めてお礼を。
そして、本来はもっと早くこうして伝えるべきだったことも含めて、急な活動休止を謝った。それでも変わらずに応援し続けてくれた人たちに、精一杯の感謝を込めて言葉を紡いだ。
もし、この瞬間から活動再開なんだと期待をさせてしまっていたらごめんなさい。それはもう少し待っていてほしい。
わがままを言ってるって自覚はある。だけど、ワタシはこの半年で学校のことが好きになった。
ここにはかけがえのない友達や大事な人たちがいる。その人たちと一緒に過ごす時間は、今しかないかもしれない貴重なもの。歌いたいとは心から思うけど、今このときだけの体験を大切にしたいというのもれっきとしたワタシの本音なんだ。
きっと、その経験はワタシの歌をもっともっと良くしてくれる。学校のみんなとのこれからの日々が、ワタシの歌の世界を彩ってくれる。
そうしたら今よりもずっと立派なワタシになって、みんなを驚かせちゃうから!
「――ワタシは必ず、卒業した後には絶対にステージへ戻ってくるって、ここに宣言します! ……だからそれまで、見守っていてくれますか?」
話している間は静かだった会場が、また賑やかになった。パチパチと拍手が広がって、その温かさにホッと安堵の息が零れる。
この光景、この気持ち、忘れないよ。
「ありがとう! ワタシも、みんなが大好き!」
胸に思い浮かぶ言葉を心のまま伝えて、優しい光の中、深くお辞儀をした。閉じた瞼の中に、無数の光がまたたいていた。
司会のエレナが動いたのは、各クラスとステージの出し物それぞれの最優秀賞が発表された直後だった。
「これより表彰に移りますが、その前に一つ、追加発表です」
台本には無いはずの台詞に、何だろ? と振り返る。
「急なオファーに応えて舞台に立ってくれたミリーにも、実行委員会特別賞として花束を贈呈したいと思います! 各団体の代表者一名とミリーは、登壇してください!」
ワッとみんなが沸き立ち、拍手のレールが引かれた。
でも、ワタシはその場で立ちすくんだ。
「な、何言ってるの、エレナ? 歌わせてって無理なお願いしたのはワタシで……」
エレナは拡声器として使う杖を口元から下ろし、戸惑うワタシにしたり顔を向ける。
「これはわたし一人じゃなくて委員会みんなで決めたことよ。先生からもちゃんと許可はもらってるわ」
「そ、そういうことじゃなくって」
「うふふ、もう言っちゃったもの。今更取り下げられないわよ?」
エレナの向こう側に整列している、実行委員の他の子たちも同じような顔をしていた。
まさかワタシもサプライズを仕掛けられる側になっていたなんて。今日の一大イベントをすっかりやり遂げたつもりで完全に油断していたし、気付かなかった。
「どうしてミリーが急に歌おうとしてくれたのか、わたしたちにはわからないわ。去年何があったのかってことも。でもいいのよ。関係ないわ。わたしたちの気持ちよ、もらってちょうだい?」
ワタシをからかうために計画したんじゃないってことは、その目の光を見ればわかる。委員会のみんなもワタシを見ている。あまりに純粋な目が、かえってワタシの足をすくませた。
拍手は続いている。
「ほら! もう二人は来てるわよ!」
エレナに背中をトンと押された。
流されるまま前に出ると、壇へ上がる階段の手前で、表彰を受ける代表者として前に出てきていたスティンヴがこっちに振り返り口を開いた。
「嬉しくないのか? 今日一番だったのは誰が見たってあんただ。素直に受け取ればいいじゃないか」
「えっ」
「何?」
「う、ううん……」
スティンヴは何ということもなく普通に言ってたんだけど、そんな風に思われていたのはすごく意外だった。興味ないって前は話していたのに。
もう一度ステージに上がった。今度は、みんなに呼ばれて。
登壇して横に整列したワタシたちの目の前に、長テーブルと橙色の花束三つが現れる。花束の中心に据えられた釣り鐘型の花、コミナライトが丸くて淡い光を湛えていた。
続けて壇上に上がってきたのは、ネフィリーだった。ワタシの番は最後に回ってきた。
ネフィリーが正面に立ち止まり、両手で大事そうに抱いた花束を差し出す。
「はい、ミリー」
それでもワタシは迷っていた。
本当にいいのかな。偽りばかりの、「本物」じゃないワタシなのに……。
困惑を隠せずにその顔と花束を交互に見ているワタシに、ネフィリーが不思議そうな目を向ける。
すると、ネフィリーは腕を伸ばしてワタシの手を取り、ギュッと向こうから花束を握らせた。
「どうしたの? この花はミリーのものだよ」
花々の香りが漂う。複数の香りが混ざり合っているけど穏やかに調和して、柔らかな落ち着く香りを作り出していた。
まるでみんなの笑顔みたいな花のブーケ。
さっきまでとはまた少し異なる雰囲気の、優しくて温かな拍手がワタシたちを包み込む。
急に気が緩んで、涙が零れた。
自然にポロッと零れ落ちた。
慌てるネフィリーに、ワタシは腕で目元を拭いながらかぶりを振って笑みを浮かべる。
「違うの、大丈夫……ありがとう」
「……おめでとう、ミリー」
ほっと息をついて微笑み返すネフィリーの瞳の中には、花束を抱きかかえたワタシの姿。橙色の照り返しが映り込み、コミナライトの丸い灯りと閃光のようなライトが溶け合って七色に見える。
そんな風に、みんなの目に映るワタシの姿には沢山のフィルターがかかっていて、本当のワタシじゃない。
本当のワタシは、みんなが思うような人じゃない。
だから花束を差し出されても、自分には相応しくないように思えて身を引いてしまう。みんなを騙して、良くないことをしているように思ってしまう。
でも、それはきっと間違い。良くないことのはずがない。
だって、みんながワタシに向けてくれる笑顔は偽りじゃないでしょ?
みんなを騙したいわけじゃない。みんなの心からの笑顔が見たいから、みんなが望む通りのワタシを演じている。それを悪だとは思わなくてもいいんじゃないか。
ワタシがみんなを騙しているのは事実。本当のワタシをみんなは知らない。
だけど、それでいい。
それでもいいんだ。
そう思えた。自分を受け入れることができた。
もしかしたらこの感情は開き直りとか自己弁護とか、そういうものなのかもしれないけど、だとしても構わない。
嘘か本当か、偽物か本物か、なんて、気にしてるのはきっとワタシ自身だけ。ワタシを責めているのはこれまでだってワタシ一人だった。だったら、自分に都合よく考えちゃおう。
もしもこの先、誰かがワタシを嘘吐きだと糾弾したってやめない。
そのときは堂々と認めよう。それがワタシだって。ワタシがワタシを演じ続けるのは、大好きなみんながいるからですって。
最後まで「本物」になることはできなくてもいい。降り注ぐスポットライトの光、大勢の歓声、みんなの笑顔、祝福の花束……そんな沢山の「本物」のものを、もうもらっているから。
ワタシの姿が本当じゃなくっても、みんなの気持ちは絶対に本物。
それなら充分、満足だよ。
ワタシはそうやって生きていこう。
そしていつかその日が来たときは、語り尽くせないくらいいっぱいの思い出話をクレアへのお土産にして。こんなに幸せな一生だったよって、笑って言うんだ。
ステージはいつも誰かの明かりに照らされて輝いている。
ワタシを照らす光はこんなにも眩しくて、温かくて、夢幻のように綺麗。
それはこの舞台が終わった後もずっと、心に残り続けていた。
* * *




105.gift&blessing(7)
確認を取りつつ、リハーサル通りの開始位置に立つ。エレナはステージ袖へ去っていった。
照明の落ちた広いステージの中央に一人。
騒めいていた講堂の中が、徐々に静まっていくのがわかる。
閉じている垂れ幕の向こうのみんなは、ここにワタシが立っているとは気付いていない。考えてもいないはず。
向こう側の景色を想像すると、緊張に足がすくんで震えそう。
だけど、バレッドさんが見せてくれたみんなの顔を思い描けば、そんな気持ちは消し飛んでいく。
何度も何度も挫けそうになってしまったワタシだけど、あれだけの想いをもらった後だもん。
不安に負けてなんかいられないよ。
ワタシには、何の力もない。
バレッドさんみたいな魔法の力も持ってないし、エレナみたいな頭の良さや自信もない。自分のことばかり考えて、無力で、弱い。
でも、そんなワタシにも、ワタシだけにできることがあるってパリアンさんは言ってくれた。ワタシの歌は力を持ってるんだ、って背中を押してくれた。
そして、それを伝えてくれたのはパリアンさん一人だけじゃなかった。
クレアと、レルズ君。
二人の言葉を思い出し、目を閉じる。
――あなたは、わたしの太陽でした。
――わたしは、ミリーの歌にいっぱい元気をもらいました。これからもずっと、ずっと、応援しています。
クレアが最期に遺してくれた言葉。
レルズ君がワタシにくれたのも同じ言葉だった。
――いつだって何回だって、俺は答えるっす!
――ミリーちゃんは、俺の太陽だって!
太陽。
二人はワタシを太陽だと言う。
でも、ワタシは今でも自分をそんな風には思えない。
太陽みたいにいつでも、一人でも明るく強くあり続けることなんて、ワタシにはできないもん。
ワタシがそんな風な人に見えるのだとしたら、それは他でもないみんなの前だから。
ワタシがいるのは晴れやかな青空の下じゃない。いつだって、この暗く閉じたステージみたいに先の見えない夜道の中。
太陽に照らされているのはワタシの方で、みんながワタシの進む道を示してくれているんだ。
ワタシがしているのは「本物」の真似事に過ぎない。
ピアノを奏でるクレアの光り輝く瞳に憧れた。
あんな風になりたいと願った。
ワタシが目指しているのは、今もクレアなんだよ。
レルズ君もワタシに光をくれた。
君はワタシのことを太陽だって言ってくれたけど、ワタシは逆だと思う。
弱気に負けそうになるワタシのことを信じ続けてくれた。ワタシよりもワタシのことを信じてくれていた。
あの放課後、丸い頬を夕陽で真っ赤に染めながらひたむきに、熱い想いを瞳に宿して伝えてくれた。
どれほど嬉しかったか。支えになったか。
君こそ、ワタシの太陽だよ。
なんて言ったら、君はどう思う?
俺はそんなんじゃないです、って慌てるのかな?
ワタシが自分のことをそう思えないのと同じように。
自分自身が何と思っているとしても、誰だって、誰かにとっての「太陽」になれるのかもって思う。
案外、人から見た自分のことってわからない。だから、自分に自信がないのなら、自分を信じてくれる相手のことを信じてみよう。
ワタシはそうやってここに立っている。
そんな風に信じてくれる人がいるだけでも、幸せなこと。
みんなにとってもワタシがそういう存在であればいい。みんなには人を照らす力があるんだよって、伝えたい。
どうか、この想いがみんなへ届きますように。
ワタシの歌がみんなの光でありますように。
深呼吸を一つ。
魔法で指先に光を纏わせて、最後の準備が整う。
端で控えているエレナにちらりと視線を向け、光の軌跡を描く指でハンドサインを送った。その合図は、エレナからステージの演出係と司会進行役へと伝わっていく。
始まりを告げる鐘が鳴った。
カラカラと音を立てながら、幕がゆっくり上がっていく。
シンとしていた講堂の空気がザワッと揺れ、幕が上がり切ったときには大きなうねりとなっていた。全身に感じた振動は、ワタシの決意を固めさせるには充分すぎるくらいだった。
頭上のスポットライトが点灯し、歓声とも悲鳴ともつかない声の波の上へ被せるようにレコードが再生される。
そのポップなメロディが弾けるのに合わせてパッと目を開け、自然と零れてきた渾身の笑顔を向けてみせた。
客席の方は明かりが点いていないけど、みんなの姿はちゃんと見える。それぞれのクラスTシャツや発表の衣装を身に付けていて色とりどりで、一様に、何が起きているのかと驚き顔。どよめきも止まない。
ワタシはリズムに乗ってステップを踏みながら、両腕を大きく広げて手招きした。
みんな、もっとこっちに来て!
その表情をもっとよく見せて!
みんなの喜ぶ顔が、ワタシの力の源なんだ!
全校生徒のカラフルな列は途端に崩れて混ざり合い、波のように一斉に集まってきた。奥半分に用意された一般来場者向けの座席からも多くの人が立ち上がって、前方へ駆けてくる。
あの冬以来のライブ。
――大丈夫。
大丈夫!
ステージライトと指先の光が、視線の先を照らし出していく。
座席に残った人たちの中にシズクちゃんの姿を見つけた。最前列の椅子の前で、興奮を抑え切れずにピョンピョンとジャンプしている。歌が始まると飛び跳ねるのをやめ、代わりに左右に体を揺らしてリズムに乗った。
その近くにはティーナちゃん。椅子の前に立ち尽くし、斜め掛けしたショルダーバッグの紐をギュッと握りながら、煌めいた目でこちらを見つめている。
シザーはいるかな、と目を凝らすと、ステージ前に集まった生徒たちよりも数歩後ろのところに一人立っているのを見つけることができた。他に誰の視線も無いからか気が抜けていて、口を丸く開けてぼうっとしたような顔をしている。
ワタシと目を合わせた瞬間が確かにあったし、シザーもそれに気付いていたのは明らかだった。ハッとした表情を見せた彼に、パチリとウインクを向けてみせた。
シザーのいる辺りが元々の整列場所なんだろう。人の山から離れたその付近には、ルベリーも立っていた。彼女は常に人の心の声が聞こえているというから、これだけの人数がいる場で気分を悪くしていないかと一瞬不安がよぎる。だけど思いのほか顔色は良さそうに見えた。ライブ中の皆の心の中って、どんな風に聞こえているのかな。
ルミナのことも見つけた。その場に立ち止まっている二人とは違って、みんなの後ろで左右にひょこひょこと揺れて顔を出そうとしている。本当は前に来たかったのかもしれないけど、最初の流れに乗り遅れちゃったような様子だ。
ステージのほぼ真下、最前列に駆けつけてくれた人たちは息ピッタリだった。曲とワタシの呼びかけに合わせて、腕を高く突き上げて応えてくれる。何人かの友達と一緒に並んだレルズ君が気恥ずかしそうに、けどしっかりと、ちゃっかりと抜け目なく参加していて、その一生懸命な表情が面白くてこっちも笑みが零れた。
予想していなかったのは、ネフィリーも前列に加わっていたこと。いつも大人しくって、こういうので前に出るタイプじゃなさそうなのに。今朝、大勢の人に囲まれたワタシを助けてくれたときも印象違ったし、まだワタシの知らないネフィリーがいるのかも。
ネフィリーは活動休止前のワタシを知らないと言っていたから、ライブも初めてのはず。きっとコールのことも知らない。でも、周りのみんなを真似て一生懸命合わせようとしているのが見て取れる。その気持ちが嬉しいし、ネフィリーも楽しんでくれてたらいいなって思う。
ワタシのライブを知らないのは、隣国から今年引っ越してきたルミナも同じだろう。もう一度見ると、ルミナは舞台から視線を外して横の観客たちを見ていた。やっぱり、返し方をわかっていなくて戸惑っていたみたい。
この後も何回かあるけど、付いてきてくれるかな。ごめんね、あらかじめ教えておけたら良かったんだけど、ライブの計画は秘密だったからできなかったんだ。なんて、ここから伝わるはずもないけど、心の中で謝りつつ言い訳した。
今はまだ、スズライトの街の中でしか歌ったことがない。だけどいつかは国を超えて、海を渡って、もっと沢山の人にもワタシの歌を聞いてほしい。
そんな感情がすっと自然に胸に浮かんだことは、自分でも意外だった。
元々はワタシとクレアのものでさえあればよかった、ワタシの音楽だけど。
クレアは今のワタシの気持ちを聞いたら、喜んでくれるかな。笑って応援してくれるかな。
もう、想像することしかできない。
だけど、そうだったらいいな……。
デビュー曲の「twinkle eyes」を選んだのは、シズクちゃんが一番好きな歌はこれだと話していたから。
でも、ちょうどよかった。この日が本当の意味でワタシのスタート地点だと思って挑んでいるから、デビュー曲はおあつらえ向きだ。
それにこの歌は、今のワタシ自身の気持ちにもよく合致していた。
きっといいことがある、だから一緒に頑張ろうってみんなにエールを送る歌。その歌詞に込める真っ直ぐな思いに変わりはない。
だけど実のところ、今はちょっと違う。思い描いている感情はそれだけじゃない。
歌いながら、自分の歌に勇気をもらう。ワタシ自身のことを奮い立たせている。
一時期は、その明かりが眩しすぎて遠ざけていたこともあった。自分で詩を書いた「ピアニスト」がワタシそのものなら、「twinkle eyes」もまたワタシ自身を象徴するような歌だ。無邪気で幼く、それ故に間違いを犯して、責め続ける一方で突き放すこともできず共に生きてきた、過去のワタシだった。
「twinkle eyes」を素直な気持ちのままでまた歌えるようになったことって、ワタシの中では大きな一歩なんだ。
みんなには内緒。
ワタシだけの秘密。
ワタシもみんなと同じ人間だから、みんなと同じように悩んだり、苦しんだり、立ち止まったりするよ。
そんなときは一緒に思い出そう。大好きな人たちのことを、おいしいご飯のことを、温かくて綺麗な陽の光のことを。
そうしたら、もう大丈夫。
先の見えない夜道の中でだって、きっと歩いていける。
今日この場限り、たった一曲だけのライブは、あっという間にクライマックスへ迫る。
コール&レスポンスに不慣れそうだったネフィリーやルミナも、何度か繰り返すうちにタイミングが掴めたみたいだ。
スティンヴやキラみたいに、あんまりライブに興味なさそうだったり騒いだりしなさそうな人も中には当然いるけど、みんなに合わせて控えめながら腕を上げたり手拍子を入れたりしてくれている。
シザーは身動きしていない。でも、片時も目を離さずにじっとステージを見つめていた。
ドキドキと高揚感に満ちていく身体は、最高のコンディションだ。喉はしっかり開けていて、足取りも軽い。音楽に乗って身体は自然に動く。
全身が火照り、胸がいっぱいになる。
最後の一音を、ありったけの全力で出し切った。
手拍子と、歓声と、どこまでも続きそうなアウトロに包まれる。
スポットライトの光と流星のような煌めきが幾重に重なって、辺り一帯を照らす。みんなの姿まで輝かせている。
大喝采を浴びて、ワタシは観客席の隅から隅まで全員にしっかりと届くように、腕を高く上げて手のひらを広げた。
「ただいま!」




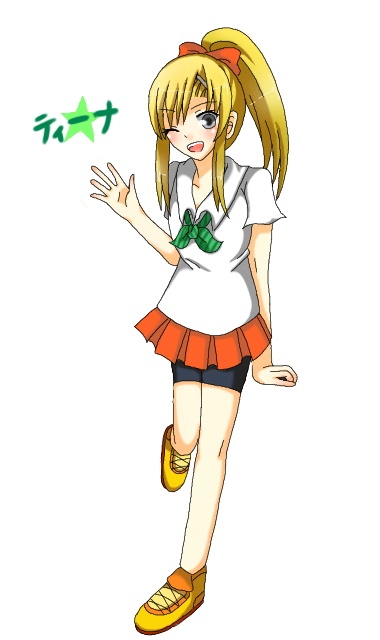






104.gift&blessing(6)
レルズ君が去った後も、しばらく教室の光景を見ることができた。
会いに来てくれたみんなの笑顔と応援の言葉、そうしたものから溢れ出すエネルギーが、パリアンさんの眼を通してワタシに伝わってくる。
時々、差し入れも手渡されていた。何のためらいもなく全て受け取ってしまうパリアンさんにワタシは焦り、もらう前に中身ちゃんと確認しなきゃダメだよって言いたくなったけど、それすらも緊張した心をほぐすエッセンスだ。仕方ないなぁ、って、笑みが零れた。
ワタシを飲み込もうとしていた暗い夜のような闇は、もうすっかり晴れていたみたいだった。
ラストオーダーを聞いてキッチンへ伝えに行くところで、ぶつっと映像が切れた。いつの間にか相当見入っていたらしく、一気に現実へと意識を引き戻される。
白い光が消えて淀みの塊に戻った球体は、バレッドさんの手のひらの上で萎んでフッと空気に溶けるように消えた。
バレッドさんがじっとこっちを見ていた。ワタシが気付いてなかっただけで、本当はずっと前から見られ続けていたのかも。無防備な顔を間近に見られていて、ちょっと恥ずかしい。
真正面からワタシを見据えたまま、僅かに首を横に傾ける。その動きに合わせてバレッドさんの長い前髪がサラッと流れて、切れ長の目が覗いた。
その目元は、心なしかほんのちょっと優しげな感じがする。
前に睨まれたときはもっと眉間に皺が寄っていて、眼光も鋭くって、怖かった。でも今は、ワタシの勘違いじゃなければあのときよりも少し、本当に少しだけだけど、柔らかい印象を受けた。
今の魔法は何だったのか、どうやったのか、わからないことしかないけど……ひょっとして、ワタシを元気づけようとして見せてくれたんだろうか。パリアンさんが一緒だったら、答え合わせができたかなぁ。
バレッドさんは唇を固く結んだままワタシを凝視し続けている。こっちが何か喋るか動くかリアクションを取るまで、ずっとそうしていそうな気配さえ感じた。
と、思いきや、突然バチバチッと瞬きをして視線を落とし、空っぽの左手を見下ろしてピクリとも動かなくなった。
「………」
それでワタシもはたと気付く。
杖、持ってない。
それに、呪文を唱えたりもしてなかった。
さっきしていたことといえば、顔の前に右手を広げただけ。
たったそれだけで魔法が使えるなんて、授業でも聞いたことがない。
バレッドさんは何をしたの? あれは一体何だったの? やっぱり、この人ってルベリーと同じ半霊族……?
固まってしまったその顔色を窺おうとしたのと、バレッドさんが深く溜息を吐いたタイミングが重なった。
ガシガシと不機嫌に頭を掻きながら立ち上がる。ポケットに突っ込んだ手から、小さく縮んだいつもの杖が出てきた。
「……マジだりぃ」
一言、それだけ言い放つ。
言い訳も何もしないのは、多分、面倒だから……かな。
「時間だ」
今日一番のドスの効いた声でそう告げて、元の大きさに戻した長杖をガンッと床に力強く叩きつける。ワタシが身をすくませるのも、支度がまだなのも全く構わずに口の中でもごもご呪文を言い始めたから、「待ってください!」と慌てて遮った。
立ち上がり、パリアンさんが持ってきてくれたタオルや置きっぱなしのドリンクを取りに行く。その背後から素っ気ない声が飛んできた。
「ここからは一人で行け」
「え? ワ、ワタシ一人ってこと? バレッドさんは来ないんですか……?」
「行かねえ」
返ってくるのも、最低限の短い言葉だけ。
ワタシはてっきり、パリアンさんと合流するために学校まで一緒に来るのだと思っていた。でも、どうやらそれは違ったらしい。
振り向くと、バレッドさんの杖は既に十分な光を湛えていた。ワタシを置いて彼だけが先にいなくなってもおかしくない。面倒くさくて早く帰りたがっているのは、きっと本心だ。
本当にここでお別れなら、その前に短い時間だけでも話がしたいと思った。
ワタシは荷物を取り、彼の目の前に立って見上げる。
今日起こった様々な出来事への疑問を投げかけても、バレッドさんはいつものように何も話さないだろう。それに、もし答えてくれたとしても、それはワタシが知る必要のある話じゃないと思う。
だからこれから言うのは彼に聞きたいことじゃなくて、彼へ伝えたいこと。
口にすれば、とってもシンプルな思いだけど。それでも、伝えることは大事だから。伝えればよかった、って後悔することになるのはもう嫌だから。ワタシがそうしたいと思うから。
「ありがとうございました、バレッドさん」
目いっぱいの笑顔を向けて、深々とお辞儀をする。
今日だけの話じゃない。パリアンさんに連れられて相談をしに行ったあの日からずっと、バレッドさんはワタシの力になり続けてくれていたんだ。
だけど、ワタシはバレッドさんへ何も返せていない。本当はライブまで見届けていってもらって、その歌がお礼になればいいんだけど、バレッドさんはそれで喜ぶ人じゃなさそう。
この感謝は、ただ純粋に言葉にして伝えるしかない。他の方法はもうわからない。
顔を上げると、バレッドさんは横向きに顔を背けて静かにぽつりと呟いた。
「……礼はアイツに言え」
「アイツ?」
「………」
それきり、また口を閉ざしてしまう。
けど、パリアンさんのことかな、って直感した。
ほぼ半日バレッドさんと一緒に行動してきて、そんなにいっぱい話ができたわけじゃないし、ますます謎が深まったことの方が多かったかもだけど、どんな人なのかちょっとだけ掴めた気がする。
全然喋らないし、表情は変わらないし、何を考えているのかわからなくて、不思議で謎めいていて、不気味に感じることも時々あるけど。
本当は、優しい人かもしれない。
パリアンさんがずっと言っているように。
でもそれはパリアンさんがそう信じて、頼って、慕っているからじゃないのかな。
ワタシの見立てだと……もしかしたらこの人って、パリアンさんのことが大好きなんじゃない?
いつもパリアンさんばかり一方的に猛アタックしているみたいだけど、実はバレッドさんの方もまんざらでもないんじゃないかな?
ずっと不思議だった。面倒がりな性格でワタシの友達でもないバレッドさんが、どうしてここまで付き合ってくれたのか。
その答えは、パリアンさんの頼みだから?
そう考えるのがワタシの中では一番納得のいく理由だった。
「………」
何か言おうとしているのか、バレッドさんは閉じた唇の端をちょっぴりピクピクさせていた。だけど結局、何も言わなかった。
「それでも、ワタシはバレッドさんにもお礼を言いたいです。いっぱい協力してくれて、ありがとうございました! また今度、お店に遊びに行ってもいいですか? ちゃんとお礼したいので!」
「………」
呆れたみたいに、バレッドさんは無言で腰に手を当てて息を吐く。
本当に嫌なときや駄目なときは、バレッドさんははっきり言うはず。だからこの沈黙は拒絶じゃないって、わかるようになっていた。
杖の光が広がって視界を包み込む。
その温かさを感じながら微笑みを浮かべて、目を閉じた。
物置のような、暗くて狭い部屋に着く。
今度はちゃんと見覚えのある場所で、講堂の舞台袖だった。ステージカーテンの影の中だ。日中の発表で使った物と思われる模造紙や段ボールの小道具が隅に固めて置いてある。大勢の人がザワザワしているのが漏れ聞こえてきていた。
「ただ今をもちまして、スズライト魔法学校の学園祭は終了です。この後は講堂でエンディングセレモニーが行われます。全校生徒、及びお時間のある方は、講堂へお集まりください。本日はご来場ありがとうございました」
ワタシの頭上で、模擬店の営業時間が全て終了したことを知らせるアナウンスが大音量で鳴る。階段を二段だけ登ってステージを覗くと、幕は一番下まで下ろされていて備品の類も綺麗さっぱり片付いていた。
反対側の舞台袖近くに、台本を手にして立つエレナの横姿がある。ワタシが移動してきたところは見ていなさそうだ。元々の計画だと、最後の発表者が舞台を降りて委員会の人たちだけになった後にここへ来て用意する段取りになっていた。
エレナがワタシに気付いて、小走りで駆け寄ってくる。カーテンの向こうに聞こえないように、お互い控えめに声を掛け合った。
「ミリー! 見つからないで来れた?」
「う、うん。今どんな感じ?」
「こっちは準備オッケーよ。あとはミリーの準備ね。順調だわ!」
エレナの安心した様子が、他に何の問題も起きていないことを物語っている。
ワタシのフリをしたパリアンさんが今どこで何をしているのかはわからないけど、あっちもうまくやってくれたはずだろう。二人を信じ、ワタシはすぐに支度を始めた。
姿を変える魔法の応用で、服だけを変化させて着替える。応用なんて言うと難しそうに聞こえるけど、やることはほとんどいつも通り。その服を着ている自分自身の姿をイメージして、描く。全身を変えるよりも簡単なくらい。
この衣装は、今から歌うデビュー曲のときのもの。可愛いデザインでワタシ自身も気に入っているけど、現物はもうサイズが合わなくて着れなくなってしまった。
実際に着替えてみて、初めて気付く。
そっか、こうすると思い出の服をいつでも再現して着ることができるんだね。
ワタシはこの魔法のことが好きじゃないけど、人を騙したりするんじゃなくってそういう使い方をするんだったら素敵な魔法だって思える。誰もがこんな風に使っていたのなら、実は禁術扱いして嫌う必要なんてなかったものなのかもしれない。
「まあ、便利ね。わたしもやってみたいわ。パルティナ先生に聞いたら詳しく教えてもらえるかしら?」
ワタシが衣装を変えるのを興味深そうに見て、エレナは弾んだ口調で言っていた。



103.gift&blessing(5)
職員室の前まで戻ってきた。手前で立ち止まる。
ギアー先生、いるかな。また見つかってしまったら、次は声をかけてくるかも。もしそうなったら何て答えよう……。
ドキドキと緊張しながら、開けっぱなしになっている扉の向こうを覗き見る。
先生たちもお昼休みで出かけているらしく、さっきよりも人数が減っていた。自席でお弁当を食べている先生はいるけど、ポツポツとまばらだ。ギアー先生はいなさそう。隣のデスクのパルティナ先生も席を外している。
様子を伺っていると、小部屋に繋がる扉は閉まっていたのに内側から風に吹かれたように隙間が開いた。
小部屋の中に窓は無かった。この動き方は不自然だ。
それに気付き、身を屈めて職員室に潜り込む。お行儀良くないけど、両手を二つの紙パックで塞がれていたワタシはその隙間に腕を突っ込んで体を入れた。小部屋に入ると、扉は音もなく勝手に動いて閉まった。
「………」
中ではバレッドさんが、来たときと同じ壁際に寄り掛かって待っていた。長い杖を脇に抱えて腕を組み、ぼんやりしている。
確証はないけど、多分さっきの扉はバレッドさんが動かしていたんじゃないかな。
本当にそうだったら禁術スレスレの行為。だけど、「もしどこかで見ていたとしてもこれくらい見逃してください、妖精様」って、ワタシは思っちゃった。
バレッドさんが無言のまま顔だけ振り向いて、クッとかすかにだけ顎を上下させる。
今の動きは、こっちに来い……って、こと?
悪い人じゃないんだろうけど、バレッドさんと二人きりになるのはまだ慣れないなぁ……。壁の蝋燭にまた灯っている青紫色の炎の照り返しが、この古ぼけた部屋と彼の顔色を一層不気味に演出しているのも悪いと思う。
意図を汲み取れた自信はないけど、正面まで歩いていってみる。
バレッドさんは何も言わない。数秒ほど、一切何もせずにぼうっと突っ立っていた。
……ま、間違えたかな?
不安になっていると、バレッドさんが溜息を吐きながら腕組みを解いた。
「めんどくせー……」
ぼそっと気だるげに呪文を唱え出して、徐々にワタシの視界は白で包まれていく。
あれ? でもこれは、さっき転移したときとは違う呪文だ。
だけど、知ってる。
魔法で変えた姿を元に戻すときの呪文?
白い光に包まれたのはワタシ一人だけだった。
パッと一瞬で、光が消える。
目線は低くなり、長かった金髪は縮んで桃色になり、握っていた紙コップは少し大きくなった。正しい表現をすれば、ワタシの手の方が小さくなったんだ。
何故かバレッドさんは、ワタシをこの場で元の姿に戻した。バレッドさんもこの魔法が使えることを初めて知ったけど、もうこれくらいじゃ驚かなくなっちゃったよ。
でも、行動の意図が読めない。どうして?
体格も声も全てが変わるから、練習の続きをするなら元の姿に戻る必要があるのは確かだ。でもそれは練習スタジオに着いてからでいいし、ワタシが自分でもできる。
何においても「面倒くさい」と口癖のように言うバレッドさんだから、わざわざ無意味なことはしないはず。けど、今ここでこうしなきゃいけない理由なんてあったかな?
バレッドさんを見上げて長い前髪の下の顔を覗き込んでみても、表情はぴくりとも動いていない。何を考えてるんだろう。
何も説明せずおもむろに、もう一度呪文を紡ぎ始めた。今度は正真正銘、転移の魔法だ。
視界が再び白く染められていく。
そのとき。
ふと、すぐ隣から名前を呼ばれたような気がした。
バレッドさんの低い声とは違う、もっと穏やかで、優しくて、懐かしい感じ。
人に見つかったら困るのに、恐れも戸惑いも不思議と感じない。
振り返る途中で目の前は完全に真っ白になった。
人影らしきものは何も見えなかった。
ワタシの変装を解いたのはなぜなのか、他に誰かいなかったか、後からバレッドさんに尋ねてみたけど、何も答えはなかった。
空耳かもしれない。気のせいかもしれない。
でも、ワタシを呼ぶ声が聞こえたんだ。
あの声は何だったんだろう。
誰だったんだろう?
スタジオに戻ってきて、背もたれのない長椅子が並ぶ休憩スペースでお昼ご飯にした。
ワタシたちの他には誰もいない。照明は点いていなくて、窓から光が入らない角の辺りはちょっと薄暗かった。
「あ、あの、これ、バレッドさんの分です。食べてください」
「……いらんつったろうが。めんどくせえな」
「あぅ……」
唐揚げを差し出すと、そんな風に文句を言われてしまった。ワタシの質問に面倒と答えたのは、食べるのが面倒っていう意味だったのかもしれない……。
でも、バレッドさんはひったくるように乱暴に紙コップを受け取った。立ったまま顔を上向きにし、大きく口を開け、その上から紙コップを斜めに傾ける。転がってくる唐揚げを丸ごと口に放り込んでガツガツ咀嚼する姿にワタシは呆気に取られて、思わずまじまじと見上げた。
何かを食べているところは初めて見るし、いつもちょっとしか唇を動かさないでぼそぼそ喋るから、こんな風に大口を開けているのを見るのも初めて。まるで人じゃないみたいに鋭く尖った牙が先端を覗かせていて、少しドキリとする。
バレッドさんはあっという間に紙コップを空にすると、グシャッと片手で握り潰した。適当な場所に腰を下ろし、足を組む。その隣に肩を並べる度胸はなくて、ワタシは一列後ろに座った。
ワタシが全て食べ終えて声をかけるまでバレッドさんは黙って待ち続けていて、会話は一言もなかった。気まずさを感じていたのはワタシの方だけだろう。
長い沈黙を何とか乗り切り、練習を再開した。
午前に気になっていた箇所は改善できたはず。パリアンさんとバレッドさん、二人が時間を作ってくれたおかげだ。感謝しなくちゃ。
ワタシが練習している間バレッドさんはスタジオの隅っこに胡坐をかいて座り、いつの間にか手にしていた芸能誌に視線を落としていた。感想もアドバイスも言うわけがなく、関心もなさそう。ワタシはそんなバレッドさんを気にしないようにして、最後に一曲初めから通してリハーサルとした。
……これでおしまい。まだ時間はあるけど、余裕を持って切り上げる。練習で頑張りすぎて本番まで体力が持たなかったら、台無しだもん。休むことも大切だって、ワタシは身に沁みて知っている。
「これくらいにして、後は時間まで休んでます。えっと、また学校に戻るときは、送ってもらえるんですよね?」
「………」
「お、お願いしますね」
一応伝えておくものの、やっぱり返事も反応もない。だけどこれまでのことを考えると、心配はいらない……はず。
ワタシは彼からちょっと離れた窓辺に腰を下ろし、ネフィリーとルミナのクラスの模擬店でもらったお菓子を食べながら休憩にした。
バレッドさんをちらりと見る。
何も用が無いとき、よく雑誌を読んでる気がする。趣味なのかな。他人や世の中のことに興味なさそうな人に見えるけど、興味がないなら雑誌を読むことはないよね?
バレッドさんとももっとお話しできたらいいのに。案外シザーみたいに、話すようになったら全然怖くなくなるかもしれないから。
立ち上がって、一度だけバレッドさんにもお菓子を分けに行った。だけどやっぱり、無視されてしまった。顔を上げることすらもない。
仕方ないから、隣にちょんと置くだけ置いて戻った。
一定のペースで繰り返される、ひそやかに雑誌のページを捲る音。
窓の向こうはよく晴れて、陽光が差している。
斜めに傾き始めた日差しは、室内に影を伸ばしていった。
袋の中のお菓子へ伸ばす手が次第にゆっくりになり、止まる。
今日までにやれることは頑張ってきたし、二人の思わぬ協力のおかげで準備は整っている。なのに、心配が募って止まらない。静けさが胸のざわつきを加速させる。
一度意識してしまうと、収まってと思うほどにぐるぐると頭の中を巡る。
ぎゅっと両膝を抱えて、うつむいた。
時間は刻一刻と迫ってくる。
本番を前にして焦りを感じるのは初めてじゃない。むしろ何度も通ってきている。だけど活動休止前までのそれよりも、今は怯えや恐怖の感情に重くのしかかられていた。
心の中にいくつもの声が浮かんで、ワタシ自身へ語りかけてくる。
――できることはもう充分やったよ。無理しちゃいけない。
だけど、まだ他にも、もっとやるべきことがあるんじゃない?
今の状態で本当にベストを尽くせる?
ワタシはみんなに迎え入れてもらえる?
次々と自分を内側から責め立ててくる声に押し潰されてしまいそう。
怖い。
そんな折、おもむろにバレッドさんが立ち上がって、こちらへのろのろと歩いてきた。
ワタシの真正面まで来ると膝をついてしゃがみ、感情の読めない目で、じっとワタシを見つめる。
だけどそれから、一向に口を開かない。表情も変わらないから、考えが全くわからなくて戸惑う。
窓ガラスの向こうから室内を照らし出す陽の光を反射して、彼の真っ黒な瞳が一瞬だけ淡く煌めいたように見えた。
バレッドさんがワタシの顔の前に、右手の手のひらを上向きにして広げる。
その上に、ゆらゆら波打っている不可思議な球体がぼんやりと出現した。ドロッと淀んでいるようにも見えて、綺麗とは言い難い。
浮かび上がった球体は揺らめきながら徐々に膨れ上がり、バレッドさんの筋張った大きな手の上をはみ出ていく。顔を隠すくらいの大きさになったところで、膨張は止まった。
球体の外周上を黒い電流のようなものが走り、内側からは対照的な白の光を放ち始める。
眩しい光が少しずつ弱まって、その中に何か映し出されているのが見えてきた。
ぼやけていた映像が徐々にくっきりしていき、合わせて聞こえる物音も鮮明になっていく。
『――――ございました!』
ガヤガヤとした人の喧騒をバックにして、馴染みある声が飛び出してきた。
『お待たせしました、次の方ー! こちらの席にどうぞ!』
『ミリーちゃん! 次あっち、三番テーブル!』
『はいはーいっ』
球体に映った光景は、前後にも左右にも目まぐるしく動く。
満員のテーブル席。大勢の人たち、それからクラスのみんな。三日月型の器に入って湯気が出ているたこ焼き。それを受け取る、手前から伸びてくる両手。手渡された人たちはパッと笑顔になった。
球体の中で忙しなく、くるくると、見えるものが変化する。見続けていたらちょっと酔いそう。
この映像ってもしかして――ワタシに変装したパリアンさんの視界と同じ?
そんな魔法、今まで見たことも聞いたこともないから突飛な考えだけど。
でも、今日はこれ以外にもおかしなことが起こってばかりだから、どんなに不可思議な現象も受け入れられてしまう。
この球体の中には間違いなく学園祭真っただ中の校舎が誰かの一人称視点で映し出されていて、中に現れる人々はみんなこちら側を覗いて「ミリーちゃん」と呼びかけた。それは紛れもない事実だった。
また視界が横に揺れて、一瞬シザーの姿が映った。三角巾で髪を押さえつけ、キッチン側の湯気にくるまれている。
ちょっとだけ心が跳ねて、けれど同時に疑問も生じた。
シザーとワタシのシフトは一緒じゃなかったはずだよね? っていうか、これっていつの出来事? 今って何時? もうワタシの当番の時間も終わってる頃じゃ……?
思いを巡らせているうちに、目線はフロア側へ移動してシザーは見えなくなっていた。
『いらっしゃいませ、いかがですかっ? もうそろそろラストオーダーだけど、今ならまだ間に合うよ!』
『だ、わあっ!?』
今度は、騒めきの中に一際元気のある少年の叫び声が響く。
びっくり顔のレルズ君が映っていた。
こっちもハッとして、ワタシの中にあったあらゆる疑問が一旦全て吹き飛んでいく。
レルズ君は教室には寄らず、短く挨拶だけ交わして去った。だけどすぐに戻ってきて、また球体の中に現れた。
『あ、あーっと、その! こんなに沢山の人が集まってんのって、やっぱすげーことだと思うっす! 誰にでもできることじゃねーっす! だ、だから……さすがみんなのアイドルっすね! いや、違うな、そうじゃなくて……俺何言ってんすかね!?』
何か言い忘れてたみたいに色々と口にするものの、どの台詞にも自分で納得していないよう。もどかしそうに、もぞもぞと落ち着きなく体を揺らしている。
だけど、ワタシにはレルズ君の言いたいことが感じ取れた。
学園祭の前に二人で話す機会があり、そのときにワタシは思いがけず彼に弱音を漏らしてしまっている。今見ている光景は、その放課後に重なっていた。
何度も言葉を詰まらせながら一生懸命話そうとしてくれた、あのときと同じ。レルズ君はまたワタシを応援しようと、励まそうとしてくれている。その気持ちが伝わってきて、温かい思いが胸に広がっていく。
上手に言葉にならなくっても、大丈夫だよ。
ちゃんと届いているから。
不意に、レルズ君がこちらを見た状態でピタッと動きを止めた。
一呼吸を置き、晴れやかな表情になっていく。
ワタシの方からは特に何もわからなかったけど、ここに映っていないところで何かを見たのかな。
『……やっぱ、何でもねっす。じゃ、じゃあ、今度こそ俺はこれで。邪魔してすんませんっした』
姿勢を正して真っ直ぐ正面に向き直る。
澄んだ瞳にはワタシの姿が映っていた。
『ううん。そんなことないよ。ありがとう!』
そう返事をしたのは、本当はワタシじゃない。
けど、その場にいたらきっとワタシも同じ風に言っていた。
君は意外と慎重で、ちょっと心配性だね。
でも、ありがとう。
ワタシをいつも想ってくれていて、ありがとう。



