番外11.とある日のリゼ
裏口の扉から外に出ると、夕方なのに建物の隙間からカッと日差しが照り付けてきた。思わずキャップ帽の上から手をかざす。
「リゼちゃん、お疲れ様」
後ろから出てきた同僚の子が、明るく話しかけてきた。
夏季連休の間だけ、アタシと同じように短期バイトでこの喫茶「マジカル」へ勤めることになっているスタッフ。笑うと小さく覗く八重歯が特徴的な、素直な子だ。仕事以外の話はまだ殆どしていないけど、見たところ同い年くらいだろう。
アタシが勤務態度を改めて接するようにして以降、彼女の方からも話しかけてくるようになった。そのおかげでアタシを疎ましそうに扱っていた先輩スタッフたちの態度も少し軟化されたようだった。この子がいてくれて良かったと思う。
初日だからということで、アタシたちは早上がりだ。商店街を出るまで少しの間一緒に帰った。
「リゼちゃんの家ってどの辺?」
「あーっと、そうね、あっちの方よ」
適当に妖精の森が見える西側を指差す。嘘じゃないわ。
「反対側かあ、私は寮だから向こうなんだ。じゃあ、またね。明日も頑張ろ」
どうやらスズライト魔法学校の生徒らしい。ルミナとキラも、あの学校の生徒なのよね。二人のこと聞いてみればよかったわ。明日話そうかしら。
東南の空の下の、遠目にもよく見える大樹のシルエットが学生寮だ。彼女は箒に跨って飛び去っていった。
箒には白い綿のように魔力がまとわりついていて、遠ざかる様はまるで発光する雲のよう。
そんな風に見えているのは、少なくともこの辺りだと双子の姉メアリーとアタシの二人しかいないみたい。箒の後ろからボロボロと零れ落ちている魔力の塵だけは他の人の目にもかすかに見えるそうだけど。
それは太陽光にチカチカと反射して、塵のようだ。
アタシたちが半霊族として生まれたこと、そして一般には目に映らないはずの魔力が見えていることが判明したのは早かった。真っ先に違和感に気付いたのはアタシだったか、メアリーだったか、それともお父様か家庭教師かメイドか庭師か……。ともかく、アタシたち双子と他の人との間では世界の見え方が違うと踏まえた上で、屋敷の中だけで専用の教育が始められた。
先生が唱えた術とアタシたちに見えた光景を一つずつ擦り合わせ、どの現象が何の魔法を表しているのか学んでいくのは地道な作業だった。だけどそのおかげで、今となっては蠢く魔力を見ればその内容や力の強さまで見極められるようになっていた。
人が魔法を唱えると、込められた術式に従って放出された魔力の塊が術を具現化させる。
しかしその魔力の構造は大抵の場合あまり美しくない、というのがアタシの感想だ。だから正確にはアタシたちに見えているのは魔力じゃなくて、構築された術式の形とそのクオリティなんじゃない? と考えているのだけど確かめる術はない。何しろ答えを教えられる人間がいないんだから。多分、家庭教師の先生だってアタシたちのことを半分も理解していないわ。
例えば、箒を飛ばすときの雲のような魔力は常に崩れ続けているほどに結束が脆く不安定で、比率も均一じゃない。術式の構造自体には問題ないが、術者の力が伴っていないせいだ。皆は箒が漏らす魔力の光を綺麗だと言うけど、アタシには穴の開いたクッションから綿が飛び出しているようなものとしか感じられなかった。
他の魔法も同様に、いびつに歪んでいたり、灰色に濁った不純物が混じっていたり、不器用なパッチワークみたいに格好悪い継ぎ接ぎがあったり。どんなに高名な王宮魔導士が唱える術だろうが全部そう。絶対どこかに綻びがあり、魔力が零れて無駄になっている。それを知りもせず鼻高々になっているあいつらは滑稽で、面白くない。
人間の書いた術式は所詮その程度。それが人間の限界。
そう悟ってから、アタシは本気で勉強するのが馬鹿らしくなってしまった。魔法以外も、全てが。
魔力が見えるということ。それはつまり、魔法にかけられて魔力をまとっている物の見分けがつくということでもある。箒も、身体強化を施した人間も、遥か遠い空の彼方に薄く張られた結界さえも。
それを羨む人はいた。確かに、便利だろう。アタシたち姉妹の目に映るスズライトの空や森は世間に伝わる姿より美しいのだろう。
けど、魔法と呼ばれる現象は綺麗なだけじゃない。この「能力」を羨ましがる奴らには、都合のいい表面的な部分しか見えていない。他人を貶める呪いもれっきとした魔法の一種なのよ。
アタシとメアリーは魔力が見えて得をしたこともあれば、嫌なものを目にする機会だって何度もあった。魔力の光と共に重ねられた、陰険な策謀や醜い感情がアタシたちには全て見えてしまうから。
魔法使いが――いや、人間がどれほど汚いものか、アタシたちは今よりずっと幼い頃に嫌というほど突き付けられている。十数年も続けばもう慣れたものだけどさ。
半霊族の力はどうあっても捨てられない、一生の付き合いになるもの。だからうまく利用して生きるのが賢い選択。昔そう教えてくれたのはお父様と、執事長のリアスだ。
アタシは二人の言葉通りに強かに生きると決めている。魔力が見える「体質」に開き直って、アタシを窮屈に縛る家柄もその権力も全て使い倒して、好きに生きてやるのよ。
家や城の中だけの狭い世界になんて囚われない。魔力にも他人の心にも縛られない。アタシが生きるのは、この広い空の下の世界なんだから。
妖精の森を経由して屋敷と行き来ができる、先日発見したばかりのあの抜け道はなかなか優秀みたいだ。二日目のバイト日も同じ時間に同じ道で外へ出られた。塞がれてないってことは、このルートはまだバレていない訳だもの。
昨日は小細工無しでシンプルにお稽古をサボったが、今日は身代わりとして認識阻害の魔法人形を置いてみた。ただの人形を「ネビュラ」だと錯覚させる魔術だ。いつまで効くのかしらね? メアリーには言葉通り一目で見抜かれてるだろうし、あの子の態度で先生にもバレそうだからあまり信用はしてないけど、まあ別にアタシの居場所さえ見つからなければ何だっていいわ。ちょっとお説教されるくらいどうってこともないし。むしろ、難度の高い術を成功させていると褒めてもらいたいわね。
バックヤードの扉を開き、明るい挨拶を発しながら出勤して、アタシはスズライト家の「ネビュラ」から一市民の「リゼ」へと心のスイッチを切り替える。
キッチンの角から柔らかな声がアタシを呼んだ。
「おはよう。早いのね、リゼさん」
どこかの貴族令嬢みたいにぐるぐる巻いた二つ結びの髪。黒いシャツの袖口や襟元にあしらわれたフリル。それらの幼げなパーツを引き締めるのは、艶やかなリップを塗った唇と上品に澄んだ桃色の瞳。
底の見えない、遠く別世界を映しているような目をしたその女性は、店長のパフィーナ。
「おはようございます!」
パッととびきりの笑顔を振りまいて返事をしつつ、ああやっぱり今日も変わらないわね、と心の中で呟いた。
初めて会った日から、アタシの目にはずっと見えている。
この人が全身に魔力を纏っていることが。
何で? と、まず思い浮かんだのは疑問符だった。
最初に彼女と会ったのはバイトの申し込みに行った日、面接の場。
頭のてっぺんから爪先まで余さず、薄い膜のように魔力の光を帯びている……つまり外見に魔法で細工している店長を見て、反射的に体がこわばってしまった。これまでの経験上、そうやって外見を偽った人間に関わると大抵ろくなことにならなかったもの。世間の共通認識においても、人の見た目を魔法で変えさせることはあまり良く思われていなかったはずだ。……ま、メアリーとティーナが言うにはあのミリーちゃんも変装に使ってたらしいし、一概に悪とも決めつけられないものなんだけど。
けど、たかだか一商店街の喫茶店の店長がどうして、魔法を使ってまで容姿を整える必要があるワケ? アイドルやモデルでもあるまいし。というかそれは、魔力に頼らずその身一つで勝負しているミリーちゃんみたいな実際のアイドルたちに失礼じゃない。
事務室には二人しかいなかった。「見えている」ことを悟られないよう、平静を装う。
「リゼさん、ね」
彼女は何食わぬ顔でアタシの向かい側の椅子に座って、でたらめに書いた詐称だらけの経歴書に目を通していった。
この人は容姿を偽っている。
だけどアタシも、容姿以外を偽っている。
互いに無言で嘘をついて向き合うアタシたちの間で、時計の針がカチコチと音を立てていた。
面接といっても、一週間の短期バイトだから内容はあっさりしていたと思う。問われたのは志望動機と意気込みくらい。店長はアタシの上っ面な回答に満足げな笑みを浮かべて頷いていた。そうして難なく採用が決まり、面接は終わった。さすがのアタシも、仕事に無関係かつ店長個人に関するような質問をこの場でぶつけるほど無神経にはなれなかったのだった。
その後、バイト初日で顔を合わせたときも、今日も、店長の容姿は同じだ。ティーナも誰も何も言ってないし、彼女は普段からいつでもこの姿で人前に出ているのだろう。
でもアタシには見えているわ。その体も髪も瞳も全部、この人が生まれ持った本当のものじゃないんだって。
見えないのは、その心の中だけだ。
しかも、働き始めてからも不可解なことが新たにもう一つ見つかった。
それは、昨日もよくオーダーされていた人気メニューのドリンクのこと。噂は聞いていたけど、現物を初めて間近で見て何らかのまじないが込められていることがわかった。
グラスの底に、溶けない角砂糖のように白い魔力の結晶が幾つも沈殿している。また、半透明のドリンクの中を魔力の帯が旋回して光の軌跡を描いている。体内に摂取する食品にまじないをかけることは珍しくないしそれ自体は別にいいんだけど、問題はその内容だ。
魔力の結晶も帯も異様なほど繊細で、繋ぎ目も綻びも一切見られない。その上、この魔力の正体が全く理解できない。
どんな意味を持つのかがまるでわからなかった。どれも一度も見たことがない型で、こんなのは初めてだった。
かろうじて、精巧に組み上げられた術式だということだけはわかる。美しすぎて、恐怖に似た畏れすら覚えるほど。アタシは何度も見間違いを疑った。
「リゼさん? どうかした? 二番テーブルは向こうの、女性三人の席よ」
「は、はい!」
店長に言われてハッとし、指示された場所へすぐに持っていく。その間も内心では懐疑心と動揺がずっと渦巻いていた。
そのドリンクが飲まれるところを盗み見ていたものの、何もおかしなことは起こらない。店長も特にその座席へ意識を向けている様子はない。飲み干されて空になったグラスには、魔力の跡も残っていなかった。
疑問を抱いているのはアタシだけ。
あのドリンクを作れるのは店長ただ一人で、他の店員には決して作れない。季節に応じて味を変えるそうだけど、店長のみが製法を知っている点は決して揺るがない。その理由は、密かに施されたあの魔力以外に何があるというのだろう。
訝しさが膨れ上がる。
外見を偽って、得体の知れない魔法を商品に込めて、一体何のつもり?
昨日はまだ初日だったし、他に対処すべき問題もあったから殆ど暇はなかったわけだけど。店長本人でもティーナでも誰でもいいから、とにかくあの魔法が何なのか聞いておきたいわね。
呪いや悪意でないことを願いたい。疑いたくない。けど、もしアタシやティーナたちに害を与えるものだと発覚したなら、問い詰めるしかないだろう。その結果こっちの嘘がバレることになったとしても、そのときはそのときだわ。
「着替えて手を洗ったら、日替わりの内容と予約席を確認してね。じきに皆も来るから、詳しい話はそれから聞くといいわ」
「わかりました」
「昨日は大変だったのではなくて? まだ慣れないでしょうし、わからないことは何でも聞いてちょうだいね」
店長は今日も薄い微笑みを湛えている。吸い込まれそうなその瞳の向こう側は、まだ見通せなかった。


番外10.キラの誕生日
別に期待なんかしてなかった。祝われたいなんて子供じみた気持ち、オレにはない。
爺さんが校長をしている学校に入学し、生まれ育った家を出て、学生寮に入った。
ホールケーキを囲み、明かりの消えた部屋でロウソクの火を消して、プレゼントをもらって家族で過ごす、そんな絵に描いたような誕生日からは卒業したんだ。
夏休みが終わるまで約一週間。開けた窓の外は雲一つない快晴で、時々柔らかい風が吹き込んでくる。その度に、引き上げたブラインドが揺らされてカサカサと音を立てた。とっくに宿題を全て終えていたオレはこれといってやることもなく、床にクッションを敷いて膝の上でホウキレースの雑誌を広げていた。
だからその陽気な声は、静かな部屋にキーンと鳴り響いた。
「キラ! ボクだよ! いるかい?」
壁と閉めた扉を突き抜けて、外にまで漏れ聞こえていそうな声量。座ったまま顔だけ向けて返事を投げる。
「何だよ、うるさいな」
「開けてよ、両手塞がっててさ!」
「わかったからちょっと静かにしろ!」
恥ずかしくないのかこいつは。
雑誌を雑に放って立ち上がり、ドアノブに手を伸ばす。
赤茶色の髪に、オレと同じ藍色の眼。声の主は、満足気な表情で両手に荷物を抱えたソラ兄だ。右手に持っているのは小ぶりな紙袋で、左手にもう一つ提げているのはケーキの包み箱だった。
「誕生日おめでとう! キラ!」
こっちがムスッとした顔をしていても、気にする様子は全くない。マイペースに笑ったまま右手の紙袋を突き出し、オレに持たせた。
「家に帰らないって言うから、プレゼント持ってきたよ。こっちはケーキだからね。甘いの好きだろ? 今日のおやつはまだ食べてないよね? あああと、父さんと母さんからも手紙が届いてたよ。その袋の中に一緒に入れておいたから」
オレが口を挟む間もなく、まるで自分の部屋に帰ってきたかのように、ソラ兄は部屋へ上がっていった。ついさっきまでオレが座っていたクッションの向かい側に腰を下ろし、ガラスのローテーブルの上に残りの手荷物を置く。実家では二人で一つの部屋を使っていたから、同じ感覚で入ってきているのだろう。オレはというと、せっかく手に入れた個室に侵食してくる兄が少し鬱陶しかった。
「何勝手に人のポスト開けてんだよ」
「いいじゃないか、家族なんだからさ。それとも、兄ちゃんには見られたくないものでもあるのかな?」
「あるわけない。……こっちの封筒は」
「ああ、爺ちゃんから預かってきたんだ」
「それは見たらわかる」
渡された紙袋の中に、ラッピングにくるまれた箱が一つと封筒が二つ入っている。オレが取り出した縦長の封筒には、黒のインクで「キラへ 祖父より」とだけ簡素に書かれていた。
両親の手紙以上に殆ど厚みがなく、封を切ってみると高額紙幣が一枚出てきた。
「現金かよ」
「好きなもの買いな、ってさ。今日は夜まで仕事みたいだけど、ちゃんとお礼言いに行くんだよ」
オレはその声に返事をせず、引き出した紙幣を封筒に戻す。
爺さんは、不愛想だ。だからといって嫌いではないし、オレ自身も人のことは言えないのだが。むしろオレはそういう性質を爺さんから受け継いでしまったのかもしれない。ソラ兄のような性格にも別に憧れてはいないが。
二つの封筒を机の引き出しの中へ仕舞って、箱を取り出す。ラッピングを解いて開けると、更に小さな箱がぎっしりと詰め込まれていた。
「……この箱も、爺さん?」
「いいや、それはボクから!」
「何だこの数……」
ソラ兄は何故か誇らしげだ。
家の形をしたチョコの中に、動物の小さなフィギュアがランダムで一つ入っている商品だった。パッケージの側面にサンプルの絵が描いてある。バリエーションは九種類。加えてシークレットが一つあるが、それは黒い円で塗り潰されてシルエットもわからない。詰め込まれているのは全部でちょうど十個だ。
「久しぶりに見つけて嬉しくなっちゃって。キラ、よくこういうの集めてたもんね?」
自信満々なソラ兄に、オレは口を尖らせる。
「いつの話してんだよ」
「あれ、そうだった?」
「引っ越し前で記憶止まってるんじゃないか? いい加減に子供扱いはやめろ」
「ごめんごめん。じゃあ、ケーキももう食べない?」
「……もらう」
決まり悪くてぼそりと言うと、ソラ兄は何がそんなに楽しいのかニコニコ笑いながらケーキの箱を開き始めた。それもまた今までの誕生日に毎年家で食べたチョコケーキによく似ていたのだが、オレは指摘せず口をつぐんでいた。
ソラ兄はオレが選ばなかった方のケーキを食べて、その後もしばらく部屋に居座った。前期末のテスト結果や夏休み明けの学園祭の予定など、オレの近況についてひとしきり聞くと夕方やっと帰っていった。誕生日にかこつけてオレに構いに来たんだろう。いつまでも弟離れしない、過保護な兄だった。
当然ながら、今年はそんな風にソラ兄が訪問してくることはない。
別に初めから期待なんかしてないが。
ブラインドの外に鬱屈とした曇り空が広がっていて、湿り気を含んだ空気がじっとりと肌にまとわりついてくる。爽やかな夏日だった去年とは大違いだ。
去年はあの後、休み明けに数日遅れの誕生祝いを教室でももらっていた。エレナが、クラス全員の誕生日を把握して余さずに祝っていたからだ。今のクラスにはそのように先導したがるタイプの奴がいないため、そうした風潮は無い。だか、だからどうということもなかった。
散歩にでも出ようかとぼんやり考えていると、ドアがノックされた。ドキリとしたのはちょうど外に行こうとしていたからで、その他に理由はない。
「よー、キラいるかー?」
扉を開けて、廊下の明かりが部屋に淡く差し込む。
正面に立っていたのはレルズだった。
「何だ、どうした?」
「どうしたって、今日キラの誕生日だろ? ……だよな?」
「そうだけど……お前に教えたことあったか?」
「女子が去年盛り上がってたじゃん」
「……よく覚えてたな」
「あーよかった、間違ってたら超ハズいとこだった。危ねー」
レルズは事も無げに言っていたが、オレは驚いた。当日のことですらないのに、あの一度きりで覚えている奴がいたとは思わなかった。わざわざ夏休み中の部屋にまで訪ねてくる奴がいたことも、驚いた。
「だからほら、これやるよ」
声も顔立ちも似ていないにも関わらず、駄菓子の包みを一つ差し出してはにかむ顔が少しだけソラ兄を彷彿とさせたのはこの場所のせいだろうか。
「でさ、今日割と涼しいし、またこの前みたく練習付き合ってくんね? あ、気分じゃないとか用事あるとかならいいんだけど……」
「ああ、そっちが本題か」
「そ、そんなわけじゃねーって!」
思ってもいない冗談を言い、内心の僅かな動揺を誤魔化す。レルズは素直に、真に受けて否定した。
「いいけど、お前宿題は?」
「まだ平気だって! じゃあ門のとこで待ち合わせな!」
ころっと調子のいい笑顔を見せると、ボールを取りに駆け出していく。その後ろ姿を見送った。
――散歩は、別に今日じゃなくてもいいか。
駄菓子をズボンのポケットに入れ、タオルと水筒を取りに部屋へ戻る。
去年ソラ兄に押し付けられた大量の食玩をふと思い出し、一人苦笑を洩らした。結局コンプリートすることのなかったあのフィギュアは、一時期は机に並べて飾っていたが今は引き出しの中に仕舞われている。
何となく、久しぶりに中を覗いてみた。つぶらな瞳の小さな動物たちが、汚れ一つ無いまま変わらずに眠っていた。


番外09.メアリーの手紙
――キラさんへ
――先日は家までお越しいただいて、ありがとうございました。
――この頃は気温が落ち着いて、過ごしやすくなってきましたね。今年の夏も終わりが近いのかもしれません。
――私たちには夏休みというものがありませんが、学校のお休みも、あともう少しなのでしょうか?
――この夏、私とネビュラはいつもと変わらず、家でお勉強やお稽古をしてばかりでした。キラさんは、どんな夏を過ごされたのでしょうか?
――お休みが明けたら、きっとお忙しくなるのですよね。次にお話できるのは、誕生日会の日でしょうか?
――お会いできることを楽しみにしていますね。
――ルミナさんにも、よろしくお伝えください。
――追伸
――この手紙をお出しする少し前に、キラさんからのお手紙が先に届きました。
――直接お越しになられてお話していただいたのに、改めてお返事も書いてくださったのですね。お気遣いいただき、本当にありがとうございます。
――よければまた、キラさんのことをお聞かせいただけると嬉しいです。いつでもお時間のあるときで構いませんので、お返事をお待ちしています。
――メアリーより
* * *
――メアリーへ
――前の手紙、読んでもらえてよかった。
――ちゃんと返事しておきたかったから書いただけだけど。
――別に、夏休みも特には何もしてない。
――もう学校は始まってて、もうすぐ学園祭がある。最近は放課後ずっとその準備をしてる。
――学園祭には来るのか?
――知りたいことがあれば答えるから、聞いてほしい。
――キラ
* * *
彼の手紙はいつも、無地の真っ白な便箋と封筒で送られてきます。
硬く強張った文章は決して長くなく、便箋には多くの空白。強い筆圧で書かれたような、濃くて角ばっている文字。ティーナは「男の子の字って感じ」と称したけれど、私は彼以外の同年代の男性の字を知りませんので、その表現はあまり理解できませんでした。
およそ半年前、初めて彼の書いた手紙を目にしたとき、期待にドキドキと高鳴っていた私の心臓は急速に萎み、代わりに大きな不安に襲われたものでした。
「リアス、ど、どうしよう、キラさんに嫌われてしまったかもしれない……」
「おや、どうされたのですか?」
おろおろとうろたえながらリアスに泣きつくと、長身の彼は膝を折って私の顔の高さに合わせました。
執事長であるリアスは、私と双子の妹のネビュラが生まれたときからずっと傍で世話をしてくれている人です。執事ではあるけれど、家族同然と私たちは思っています。
私は空行ばかりの便箋に目を落とし、涙が滲んでしまいそうなのを堪えながらリアスに訴えました。
「お返事が届いたのでしょう? 先程はあんなに喜んでおられたではありませんか」
「それが、キラさんのお手紙、とても短くて……。私、何か気に障ることを書いてしまったのかな。本当は私のお手紙なんて迷惑だったのかも。嫌々付き合わせてしまっているのだとしたら、私……」
「それは違いますよ、メアリー様」
リアスは、便箋を手にして震える私の両手を優しく包むと、震えが止まるまで握ってくれました。皺の入った顔に穏やかな微笑みを浮かべ、私の瞳を覗き込みます。
「メアリー様は、幼き頃よりティーナさんとお手紙のやり取りをされていましたね」
「うん」
「ですが、恐らくキラさんにはそのような経験がございません。男の子は、友人同士でお手紙を送り合ったりしないものですから」
「そうなの?」
「一概には言い切れないかもしれませんが、少なくとも私の経験上は。ですからキラさんも、お手紙には不慣れなのでしょう。その上お相手が異性ともなると、何と書けばよいのかわからずについ素っ気なくなってしまうのですよ」
「リアスも、旅行先のお友達に初めてお手紙を書いたときは、そういうことがあったの?」
まるでキラさん本人に話を聞いてきたかのように語るリアスが気になり、私は尋ねました。
リアスは、この家の執事になる前は一人で世界一周の旅をしていたそうです。その際に知り合ったご友人と今でも時々手紙のやり取りをしていることを、私は知っていました。
リアスは微笑んだまま、眉を少し下げて頷きます。
「はい、お恥ずかしながら。ですので、わかるのです。照れくさいか、緊張していらっしゃるか、そのどちらかでしょう。ご安心くださいませ。メアリー様がご心配なさっているようなことはありません」
「……教えてくれてありがとう、リアス。それなら、キラさんにお手紙のお礼をしないといけないね」
「ええ、それがよろしいかと」
リアスは私からそっと手を離しました。そのときにはもう、私の中の心細さは消えていました。
自室の机に向かいます。まっさらな便箋を広げて、ペンを取りました。
まずは言葉を紡いでくれたことへの感謝。
返事をいただけたことの喜び。
一通目とは違い、私自身の周りの出来事はほとんど書かずに、彼への気持ちが伝わるように精一杯の表現を尽くします。
そして、数日後、再び返事が届きました。
やはり短く淡白な文章でしたが、その中に記されていた一文が私の胸を打ちました。
――手紙を書くのは初めてだから、書き方が悪かったらごめん。
すっと風が吹き抜けて、心が軽くなったようでした。
キラさんもきっと、私と同じように不安な気持ちだったのでしょう。
このお手紙を読んでからは、どんなに短いメッセージもぶっきらぼうな印象を受ける言葉も気にならなくなりました。
ぎこちない文面は、彼の緊張や恥じらいの表れ。リアスの助言のおかげでそう信じられるようになった私は、手紙を送ることも返事を待つことも怖くなくなっていきました。
この半年、私たちが送り合った手紙の総数は決して多くはありません。ですが、数は少なくとも、一通一通全て大切なものです。
お互いの近況を短く伝え合うだけの、ささやかな文通に過ぎませんが、私にはそれが心の拠り所でした。手紙の中の言葉だけが、私と彼の世界を繋ぐ唯一のものだからです。
もしも、私がスズライト家に生まれることなく、彼と同じ学校に通っていたとしたら……そのように空想したことも、一度や二度ではありません。
彼と同じ学級で同じ授業を学び、同じ本を読み、自由時間には言葉を交わし、下校時には少し寄り道もして共に過ごす日々を夢想し、一人胸を躍らせたことも少なからずあります。
ですが、少し後には冷静になって、そのように都合のいい日々を送ることはきっと不可能だろうとも想像します。仮に私たちが同じ学校の級友同士だったとしても、勇気のない私は彼に挨拶の一つもできずに、三年間の学園生活を終えたことでしょう。
現実の私たちの距離は離れているけれど、だからこそ、私は彼と手紙を送り合うことができました。彼が綴る文字を知ることができました。今以上など、私の身には余ります。
顔も見えない、声も聞こえない、手紙越しのやり取り。
私はいつもその手紙の文字から想像を広げ、数えるほどしかお会いしたことがないキラさんとの記憶を手繰り寄せ、彼の姿を思い浮かべます。
絹糸のような銀髪。長い睫毛と、聡明な光を湛えた深い藍色の瞳。物静かで落ち着いた振る舞い。
目を閉じて、それらの一つ一つを思い出しながら、時間をかけて読みます。そうしていると、それがたとえ十行にも満たない淡泊な文章であっても、温かな思いが広がってくるのです。
私はお気に入りの紅茶を淹れた後、安らいだ気持ちで返事を書き進めました。
書き終えた便箋の端に微量の香水を吹きかけると、ふわりとした香りが広がります。庭に咲いている夏の花たちで作られた、愛着のある品です。この香りがキラさんへ届くときを想像すると、私は期待に胸が膨らむようでした。
宛名を記入するときは、未だにとても緊張します。たった二文字のお名前を書くだけなのに、何故でしょうか。胸の中で彼の名前を唱えると、それだけで私の体は内側からじんわりと火照ってくるのです。一筆一筆に力がこもり、手先が震えて、無意識のうちに息を止めてしまっていました。宛名を書き終えて顔を上げたときには安堵の息が洩れました。
便箋を丁寧に折り畳んで、パウダーブルーの封筒で包みます。それを一度机の上に置き、指先で優しく撫でました。
勇気のない私は、彼の元へ会いに行くことはできません。上手にお話をすることも、自然な笑みを向けることも。
だから、想いは全て手紙に託します。一通一通に心を込め、丹念に、彼の心へ届くことを願って。
レースのカーテン越しに差し込む柔らかい日差しが、辺りを照らしています。皺一つ無い封筒は、滑らかで心地よい手触りをしていました。
* * *
――学園祭、素敵ですね。どんな楽しいことがあったのか、ぜひ教えてもらいたいです。
――残念ですが、私たちは学園祭には行けません。一般のお客様の中に混ざることを、お父様が許してくれなくて……。
――でも、当日のことはティーナが聞かせてくれます。毎年、楽しみにしているんですよ。私たちのために、パンフレットにメモを書き込んでいて、それを見せながら話してくれるんです。――……


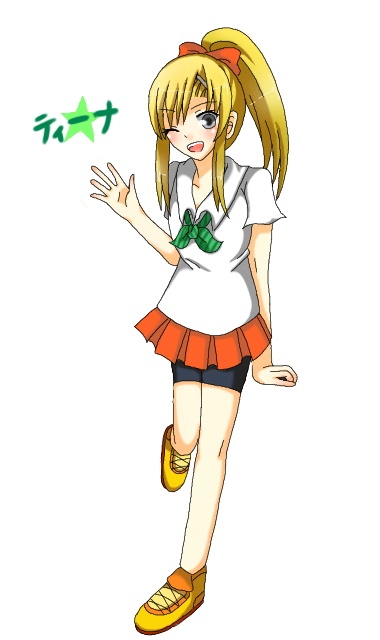

番外08.あの日のエレナ ~太陽の君~
学園祭当日の最後に発表する予定のグループがステージに上がり、リハーサルを始めた。わたしは講堂の壁に寄りかかって時計を一瞥し、その開始から終了までの時間を密かに計測する。先にリハーサルを終えてたむろしている生徒たちには、司会進行用の台本を読み直しているように見せかけていた。
一グループの所要時間は最長で十五分。このリハーサルでは少し早く終わった。でも、当日は観客のリアクションも入るから過信はしない方がいいはずね。
本当は、最後の発表者は彼らじゃない。
先日みんなに配布したパンフレットには載っていないシークレットゲストは、ミリーだ。この秘密は、彼女自身と先生、そしてわたしたち実行委員しか知らない。
活動を休止している彼女の最後のライブは去年の年末だから、実に九ヶ月ぶりのことになる。急遽決まったばかりの少し強引な計画だけど、成功すれば絶対にみんな喜ぶ。何よりもわたし自身が、その瞬間を見たいと強く願っている。ミリーのファンは学内に大勢いるし、わたしだって例に漏れずミリーのことが好きだもの。うまくいけば最高の日になるに決まってるわ!
ミリーが歌える時間を確保するため、プログラムを遅延させてはいけない。だからといって他の発表の時間を削るわけにもいかない。それぞれの発表の合間で、司会のわたしがどうにかして調整する以外に方法はない。しかも、リハーサルのしようがない一発勝負だわ。
頑張らなくっちゃ。
放課後になってから一時間くらい経過していて、窓の外は夕陽が眩しい。確認を終えたわたしはクラスの様子を見に行こうと思い、開け放っている講堂の出入り口に向かった。
「……あっ、エレナ」
その端に、ミリーがこそっと頭を覗かせていた。ステージからはギリギリ見えなさそうな角度だ。変装用の伊達眼鏡をかけて、通学鞄を手に提げている。
掃除の後ギアー先生と話をしに職員室へ行っていたけど、今終わったところなのかしら? それにしては結構長かったのね。
こちらに気付いて小さく手を振るミリーに、わたしも笑顔で応える。
「どうしたの? 誰かに用? ……ここで聞いても大丈夫なことかしら?」
「ううん、音が聞こえてたからちょっと覗いてみただけだよ」
「今日は裏門の方から帰るの? 珍しいわね。どこか寄っていくとか?」
「うん、その、正門からだとちょっと目立つかもって」
「……ん?」
言っている意味がよくわからなかった。
小声で囁きながら、ミリーの視線が斜め後ろに逸れる。その先を覗き込むと、忙しなく目を泳がせてそわそわと頭を掻きながらレルズが立っていた。距離を置き他人のフリをしているものの、ミリーを待つようにその場から動こうとしない。わたしと目を合わせた途端、バッと顔を背けた。
「い、一緒に帰るだけだよ。偶然、たまたま、同じ時間になってね?」
わたしの怪訝な顔を見て、まだ何も聞いていないのにミリーは言い訳を始める。
少し焦った様子、ってことは、それが危ない行為だという自覚は多少あるのね?
「……急ぎじゃないなら、いいかしら?」
一旦レルズは無視する。校舎と講堂の間の細い道に入り、裏手までミリーを連れ出した。ミリーは困ったように眉を八の字にして、黙ってわたしに付いてきた。
「……ダメかな? どうしても……?」
一本そびえ立つ木の影の中で向かい合う。弱気な声と上目遣いに、ぐらりと意思が揺らぎそうになった。
そもそも、いつものわたしならこんな風に止めたりしなかったと思う。でも今は時期が時期だから、慎重にもなるというもの。決して怒るつもりじゃない。咎めるわけでもない。でも、はっきり伝えないと。
責めたり押し付けたりするような言い方にならないよう慎重に、言葉を探す。
「今この時期に男子と二人で帰るのは、やめた方がいいんじゃないかしら……? もし変な噂が立ったりしたら、計画なんて言ってる場合じゃなくなってしまうでしょう? すぐそこの寮まででも、どこで誰が見てるかわからないし……。髪型を変えたり眼鏡をかけたりしただけでバレなくなるなんてことないって、ミリーもわかってるわよね?」
「うん……で、でもさ? お休みの日、初めてレルズ君と出かけたときは何もなかったよ。あのときはエレナも大丈夫って言ってくれてたよね?」
「それは……そうだったけど……」
ミリーが持ち出してきたのは、夏前の話だ。
わたしがレルズをミリーとの一日デートに連れ出した日のこと。
あれは、レルズを喜ばせようとして。彼の反応を見たかっただけで。あのときはそれしか頭になかった。ミリーの心配なんてしていなかったのが、当時のわたしだ。
「お、俺もエレナの言う通りだと思うっす……」
わたしが言葉に詰まっていると、ミリーの背後から遠慮がちにレルズが話へ加わってきた。こそこそと後を付けてきていたみたいだ。
ミリーが振り向き、レルズはたどたどしくも続ける。
「い、一緒に帰ろうって言ってもらったのは、マジで、そのー……う、嬉しいっすけど……! だけどもしそれで、俺のせいで迷惑がかかったらって思うと……」
「そんなの気にしなくていいのに! それに、ワタシとレルズ君は別に――」
「問題は、周りの目にどう映るかよ」
わたしはミリーの言葉を強引に遮った。
ミリーが口をつぐんで悲しげな顔で俯き、レルズも目線を上げようとしない。日陰になった辺りは薄暗く、重い沈黙がのしかかろうとする。
わたしは、ピンと指を上向きに立てて努めて明るい声を発した。
「要は、ミリーが男子と二人で帰ってるっていう状況が絶対にバレなければいいんでしょう?」
「そんなの、どうするってんだ?」
「手はあるわよ。ミリー、気は進まないかもしれないけど……」
「………」
ミリーが眉を寄せる。察しがついているんだろう。他人であるわたしが気付くことだから、ミリー自身も思い至っていないはずがないもの。
ミリーは、人の姿を変える魔法の使い方を知っている。
それには時間制限や副作用も特に無いらしい。どんな魔法でも普通は、一定時間経つと力が保てなくなってしまったりするはずなのだけど。
そんなに便利な力があるのに、ミリーは普段からそれに頼りたがらない。自慢もせず、それどころか、この魔法が好きじゃないとまで公言している。今まで休日や放課後に一緒に遊びに行ったことがあるけど、そこでも頑なに使おうとしなかった。
確かに、モラル的にはあまり良くない魔法ではあるけど、それだけが理由ではないと前に話してくれたことがある。
『見た目だけなんだけど、まるっきり別人になっちゃうの。なんだかワタシじゃないみたいで……ちょっと嫌なんだ』
ミリーにとっては譲れないこだわりがあるようだった。だからわたしたちも、顔バレして騒ぎになるリスクを承知の上でミリーの思いを尊重してきている。
でも今回ばかりは、話は別。
レルズは一人疑問符を浮かべていたけど、わたしの意図に気付くと納得して手を叩いた。
「……あっそうか、わかった! 変装できる魔法があるって言ってたっすね!」
「レルズも、それでいいわね?」
「ああ!」
レルズは期待の眼差しで、困り顔のミリーに向き直った。
意気揚々と目を輝かせる無邪気なその姿に、わたしは告げる。
「ほらミリー、レルズもこう言ってるわ。とびきり可愛くしちゃって?」
「えっ」
「……ん? あれ!?」
先にミリーが聞き返し、レルズも振り向いてぱちぱちと瞬きをした。
風と共に、沈んだ空気が彼方へ吹き飛んだのを確かに感じた。
「タンマ! 今の、どういう意味だ?」
「言った通りよ。さあ、女の子になりましょうか」
「待っ!? な、何でそうなるんだよ!? 俺が変装すんの!?」
「だってミリーの方が姿を変えちゃったら、ミリーと一緒に帰ってる気がしないんじゃない? 男のままじゃ変身する意味もないし」
「うっ、それは……け、けど! 他に何かないのか!?」
「じゃあ犬とか猫とか、動物?」
「それはワタシができないかな……」
ミリーが苦笑いする。
レルズは一度異議を唱えたものの、それ以上反論できないまま口だけをぱくぱくと迷わせた。
「何も中身までなりきれとは言わないわよ。女装じゃないんだから」
「同じじゃね!? ってか、お前面白がってんだろ!」
「失礼しちゃうわ。わたしは本気で協力しようとしてるのに」
と、言いながら、自分では真顔のつもりなのだけど、ひょっとしたら口角が上がるのをごまかせていなかったかもしれない。仕方がないわよね、レルズが面白いんだもの。
「ちょっとの間見た目だけ女の子になるだけで、周りの目を何も気にしなくてよくなるんだからいい話じゃない?」
「……レルズ君、どうする?」
「ぐっ、う、うぅぅ……!」
ミリーは、レルズの意思さえよければわたしの提案を飲んでくれそうだ。そう言うような彼女の視線に、レルズが唸る。
「わかった! やってやる! ひ、一思いに頼むっすー!」
叫ぶと、勢いよく腕を横に広げて大の字で仁王立ちになった。射的の的にでもなるみたいにギュッときつく目を瞑って、歯を食いしばる。
ミリーが杖を手に取り、レルズの頭上にくるんと回した。白い光が舞い、螺旋を描きながらレルズを爪先まですっぽり包み隠す。この瞬間を間近で見るのは、初めて説明を聞いたとき以来だわ。
光が弾けて周囲がパアッと一瞬明るくなり、レルズの姿が露わになった。そわそわと、困惑しつつ自身の体を見回し始める。
「……お、おぉ……? ど、どうなっ――うわ声高っ!? これ俺の声か!?」
レルズが叫び、わたしも目を丸くした。全体的には元々の外見の特徴が結構残っているように見えたけど、喋ると別人だ。ハイトーンボイスがキンキンと響いた。
服は、男女の差がない学校指定の運動着。背の高さや体型にはあまり変わりがない。髪は、黒のメッシュがなくなっている。だけどそれ以上に大きな変化があって、動物の耳みたいな小さいツインテールがくっついていた。元々童顔気味の丸い頬はピンクに色づき、目元や唇も、軽く化粧を乗せたようにほんのりと可愛らしさが足されている。
彼(彼女?)は慌てふためきながら、ぺたぺたと自分の全身を手で確かめた。頭に触れて髪型に気付いたときには、また大きく目を見開いて怪訝な顔をした。
「うまく言えねーけど、何かすっげー変な感じ……」
「だよね……あ、鏡あるよ。見る?」
ミリーが鞄から手鏡を取り出そうとすると、仰け反りながら両手を突き出して制止させた。
「えっ、わーっ、いい! いいです! 見せなくていいっす! まだその、心の準備が!」
「そ、そう?」
気圧されて、ミリーは困惑した笑みを浮かべる。
レルズはグイッと体を捻ってわたしの方に振り返った。
「エレナ! 今『俺』ってわかんなくなってるよな!?」
「え、ええ、そうね。言われてもわからないと思うわよ」
「よし! じゃあオッケー!」
そう答えるとすぐに向きを戻す。気を紛らわすみたいに、腕を振ってわざとらしく大声を上げた。
そのバタバタした挙動も口調も素のままだけど、ただの男勝りな女の子にしか見えない。勿論、姿そのものに不自然さや違和感もない。
このレルズの姿を見ていてふと脳裏をよぎったのは、昔、男の子になりたいと思った日のこと。わたしが男の子だったら男子だけの遊びの輪の中にも自然に混ざれるのに、「彼」ともっと長く一緒にいられるのに、と。
懐かしい思い出だわ。
レルズはどうなのだろう。男子でも、そんな風に思ったりすることはあるのかしら……?
「本当にいいの? レルズ君、無理してない?」
ミリーはまだ少し遠慮した様子だった。レルズは拳をぐっと握ったまま、彼女を安心させるように屈託なく笑う。姿も声も違うけど、その振る舞いはいつものレルズだ。
「平気っすよ! 変な感じはするっすけど、すぐ慣れるはずっす! こ、これなら、その、人に見つかんねーようにしたり時間ずらして校門出る必要もないっすよね?」
「うん……レルズ君がいいなら」
その笑顔に釣られて、ようやくミリーも笑みを見せた。
普段の教室で見せる明るくて元気な笑い顔とは違う、柔らかな表情。これが彼女の素顔なんじゃないかって、何となく、わたしはそんな気がした。
「委員会のお仕事中だったのに付き合わせちゃってごめんね。でも、ありがと」
ミリーは気恥ずかしげにはにかんで言う。
「いいのよ、全然。面白かったもの♪」
「やっぱ面白がってんじゃねーか!」
「エレナも一緒に帰らない?」
「せっかくだけど、わたしは教室をもう少し手伝っていくわ」
「あ、明日はワタシも残るから!」
「うふふ、ミリーには当日お願いすることがいっぱいあるんだから大丈夫よ。準備は任せてちょうだい!」
わたしは来た道を戻っていく二人を見送った。
女子生徒に扮したレルズの偽名を決めようとしているらしく、ミリーが何か口にするとレルズは焦ったように甲高い声を上げる。その後ろ姿はやはり女の子にしか見えず、疑いの余地は何もない。角を曲がる手前でミリーが振り返り、こっちに手を振った。
少し遅れてわたしも裏庭へ戻る。門の方を見ても二人の姿はもう見当たらない。
本当は後を付けていきたいけど、今日は我慢しましょうか。
心地よい風が吹き、暮れていく夕陽が眩しくてわたしは目を細めた。
西日を背に受けて校舎に向かう。目前に迫っている学園祭当日のために、わたしはわたしにできることをしなきゃね。



番外07.スティンヴの花束
このぼくが本気で手を貸したのだから、一位になって当然だ。
華々しい表彰の場に出る代表者を薦められ、それも引き受けた。この勝利の立役者がぼくだということはクラスのメンバーも理解しているらしい。
ぼくの完璧な執事らしい着こなしと立ち振る舞いが評判を呼んだ。同級生には接客態度の手本を見せてやった。全ての客を満足させ、ぼく目当てで生じた行列も捌き切ってみせた。
ぼくの後をちゃんと着いてこれた奴らにも、丁寧で統一感のある内装を作り上げた奴らにも、誇るべき功績がある。間違いなく総合的なクオリティでも一位だ。なるべくして勝ち取った順位だと自負していた。
学園祭の模擬店で一番に選ばれたクラスの代表として、全校生徒と一般客の前に登壇する。ぼくの横に並び立ったのは二人。一人は、有志パフォーマンス部門で一位を取った演劇の主役をやった上級生。もう一人は、サプライズでライブを行ったアイドルのミリーだ。ミリーは投票とは関係なく特例らしかった。
名を呼ばれてからもステージ下でもたついているミリーが不可解で、声をかける。
「嬉しくないのか? 今日一番だったのは誰が見たってあんただ。素直に受け取ればいいじゃないか」
「えっ」
「何?」
何故だか目を丸くしていた。ぼくはただ思った通りに褒めただけなのに、その顔は何なんだ。おかしなことは言ってないだろ。
ぼくらの後に壇を上がってきたのはネフィリーだった。長机の上に用意された三つの花束が一人ずつ手渡しされていく。まずは上級生へ渡されて、ぼくの番はその次だった。
体の前に花束を抱いたネフィリーがぼくの正面に立つ。オレンジ色に発光しているコミナライトの花は、春先からネフィリーが育て続けていた花だ。途中からはぼくも世話を手伝った。
この花束を作る係が割り振られていたのは、ぼくらのクラスだ。つまり自分が育てた花で自分が作った花束。それが自分の手に回ってきたことになる。結果だけ見れば、まるで自分自身に祝われたようなものだ。
ネフィリーがぼくに花束を差し出した。
受け取りまで自分でやる羽目にならなかっただけマシか。
花束の中心でコミナライトの花弁が微弱な光を放っている。オレンジの光とステージの照明が映り込んだネフィリーの瞳もまた、輝いて見えた。
「おめでとう」
「ぼくが本気を出せばこれくらい余裕に決まってる」
手渡されながらそう返すと、ネフィリーはクスリと微笑んで次の花束を取りに戻っていった。いつもと違って凝った二つ結びにしたエメラルドの髪が、緩やかなウェーブを描いてなびく。
やけにあっさりと終わってしまった。
少しばかり喋り足りなく感じたが、湧き上がる拍手と歓声ですぐに気を紛らわせた。
大勢の観衆の前で大々的に称えられるのは気分がいい。そのぼくの最も傍にいるのがこいつだというのも、悪くない。
だが同時に、微妙にすっきりしない気持ちも残った。それが物足りなさかと言われると、少し違う気がする。
この時間をぼく一人で独占していたかった、そんな感情を覚えた。
ぼくらしくもない。初めての思いだった。
最後の一つはミリーの分の花束だ。ぼくたちのクラスで作ったのは二つだけだった。一つだけ秘密にしていたか、後から増やしたかのどちらかだろう。
ぼくは「ミリー」というアイドルのことを何も知らない。特に知りたいとも思ってはいない。ライブに参加したことはないし、興味を持ったことも正直なかった。だから今日初めてそれを見た。
だが、ぼくにはわかる。具体的にどれくらい期間が空いていたのかは知らないが、並大抵の努力ではあれだけの立ち回りを演じることは到底不可能だと。
現在は活動休止中だと本人は言っていた。しかしあれは、ずっと休んでいた人間が昨日の今日で可能なパフォーマンスじゃない。たとえ過去の積み重ねがあるとしてもだ。ぼくは歌や音楽には明るくないが、運動でも勉強でも何でも同じことだろう。
活動休止と言いながら、実際はこの日のために影でかなりの研鑽を重ねてきたに違いない。たった一曲の歌唱でぼくにそう思わせるだけの力がミリーには伴っていた。
上辺の知名度と人気のみをいいように使ったあのクラスの売り方はダサいが、そうしたくなるだけの実力とカリスマがミリーにあることは理解できた。努力は報いられるべきであり、相応の結果を出したのなら認められるべきだ。
表面的には、実行委員の一存でミリーが贔屓されているかのように見えたことかもしれない。だがぼくには何の異論もなかった。
当のミリー自身は尚も遠慮して、なかなか花束をもらおうとしない。するとネフィリーが業を煮やした様子で、迷っている空の手を握り強引に受け取らせた。
その行動を見てぼくはつい少し笑みをこぼしてしまった。
あいつは何なんだろうな。単に普段は猫を被っているだけなのか。それにしては詰めが甘いというか、今のように容易く仮面が剥がれて素顔が垣間見える。隙だらけだ。そのくせ人に頼るのは下手で不器用な、放っておけない気になるような、変な奴。
花束を持たされたミリーが、感極まったのか涙を零している。ネフィリーは微笑み、何か声をかけた。整列した生徒の拍手の音やざわめきに掻き消されて会話は聞こえてこないが、最後には二人とも笑い合っていた。
淡く発光する橙の花とスポットライトが、ミリーを照らしている。
舞台の主役はそっちだろう。
だがその光は同時にネフィリーにも当たっていて、視界の隅に映るその横顔へぼくの目は無意識に惹きつけられていた。
そこに花があるせいだ。
花が好きだと語っていたからだ。
だから花の印象に引きずられただけ。
綺麗だと思ったのは、花束と光の方のことだ。
教室に花束を持ち帰る。片付け前の教室はまだ屋敷を模した様相で、レースのカーテンやテーブルクロスがそのままだ。適当に、飾りの造花の横に並べて置いた。
底がしっかりしていてこのままでも自立する形だから、花瓶を用意して移し替えたりせずともこのまま置いておける。そうなるように作った。昼間や明かりの下だとコミナライトの光は目立たないが、他の花と比べて大きめの花弁はそれだけで存在感がある。白一色で整えられた教室にポンと咲いたオレンジは華やかだった。
やっぱり花は咲いてこそ意味がある。咲かなければ見向きもされない。花を咲かせていなければこの一輪はここにいないのだから。
花束の中で、ぼくの目に映るのはコミナライトの花だけだった。
夏の間、ぼくは朝や夕方に中庭の花壇の面倒を見に行っていた。それが癖になり、夏休み明けの登校日も朝早く来て様子を見に行くのが決まりのように馴染んでしまっていた。時には、本来の世話係のネフィリーよりぼくの方が早く到着することすらあった。
数か月間育てていたコミナライトの花がようやく咲いたのは、学園祭当日の一週間前だ。前日はぴたっと閉じていた蕾の先が数センチ膨らんで開いているのを、朝一番にぼくとネフィリーの二人で確認した。
明るい空の下だから花そのものは光っていないが、薄い花びらは陽の光を透かしている。柔らかい朝日が朝露に反射した姿は十分に光って見えた。
『今くらいの季節に似合う花だね』
『……どういう意味?』
『ううん……何でもない。ちゃんと咲いたこと、後でパルティナ先生に報告しないと。クラスも違うのに今日まで手伝ってくれてありがとう』
ネフィリーが和やかな雰囲気でぼくに笑いかけてそう言ったとき。それは喜んで受け取るべき感謝の言葉だったのに、ぼくは言葉を返すことができなかった。
その笑顔に突き放されたかのように感じた。用済みだと告げるような響きを持ってぼくの耳には届いた。
ぼくは馬鹿じゃない。夏が過ぎ、全ての蕾が重く頭をもたげ始めた頃にはとっくに想像がついていた。もし時間が止まったならと、無意味な仮定も時には頭に浮かんでいた。その意味と理由を深く考えたくなくて、目を逸らした。
学校でぼくらを繋ぐものは、この中庭で流れる時間しかない。クラスも趣味も異なるぼくらはこの花壇でしか接点を持つことがない。学校からホウキレースの場へ出れば、今度はゼクスの存在がつきまとって邪魔をする。認めたくはないが、ぼくは未だに奴に敵わない。
花開いた日の翌朝も花壇を見に行ったが、ネフィリーが姿を見せることはなかった。世話する必要のない花を一人で見下ろす以外にやることはなく、風が肌寒いだけだった。
その日以降、ぼくは朝方も放課後もあの花壇に近付いていない。花束を作った日も、必要な花は担任が授業前に用意して持ってきたから花壇の元へは行かなかった。
だが、今ぼくは無性にあの花を見に行きたいと感じている。
何故だろう。ただ、この感情を抱えたまま明日の休日を迎えるのは嫌だ。気分が悪い。すっきりしない。
夏休みを経て、自分でも気付かないうちに花を見に行くことが習慣化していた。それに伴い、ぼくはあの花壇とコミナライトの花に対し愛着に似た感情を抱くようになっていたかもしれない。
花壇に向かったところで、どうもしない確率は高い。余計に虚しくなるだけかもしれない。それでもぼくは、何かが起きる僅かな可能性に期待し焦がれていた。
途中でグラウンドを通るし、ついでだから後夜祭も軽く覗いていこうかと思う。キャンプファイアにもフォークダンスにも別に興味はないが。だが、そう、そこにもコミナライトの花の明かりがあるはずだからだ。
掃除を終えたら、気持ちを確かめに行こう。
あの場所へ残されているはずの、温かな淡い光の元へ。



番外06.ネフィリーの後夜祭
キャンプファイアを中心に照らされて、グラウンドは楽しげに輝いている。学園祭最後の催しであるフォークダンスがもうすぐ始まるところで、炎の周囲には生徒たちの輪が作られていた。
私はその輪の手前でためらいを覚えて、クラスの皆と別れた。横に曲がり、一人で中庭の方に足を進める。燻る火種の匂いの混じった風が頬を撫でて、クラスメイトが二つに結わえてくれた髪を揺らした。
暗がりの中に轟々と燃えている大きな炎。自分はその影に飲み込まれてしまいそうな気がした。
私は今でも、明かりの中にいることに負い目を感じる。馴染めている自信を持てずにいる。こうした行動が余計に拍車をかけるのだと頭ではわかっているけど、どうしても慣れることができない。
離れるにつれて炎の明かりは届かなくなっていった。薄暗いこちら側の方が私の心は落ち着いた。
視線の先、夕闇の中に、地面に近い位置で橙色の灯火がぽつぽつと浮いているのが見えてくる。コミナライトの花壇だ。表彰の花束や後夜祭の装飾に使われても全て摘み取られたわけではなく、何本かは植えられたままだった。
皆グラウンドに行っていて誰もいないと思いきや、花壇の横にしゃがみ込んでいる人影があった。
私服姿だけど、私たちと年齢の近そうな少女だ。ふわふわとしたカーディガンと瞳、外巻きの髪の毛は空色。半分ほど橙の照り返しに染まっている。
少し離れた場所に立ち止まっている私のことには気が付いていないようで、大きな声で独り言を言っている。
「ミリーがもらってた花束のお花! 凄いなあ、本当に光ってる。家の近くに咲いてるのは見たことないけど図鑑には載ってたかも……何て名前だったかな……?」
声をかけるべきか迷っていると少女がこちらに振り向いて、視界に入ってしまった。
その花はコミナライトだよ、と教えて、近付く。
少女はハッと目を丸くして左右を確認すると、おずおずと私を見上げた。気恥ずかしそうに体を縮こまらせ、声をすぼめる。
「え、えっと……、わたしの声、聞こえてました……?」
「うん、……ごめんなさい?」
「い、いいえ! 誰にも聞こえてないと思ってたから驚いただけで、その、教えてくれてありがとうございます~」
髪のハネを手櫛でいそいそ直し、動揺を落ち着けるとにっこり微笑んだ。柔らかな印象の子だった。
「ミリーに花束渡してた人ですよね」
「う、うん」
朗らかに話しかけてくる。壇上に立つとき、皆ミリーを見ていて私のことなど誰も気に留めていないだろうと言い聞かせて緊張しないようにしていたのに、彼女にはしっかり顔を覚えられていたらしい。恥ずかしさをごまかしてミリーのファンなのかと尋ねると、少女は元気よく頷いた。
「あなたもそうじゃないんですか?」
「私は、今日初めてミリーが歌ってるところを見たよ」
「え!?」
「コンサートに行ったことは無かったし、ミリーの歌のこともよく知らなかった。私が知ってたのは、活動を止めてからのミリーだけなんだ」
「……そうだったんですね」
少女の声のトーンが少し落ちた。ミリーが活動休止を発表した日のことを連想して、そのときの気持ちを思い出したのかもしれない。気が利いていなかった。言わなければよかった、と後悔する。
私はその当時のことを知らないし、アイドルというのも正直今もちゃんとわかってないけど、ファンの人たちの熱量と歌って踊るミリーの姿を実際に目の当たりにして考え方を少し変えさせられたと思う。
「ミリー、凄かった。みんなが噂する訳がわかったよ」
「そうでしょ! あなたもファンになっちゃったんじゃないですか?」
「ふふ、そうかもね」
すぐに少女は元の調子に戻り、私は安堵した。
私にとって、ミリーはミリーだ。そこには何の肩書きも無い。ただ純粋に一人の友達として、彼女を凄いと思う。尊敬する。みんなを楽しませようとする気持ちに溢れていて、誰もが惹きつけられてしまうと思った。
この感嘆がファンの人たちと同じものだというのなら、きっと少女の言う通りだろう。
と、思ったのだけど、次に彼女が発した言葉は私には意外だった。
「でも、あれはまだミリーの全力が出てなかったな。しばらく休んでいたから仕方ないとはいえ、本当のミリーはもっと凄いですよ」
「そ、そうなの? 私には全然そうは見えなかったけど。ファンなのに厳しいんだね……」
「ファンだから、厳しいのです」
おどけた口ぶりで言った少女は楽しげだ。
少女は私を見上げて笑いかけると、明るい声色で話を続けた。
「羨ましいなー、ミリーと同じ学校。わたしもこの学校に通いたかった」
「他の学校? ……サンローズの人?」
「ううん、ティンスターにある教会学校です。わかります?」
「ティンスターって……ミリーの家がある町だったような」
「そうなんですよ~」
私の疑問に答えて、誇らしげな顔をする。自分の故郷からミリーのような有名人が輩出されたことが自慢みたいだ。
しかし不意に、少女は目線を落とした。表情が陰る。
「本当に……こっちに来たかった。そうしたら、きっと……あなたとも友達になれたんだろうな」
最後の方は囁き声のようだったけど、周りは静かだからはっきり聞き取れた。
ミリーじゃなくて、私……?
少女は立ち上がり、横顔を向けたまま独り言のように呟く。
「もう、行かなきゃ」
このとき、よく見たら彼女が履いているのはスリッパだったことに気が付いた。来客用の備品は学校名が印字されていたはずだけど、彼女のそれは無地だった。
少女がゆっくりとこっちを向く。海のようにさざめく瞳で私をじっと見つめて、微笑みかけた。
「お話できて楽しかったです。ありがとう」
空色に橙色が混ざり合った少女の姿はまるで夕暮れみたいだ。沈んでいく太陽と共に夜の闇へ溶けて消えてしまいそうに儚い。
何故か、漠然とした不安に駆られた。
「ま、待って。あの、せっかくだから、名前……」
「――まさか、いるとはな」
「え?」
呼び止めようとしたところに、私ではない別の声が被さる。男子の声色。
振り返るとスティンヴがいた。昼間や表彰のときと同じ執事の格好で、校舎の角から気だるげに見ている。
「どうしたの、こんなところに何か用事? 後夜祭は?」
「別に……。あんたこそ何してんだ。行かないのか」
「私は今、この子と話を……」
近付いてくるスティンヴに言いながら、向き直る。
「……誰もいないけど」
そこに少女の姿はなかった。
私の正面に立っていたはずの彼女は、見渡してもどこにもいない。
「学校の奴? ……一般公開の時間はとっくに過ぎてるだろ」
スティンヴに白けた視線を向けられた。信じていない顔だ。
確かにそこにいたのだけど。
まるで幻を見せられていたような、不思議な感覚が残っている。
もしまた会えたら、名前を聞けるだろうか?
次の機会があるなら、そのときはミリーも呼んで三人で話をしてみたいと思う。
少女が屈んでいた場所に開いた隙間は、ゆらゆらと揺れる橙色の灯火に丸く照らされていた。


110.宴の終わりと約束の時
キラと共に校庭に出たときは、既にフォークダンスが始まった後でした。グラウンドの中央に揺らめく大きな炎を囲んで、二人ずつペアになった生徒たちの輪がゆっくりと回っています。辺りの屋台は片付けられていました。
炎の明かりの輪の外側にも、小さなランプが円を描くように点々と灯っています。柔らかな橙色に発光する、コミナライトの花です。茎から下を切り離されて、釣り鐘型の丸い花弁のみが下向きで宙に浮いています。夕闇の中、遠目に見える幻想的な風景とかすかに聞こえるスローテンポのダンスミュージックは優しい雰囲気でした。
私の数歩離れた後ろをキラが付いてきています。キラは廊下までは私の隣を歩いていたけれど、外に出てからは横に並ぼうとしませんでした。
キャンプファイアの周囲以外にも人の姿があります。皆が全員フォークダンスに参加しているわけではなく、コミナライトのランプの下で談笑をしている生徒たちの姿もちらほらと見られました。
照らされている光の中へ入る前に、私はランプの輪の少し手前で足を止めて振り返りました。声が届きそうな距離に他の人の姿がないことを確かめて、キラに尋ねます。
「キラはスズライト家のパーティって行ったことある?」
「? いや……急に何だ?」
「今度のメアリーとネビュラの誕生日会に誘われたんだ。キラも行くんだよね? どんなことするのか知ってる? もしダンスの時間があったらどうしよう、ちゃんと踊れる自信ないよ」
「……そうか。ルミナも来るのか……」
キラはぽつりと呟いた後、抑え気味の声で答えました。
「オレも初めて行くから、どんな感じかは知らないけど。向こうだってルミナにそこまで期待してないだろ」
「でも、心配だよ。そうだ、キラ! ちょうどいいから今のうちに、私の踊りでどこかおかしなところがあったら教えてくれないかな?」
「は? 何の話だ。ダンスパーティだって決まったわけじゃないだろ。フォークダンスとも違うだろうし」
「念のため! 何もしないで行くよりはいいでしょ?」
私はキラの手を取りました。
フォークダンスは口実でした。お兄さんのことで悩みを抱えているキラだけれど、今このときは楽しんでいてほしい。元気を出してほしい。そのために私ができるのは、一緒になって楽しむこと。そう思いました。それが真に正しい選択だったのかはわからないけれど、キラの学園祭の思い出が明るいものであってほしいと私は願っていたのです。
キラは握られた手を振りほどこうとしましたが、私は離しませんでした。控えめだったキラの声量が大きくなります。
「そ、そこまで付き合うとは言ってない! 一人で行けよ!」
「一人だけじゃ混ざれないよ」
「別にオレじゃなくたって、他の奴らが――」
「ううん、キラじゃないと駄目だよ。キラがいいんだ!」
「!?」
「スズライト家のことをお話できるのはキラしかいないからね! 行こ!」
びたりと動きを止めて脱力したキラの手を、改めてぎゅっと握りました。コミナライトの光は夕陽に似ていて、まるで最初の日の彼を見ているようでした。
フォークダンスの輪へ途中から混ざるのは目立つかもしれなかったけれど、不思議と私は気になりませんでした。それよりも、彼と一緒に行きたい気持ちがずっと強く勝っていました。
明かりの輪の中は暖かく、燻った煙が僅かばかり目と鼻に沁みました。
学園祭はここで終わりを迎えます。
ですが、この祭りの夜には続きがありました。
それは私の知らない、物語の裏側。約束されていた終幕。
知っていたのは彼女たちだけでした。
グラウンド中央に炎が灯って、歓声と拍手が湧き起こったとき。
キャンプファイアの火を点けたのは学園祭実行委員会の皆です。それがこの日最後の彼らの仕事でした。
組み上げられた木の周囲を十数人の生徒たちがぐるりと囲み、一斉に杖を掲げ火の玉を飛ばして点火します。一つ一つは小さな火だけれど、どんどん燃え広がってあっという間に大きな炎を形成しました。
エレナは、集まってきた一般生徒を誘導しフォークダンスの準備を整えています。その一方で、輪の外側を頻繁に気にしている様子です。
目を向ける先には、音楽プレイヤーを設営するための机と群青色のテントがありました。そこで皆にアナウンスをしているのはジェシカでした。
レコードの音楽が流れ、輪が回り始めます。
エレナは参加者の中に混ざったままでした。向かい合った見知らぬ男子生徒に手を差し出されて、少し困惑しながらダンスに加わります。表向きは周囲に合わせて楽しげにしつつも、エレナの意識はずっとジェシカの方にだけ向いていました。
曲が一巡して、ペアが入れ替わります。次にエレナの正面へ立った顔には覚えがありました。ミリーやスティンヴと並んで表彰台へ上がっていた先輩でした。
舞台用の煌びやかな衣装で炎の明かりを背に受けた立ち姿は非日常的で、本物の王子が現れたかのようです。長身の先輩を間近で見上げたエレナの顔に動揺が生じ、頬が淡く熱を帯びます。
ところが、エレナは先輩の手を取らずにくるりと踵を返しました。輪の外を見渡し、数歩離れた地点からフォークダンスを眺めていた女子生徒を見つけると、手招きして呼びかけます。
「あの! いきなりで悪いんですけど、よかったらわたしの代わりに入ってくれませんか? 用事を思い出しちゃって、抜けるので」
唐突に話を振られた彼女は戸惑っていましたが、相手の先輩の姿を見ると一層恥じらいを露わにしました。
返答を待たずに、エレナは輪を外れて駆けていきます。暗がりに出る直前で振り返り、彼らが踊り始めていることを確認すると、満足気な笑みを浮かべて歩みを再開させました。
エレナは一度グラウンドから離れて、ミリーがライブで歌っていた曲の鼻歌を歌いながら真っ直ぐに暗がりの中を進みました。
ぐるりと大回りをして、明かりの当たらない校舎の壁に沿って再びグラウンド側へ戻ってきます。向かう先はジェシカが一人立っているテントです。彼女の姿を視界に捉えたところで、木の陰にサッと身を隠しました。
ジェシカは何度も前髪を整え直してはキョロキョロと周囲を窺い、落ち着かない様子です。それを横から覗き見るエレナの口元には自然と笑みが洩れます。エレナが隠れていることには全く気が付いていないようでした。
ジェシカが意中の相手とフォークダンスの約束をしていることを今朝聞き出してから、エレナはこのときを待ち望み続けていました。今に始まったことではない、彼女の癖のようなものでした。
報いを受けたのだろうと、後に彼女は語ります。
しばらく待ち続けていると、一人の人影がエレナの隠れている木の前を通り過ぎていきました。
ジェシカの傍へ駆け寄っていく、小柄な少年のシルエット。
その人物に気が付いたエレナは自分の見たものを疑いました。暗闇に目を凝らして何度確かめても、かえって疑う余地がなくなるばかりです。胸がざわつき出します。
ジェシカと約束を交わしていた相手、レルズが、彼女の正面で立ち止まりました。
テントの下に入ると影が色濃く落ちて、二人の姿を闇の中に隠します。彼らの表情も話の内容も、エレナには何一つ伝わってきませんでした。
二人が動き出して、フォークダンスの輪の中へ歩いていきます。
エレナは木陰に添えた手に力を込め、瞬きもせずに二人の後を凝視しました。もう片方の手は胸元で握られていて、口元は小さく震えていました。
繰り返しのメロディが一巡りし、生徒たちの輪が二つに分かれていきます。ジェシカとレルズはその間へ加わって、どちらともなく、ぎこちなく手を取りました。
温かな明かりの輪の中で、目を合わせた二人の横顔がちらちらと照り返しを受けています。
初めの内は、レルズは表情も動きもこわばっていました。一方のジェシカは穏やかな微笑みを浮かべていて、彼の手をそっと引きます。次第にレルズの様子も柔らかく解れていき、彼のリードでジェシカがなめらかにターンしました。
回る彼女に合わせて、制服のスカートもひらりと翻ります。
振り返った顔を炎が美しく照らし出しました。その一瞬に垣間見えたジェシカは幸せそうで、彼女を見つめてエスコートするレルズもそれまで見せたことのないような優しい眼差しでした。
エレナは二人から目を離すことができませんでした。その場を動くこともできずに、立ち尽くしたままでした。
音楽が止まります。
最後の一周でした。
繋いでいた手がするりと解けます。
集まっていた皆の拍手が夕闇の空に溶けていきました。その間すらも、エレナは縛られたように微動だにしませんでした。
皆が校庭から去っていく中、ジェシカとレルズの二人だけがその場に立ち止まり続けます。燃え盛る炎を背景に、黙って向かい合ったまま動きません。二人はずっと俯いています。
周囲からすっかり人の姿がなくなって静まり返った頃、レルズの口が僅かに動いて言葉を紡ぎました。
その表情は前髪と炎の逆光に遮られてわかりません。話の内容もエレナには一切聞こえてきません。
ジェシカは両手に強く力を込めて唇を噛み締めていましたが、パッと顔を上げると明るく口を開きました。絞り出したような笑顔はひどく苦しげでした。
レルズが何か付け加えて言ったようです。
ジェシカは、首を優しく横に振って答えました。
二人が口をつぐみ、再び沈黙が訪れます。
先に重い一歩を踏み出したのはレルズでした。ジェシカの横を抜けて通り過ぎたところで少しの間だけ立ち止まったけれど、振り返らずに走り去っていきました。残されたジェシカが彼の後を追うことはありませんでした。
ぴくりとも動かなかったジェシカが不意にしゃがみ込んで膝の上にぐったりと顔を伏せ、それを見た瞬間、エレナは弾かれたように飛び出していました。
駆け寄ってくるエレナの足音に、ジェシカが動揺した目を向けます。
「エ、エレナちゃん!? ……もしかして、見てた?」
エレナは狼狽して喉を詰まらせ、何も答えられずに立ち止まりました。それを見上げると、ジェシカは八重歯を覗かせて力なく笑います。
「フラれちゃった」
薪の爆ぜる一際大きな音が響き、チリチリと火花が跳ねました。
言葉を失うエレナから顔を背けて目を伏せたジェシカは、微笑みを口元に乗せたまま続けます。
「いいの、全部わかってたから。こうなるって。わかってた……わかってたのに」
「わからないわ。わたしは、何もわからない」
ようやく発したエレナの声は硬く、非難の色が滲んでいました。胸中で燻る行き場のない思いが捌け口を求め、しかしそれはもうこの場に残されていませんでした。
続く言葉を飲み込んで黙ったジェシカは尚も笑みを浮かべています。地面を見る目にも涙はありませんでした。
「応援してくれてたのに、ごめんね」
改めてエレナを見上げたジェシカが、苦笑します。
「どうしてエレナちゃんが泣くの」
自分のことのように、肩を落として呆然としたエレナの頬を一筋の涙が伝っていました。
エレナはそれを拭いもせずにへたり込み、砂の上に手を付きます。ジェシカは両膝をついて体を曲げ、エレナに正面から向き合いました。縋りついたのはエレナの方でした。
震えているエレナの手にジェシカの手が添えられます。しかし、項垂れて隠れたエレナの眼には「わからない」と呟いたときと同じ険しさが宿っています。エレナが涙を零したのはあの一度きりでした。
燃え続ける炎と浮かび続けるコミナライトの明かりが、二人の影を際立たせます。
こうして、彼女たちの舞台は幕を下ろしました。



