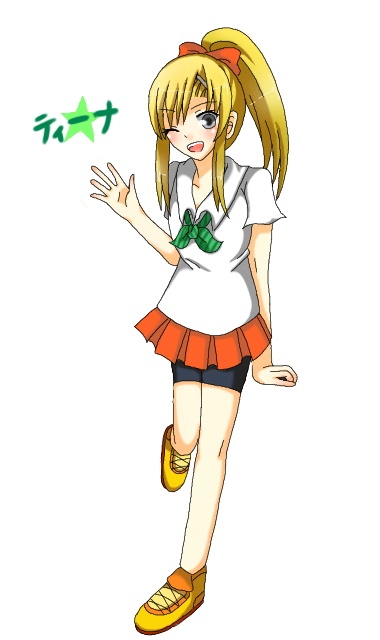93.トワイライト(1)
私が一人で講堂へ向かって、少し後にネフィリーも教室前から移動します。ミリーへの差し入れ用に、別のクラスの模擬店で冷たいジュースを買って戻ってきました。
ミリーの当番の時間は残り僅かになっています。しかし列はまだ続いていて、賑わいにつられて見物しているだけの人の数も増えていました。
先程まで私とネフィリーが立っていた、教室の中が見える位置は他の物見客で埋まっています。そうした場所はほとんど陣取られていました。出入口の前まで近付くこともできず、背伸びをして人々の隙間から顔を覗かせてみても、店内が変わらず盛況であるということしかわかりません。
ネフィリーは仕方なく人の山から遠ざかり、列の反対側の壁際でミリーが出てくるのを待ちました。
手に持ったジュースが徐々にぬるくなっていき、水滴がじっとりと手先を濡らします。列に並ぶ人たちの表情には、時間内に間に合うかという不安と焦り、そして若干の苛立ちが滲んでいました。
不意に、ひょっこりとミリーが扉から顔を出します。疲れを感じさせない涼しい顔をして、列の長さに目を丸くしました。
「わ~っ、まだこんなに! みんな、ワタシのために集まってくれたの? ……よしっ、それじゃあ、延長しちゃいまーす! ちゃんとみんなとお話できるまでずーっといるから、ご安心くださーい!」
「え」
ミリーはそう宣言します。人々が沸き上がりますが、ネフィリーだけは戸惑いを見せました。
ネフィリーを見つけたミリーは、バチッとウインクを向けて謝罪するように手を顔の前に立てると「先に行っててー!」と声を張り上げて戻っていきました。
「ほ、本気? ミリーちゃん……」
「あっ、みんなは普通に時間通り交代していいからね! お疲れ様! ワタシなら大丈夫!」
ミリーと、彼女を案じるクラスメイトの会話の一部が聞こえてきます。姿は見えないけれどその声は底抜けに明るく、対照的にクラスメイトたちの疲労が露わになっていました。
まだ興奮の冷めやらない廊下で一人、ネフィリーは困り顔です。ジュースを握る手元を見下ろします。
すると、横の人だかりの影から、はきはきとした少女の声が飛んできました。
「すみませーん、ちょっと通してくださいー」
後を追うようにもう一人、今度は少年の喚く声。
「おい、離せ! 離せっつってんだろ! この馬鹿力女! こっちは――」
「こっちは、シザーのクラスだよね?」
「てめっ、わかってんなら――」
ぐいぐいと人を掻き分けて教室へ向かってくるティーナと、彼女に腕を掴まれているシザーでした。意外にもティーナは力持ちで、多少辛そうにしてはいるものの、抵抗するシザーをここまで引っ張ってきています。
ティーナは列の先頭近くまで到達すると、急にシザーの腕を放しました。前触れのなかったこの動きにより、シザーは体勢を崩してよろめきます。
その一瞬で、ティーナが彼の背後へ鮮やかに回り込みました。
辺りの人々の視線が集中していますが、まるで動じません。シザーの肩を押さえつけて教室側へグイッと突き出すと、その状態のまま、喫茶店での接客時と同じ笑顔をして言いました。
「割り込んできてごめんなさい! 用事があって。わたしはシザーの友人なんですけど、シザーが店番サボったって話を聞いたので捕まえてきましたー」
「何のつもりだ、無茶苦茶しやがって……!」
シザーは諦めずにティーナを振り払おうとして身をよじっています。当番を代わって受付席についたばかりの女子生徒は困惑し、返事ができずにいるようです。
そこへミリーが、配膳の合間に少し離れたところから声をかけます。
「ティーナちゃん! わざわざ連れてきてくれたんだ!」
「えっ!?」
ミリーに名前を呼ばれて、ティーナは激しく動揺しました。
「嘘……! わ、わたしのこと覚えててくれたの!?」
「もちろんだよ! 久しぶりだね~!」
「う、うん! 久しぶり!」
「……俺を利用したわけか」
感激した様子で頬を紅潮させたティーナを一瞥し、シザーは苦々しく顔を歪めました。
ミリーは臆せずに笑みを向けて、シザーを教室内へ誘います。
「ここまで来ちゃったんだし、手伝ってくれないかな? まだこんなにお客さんがいるから、人手が増えると助かるなぁ」
「俺は――」
「拒否権なんてないでしょ」
険しい顔のまま言いかけたシザーの背中をティーナがはたきました。思い切りよく、加減も躊躇がありません。
「はい、皆さんどうぞ! こき使っていいからね、ミリーちゃん!」
「勝手に決めんな!」
シザーもまた、振り向きざまにティーナの肩に拳をぶつけます。
出入口前の状況を把握できていないキッチン担当の生徒が、出来立てのたこ焼きを掲げて奥からミリーを呼びました。ミリーは振り向き、仕事に戻っていきます。
呆気に取られ立ちすくんでいたネフィリーは、ハッとして二人の傍に駆け寄りました。ティーナの通った跡が残っていたため、するすると進めるようになっています。騒ぎの中心へおもむろに近付いていくネフィリーへ人々が注目しましたが、それを気にする素振りはありませんでした。
「シザー、待って。中に入るなら、これミリーに渡してきてくれる?」
虚を突かれた顔をして振り返ったシザーに、ネフィリーは安堵した笑みを浮かべて軽く首を傾げながらジュースを差し出します。
「……ここで言うことがそれかよ。意外と図太い性格してんな……」
「え?」
「……何でもねえよ」
シザーは低い声でぼそりと呟くと、それを受け取ったのでした。