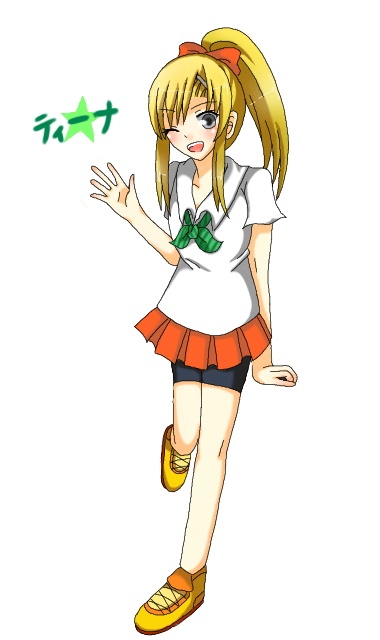94.トワイライト(2)
ネフィリーが去っていき、程なくしてティーナも、迷子捜しは任せてと言い残していなくなりました。
シザーはつかつかと中へ入ってミリーを呼び止め、預かったジュースをぶっきらぼうに突き出します。
「おい」
「ん?」
「ネフィリーから」
目を逸らしてそれだけ口にしたシザーに、ミリーは嬉しそうな微笑みを向けます。
「ありがと!」
「………」
「男子! シザー君確保しといて!」
「げ」
シザーの学校での振る舞いしか知らない生徒たちも、先程のティーナとの様子には少し警戒心が緩和されたのでしょう。シザーが踵を返そうとしたときには既に、周囲はオレンジ色のTシャツに取り囲まれていました。
必要なエプロンも三角巾も持ってきていない、と言って逃げようとしましたが、ちょうど当番を終えたクラスメイトがどちらも貸してくれるようです。成すすべなく、あっという間に、彼はキッチンに立たされることになりました。
とめどなく入ってくる注文と鉄板から立ち込める煙は、みるみるうちにシザーの思考を塗り潰していきます。元より彼には面倒見の良いところがありましたので、いざ中で手を動かし始めてしまえば止まらなかったのでしょう。あるいは、やけくそ気味でやり場のない苛立ちをぶつけていただけなのかもしれませんけれど。
使っている鉄板は海外からの輸入品で、複数の丸い窪みが並んでいるたこ焼き専用の物です。竹串で器用にタネをひっくり返していくシザーの手捌きにクラスメイトが群がってきます。
「シザー、うまいな!?」
「うっせえ」
シザーは手を止めずにしかめ面で一言だけ言い捨てました。彼の手元で次々に焼き上がっていくたこ焼きは、くるくると楽しげに跳ねるようでした。
「オラッ、二人前!」
「一番テーブルでーす!」
教卓のカウンターの上に、完成したたこ焼きのパックを叩きつけるように出します。ミリーはすぐに受け取って客席へ向かいました。
いつでも来客たちの視線の中心にはミリーがいて、いかなる時も決して笑顔を絶やしません。その軽やかな足取りはダンスのステップを踏むようです。顔色一つ変えないミリーに、シザーは人知れず驚嘆を覚えていました。
袖口で顔の汗を拭いながら彼女の背を追っていたシザーの視界に、出入口から中を覗いていく通行人たちの姿が映ります。ピークを過ぎて、少しではありますが人の切れ目ができているようです。
馴染みのあるやり取りが聞こえてきました。
「あれ!? まだやってんのか! すげー人気じゃん!」
「ぼくは別に興味ないし。セコいやり口」
「うわ、冷めてんなー。でもこれは仕方なくね?」
「人の名前一つ出すだけで、お前みたいなのが大勢釣れて楽だろうからな」
「ばっ、言うなって! あ、いや違、違う! 俺は違うぜ!?」
「時間把握してるくせに」
「だからちげーんだって!」
待機列の向かい側からレルズとスティンヴが来ています。レルズは黒いローブから黄色と緑のクラスTシャツに着替えていますが、スティンヴは変わらず執事の格好でサングラスも外したままでした。今尚続く長蛇の列と満席の教室を見てレルズは声を上げ、スティンヴは唇を尖らせて溜息を吐きます。
入口の前を通る二人と、シザーの視線が重なりました。
レルズが驚いた目になって立ち止まります。
学園祭をどう過ごすつもりなのか、シザーは二人には話していました。友人として二人を信頼し、気を許しているが故のことです。
レルズもスティンヴも、彼の考えと行動に異を唱えてはいません。しかし、少なくともレルズの本心が他にあったことは、今朝エレナに指摘されていた様子から明らかです。
このとき、二人はそれぞれ何を思ったのでしょう。
互いに呼びかけはしませんでした。ただ、大きく開いたレルズの瞳には隠し切れない喜びの色が滲んでいくのが見て取れて、シザーはそれを逸らすことができませんでした。
スティンヴは少し先に行ったところで足を止め、レルズが動き出すのを黙って待っています。
入口前で足を止めているレルズの元に、帰っていく客の見送りをしたばかりのミリーが近寄ってきました。
「いらっしゃいませ、いかがですかっ? もうそろそろラストオーダーだけど、今ならまだ間に合うよ!」
「だ、わあっ!? えっと俺はその、えーっと、ス、スティンヴが早くしろってうるせーんで! 失礼するっす! 頑張ってください!」
「あ?」
都合よく名前を使われ、スティンヴが顔をしかめています。
走り去りかけたレルズでしたが、すぐに何かを思い出したように引き返してきました。ミリーは首を傾げます。
「どしたの?」
「あ、あーっと、その! こんなに沢山の人が集まってんのって、やっぱすげーことだと思うっす! 誰にでもできることじゃねーっす! だ、だから……さすがみんなのアイドルっすね! いや、違うな、そうじゃなくて……俺何言ってんすかね!?」
アセアセとしどろもどろになりながら、レルズは必死に言葉を探しています。
それは言葉数に対してほとんど意味を成していませんでしたが、ミリーは優しい微笑みを向けました。
忙しなく腕を振っていた体勢のまま、レルズがピタリと固まります。
すっと息を吸い込んで少しだけ落ち着くと、腕を下ろし姿勢を正して晴れ晴れとした笑みを作り、ミリーと正面から向き合いました。
「……やっぱ、何でもねっす。じゃ、じゃあ、今度こそ俺はこれで。邪魔してすんませんっした」
「ううん。そんなことないよ。ありがとう!」
駆けていったレルズはスティンヴと合流し、頭の後ろを軽く平手で叩かれます。その背中を、ミリーは穏やかな目で見送っていました。
「ただ今をもちまして、スズライト魔法学校の学園祭は終了です。この後は講堂でエンディングセレモニーが行われます。全校生徒、及びお時間のある方は、講堂へお集まりください。本日はご来場ありがとうございました」
模擬店の営業の終わりを告げるアナウンスが流れて、店内では拍手が起こります。
「みんなー! 今日は本当に、ありがとうございましたー!」
客席を見渡せる教室の中央に立ったミリーが大きく手を振り、音楽ライブさながらの言葉と仕草を最後に残すと、一層の盛り上がりを見せました。休憩どころかほとんど息つく間もなく数時間の接客を続けたにも関わらず、ついに彼女の笑顔が曇ることは一度もありませんでした。
ミリーは教室中をぐるりと見ながら、全員に向かって話しかけます。
「今の放送でもあったけど、この後も時間があれば是非講堂にも来てほしいです! ね? ワタシからみんなへ、お願い!」
ミリーの言葉で来場者たちは一様に席を立ち、一直線に廊下へ出ていきました。扉の外から中を覗いていた人々やクラスメイトたちも同様で、真っ直ぐに講堂へ向かいます。
ごった返していた教室周りはあっという間に彼女を残して空になり、一人でキッチンの隅にいたシザーはその撤収の早さに目を白黒させました。
他のクラスからも続々と、講堂の方向へ人が流れています。次第にその人数は減り、廊下から人の気配がしなくなりました。斜めに傾いた日差しが雲で遮られ、校舎内が仄かに薄暗くなります。
シザーは借り物のエプロンと三角巾を外し、奥の角にまとめて置いてあるクラスメイトの荷物の山の上へ適当に投げ込みました。
フロア側へ出て、一人で教室に残って受付席の裏にしゃがみ込んでいるミリーを不思議に思います。
「……行かねえの?」
「さすがにちょっと疲れちゃった。一休みしてから行くよ」
そう言いながらもまだ余裕のありそうな笑みを見せたミリーの両手には、空色のリボンを結ばれた紙袋がありました。光沢があるサテン生地のリボンは色鮮やかで、可愛らしい印象です。
キッチン側からは人や物の影になって見えていませんでしたが、近付いてみると机の下には他にもプレゼントの袋や箱があります。全て、来客たちから彼女へ渡された差し入れの品々でした。
その整理をしながら、シザーを見上げて口を開きます。
「そっちこそ、またサボっちゃダメだよ?」
「そうそう、ミリーちゃんの言う通り」
廊下から顔を覗かせたのは、ティーナでした。ポニーテールを揺らしてひらりと片手を振る笑顔の彼女に対し、シザーはあからさまに嫌な顔をして舌打ちします。
「何しに戻って来やがった」
「普通に通りがかっただけなんですけど」
「まあまあ」
火花を散らす二人の間にはミリーが割って入って宥めました。
ティーナはコロッと態度を一転させ、ミリーに向き直ります。
「お疲れ様、ミリーちゃん! 大盛況だったね! この後の投票も一位で決まりじゃない?」
「んー、どうだろ? 確かにみんないっぱい来てくれたけど、売上ランキングじゃないからなぁ。午前中はガラガラだったみたいだし」
「みんなミリーちゃんに会いたくて、時間まで待ってたんだよ。実際わたしもそうしてたからね」
「嬉しいな」
ミリーは紙袋を置いて立ち上がると、少々気恥ずかしそうにはにかみました。
反対の壁際へ歩いていって、窓を大きく開け放ちます。教室の中にこもっていたソースの香りが飛び、代わりに爽やかで涼しい風が吹き込んできました。その心地よい風を浴びて伸びをします。
「ワタシ、ちゃんとやれてたかな?」
「やりすぎなくらいだろ。予定の倍の時間、ずっと動きっぱでよ。こっちは半分の時間でもヘトヘトだってのに、よくバテなかったな。すげえよ」
「みんなが喜んでくれるからだよ。張り切っちゃった! でもね、ワタシは『本物』の人の真似をしてるだけなんだ。『本物』はもっと凄い。ワタシはまだまだ」
「んなこたねーよ」
「えへへ、ありがと。それなら良かった」
ミリーは振り返って、後ろ手を組んで窓枠に浅く寄り掛かりました。髪を優雅な仕草で押さえ、目を閉じます。
背中に陽を浴びたシャツの橙色はまるで夕陽のようです。
風に乗って、ふわりと新緑の香りが漂ってきました。
「ティーナちゃんはこの後の式も見ていく?」
「うん、そのつもりだよ。ここまで残ったら行くでしょー」
「そっか!」
「あ、そうだシザー。迷子の子のことなんだけど……」
「えっ?」
ここまでずっと笑顔でいたミリーが、きょとんと目を開いて尋ね返します。
「迷子がいたの?」
「わたしはシザーがそう言ってるのを聞いただけだけど。眼鏡の男の子だって」
「んー……わかんないかも。ワタシにも話してくれたらよかったのに」
「本人は迷子じゃないっつって、全然平気そうだったがな」
「運営委員の人たちに聞いたら、見回り中もそんな子は見てないし何の連絡も無いって。子供が一人でいたら目立つはずだし、大丈夫ってことだと思う。その子を捜して困ってる人もいなかったよ」
「そうか。人騒がせなガキだ」
悪態をつきながらも、その声色と表情に刺々しさはありません。シザーが納得を見せる一方、話を聞いたミリーは首を捻ったままでした。
その少年に会ったと言うのは、最後までシザー一人だけだったようです。ですが、他に何の情報も得られずとも、ティーナは彼の証言を一切疑っていませんでした。口喧嘩ばかりしていたようだったけれど、シザーがそのような嘘を吐く人ではないとは理解していたのでしょう。
そろそろ講堂へ行かないか、とティーナが二人を促します。
しかし、ミリーは眉を下げて首を振りました。
「もう少し休憩してからでいい? ティーナちゃんは先にシザーと一緒に行ってて。それで、抜け出したりしないように見ててくれる?」
「な、おい、ミリー?」
「わかった、ミリーちゃんの頼みなら!」
ティーナがシザーの後ろに回って、その背中を押します。シザーは踵で彼女の足を蹴りつけました。
遠ざかっていく口論の声と足音。
窓辺で逆光に包まれたミリーは、開いた扉の先を優しい顔で見つめていました。