74.もうすぐ
静かな、授業中の教室。チョークが黒板を叩く硬い音と、鉛筆が紙をこするひそやかな音が交わり合っています。
地学の男性教諭が黒板に板書をしていて、生徒たちはそれを黙々とノートに写していました。シザーだけは相変わらず、机の上に一切教材を置かず先生の後ろ姿を凝視していましたけれど。
ミリーは、広げたノートと教科書の間に薄紅色の可愛らしい便箋を挟んで、ノートを取るフリをしながら手紙を書いていました。何行にも及ぶそれを書き終えると中身が見えないように小さく折り、隣の席のクラスメイトに耳打ちしながらそっと渡します。手紙は先生の目を盗んで、斜め前方に離れているエレナの席まで辿り着きました。
手紙を読んだエレナは、ペンケースからウサギ柄のメモ帳を取り出して一枚切り離すと、ササッと返事を書いて二つ折りにします。
ミリーの手元に、先生に咎められることなく無事に手紙が返ってきました。中を開いて目を通し、顔を上げると、振り向いていたエレナと目が合います。
机の下でこっそりと拳を握って、柔らかく微笑むエレナ。
ミリーは頷き、同じ仕草を返します。
そんな二人のやり取りを、後方の席からルベリーがじっと見守っていました。
各クラスの準備は大詰めを迎えていました。どこの教室も、段ボールにペンで色を塗った看板、小物、飾りなどが壁際やロッカーの上に並んでいます。
この学園祭準備期間中に、ミリーたちのクラスではひと騒ぎありましたけれど、準備の進行と並行してそのわだかまりも解けつつあったようでした。
「使ってない色ペンまだある? 取ってきてくれね?」
「何色?」
「色っつーかケースごと全部――」
「……こ、これ」
「うおっ、早。いつの間に。ああルベリーさんか、ありがと」
「……うん。どういたしまして……」
ガヤガヤとした教室内を、ルベリーは一人落ち着きなく往復しています。追加のダンボールや画用紙、粘着テープに接着剤、のりやハサミといった数々の道具をあちこちのグループに持って行ったり、作業に手を貸したりしているようです。
彼女は他者の心の声が聞こえてくるという「能力」をうまく活用し、皆が要求を口に出す前に先読みして動いていたのでした。
先回りをされた同級生たちは最初こそ困惑気味でありましたが、次第に気にならなくなっていったようです。ルベリーの表情はまだ少し硬く、目を合わせられる時間も短かったようですけれど、態度を軟化させ快く受け答えをしてくれるクラスメイトが何人もいました。そうして、ルベリーの緊張も徐々にほぐれていきました。
元より、皆の仲が良い和やかなクラスなのです。たった一度のすれ違いが生じた程度で全てが崩れてしまうほど、脆い絆ではありませんでした。
それでも、皆が同じ気持ちを抱いてこの場にいるのではないことをルベリーは知っています。あくまでも許されたのは自分ではないことも、全員に心から歓迎されているわけではないこともわかっています。だからこそ臆せず、怯まず、級友たちの元に歩み寄り続けていたのでした。そんなルベリーに向かって、表立って意地悪をする人はいませんでした。
「ねえ見て、これどうかしら!」
横からエレナたちのグループがルベリーを呼びます。
エレナとリーンが二人がかりで広げた大きな画用紙の中央に、クラスで出店するたこ焼き屋の店名がカラフルなペンで書いてありました。多様なタッチの、可愛らしい顔をしたタコのイラストも散りばめられています。
笑顔の彼女たちに、安堵したような微笑みを浮かべながら近付いていきました。
「エレナさんが……描いたんですか?」
「いいえ、描いたのはほとんどみんなよ」
エレナは後ろに振り向くと、並べた机の前に座った三人の友人に笑いかけます。彼女たちも笑顔を見せました。
「わたしはこの隅っこのタコ二匹だけ」
「……可愛い。上手です」
軽く腰を折り、イラストに顔を近付けます。
その途中でふと、何かに気が付いたように眉が上がって、瞳が揺れました。
少々思い詰めたような様子で唇を結んだけれど、膝に乗せた手にぐっと力を込め、二人の奥で座っている女子生徒たちの方へ顔を上げます。
「あの。……私、この喋り方も、呼び方も……これから頑張って直していくから」
エレナとリーンが並んで目を丸くすると、後方でボーイッシュなショートカットの一人がガタンと立ち上がって声を上げました。
「ご、ごめん! そんなつもりじゃないんだ! 私はただ、ちょっとよそよそしいって思っちゃっただけで、それが駄目だとか嫌だとかっていう意味じゃないよ! 無理に直してほしいわけでも……だから……!」
心を読まれ慌てふためく彼女につられてルベリーもあたふたしながら、ブンブンと首を横に振ります。
「あ、いえっ、ちが、違うんです! その……ええと……私もそう思ってるから。人に言われたから……そう思われてるからじゃなくて。……私が、変わりたくて。慣れるのはまだ時間がかかるかもしれないけど……」
「ルベリーったらそんなこと考えてくれてたのね! わたしたちはいつだってウェルカムよ!」
二人の間の空気を吹き飛ばすように、エレナの声が明るく飛び跳ねました。
「ぅ……えと……」
「コラ、困ってるでしょーが。ルベリーのペース考えなよ?」
苦笑交じりでリーンが軽く抑えましたが、エレナは笑みを堪えられません。
「だって嬉しいんだもの! リーンだってそうでしょう?」
「あ、あたしは」
パっと振り返ったエレナに、リーンはたじろぎます。
惑った視線がルベリーとぶつかり、その琥珀色の瞳が揺れました。リーンは目を逸らしてそっぽを向くと、照れ隠しのように唇を尖らせます。
「……まあ、何だっていいわよ、別に。はっきりしてよね」
「う、うん……ごめ、あ、いえ……その、ありがとう」
「何でそこでお礼なのよ。変なの」
言いながら、リーンの口元は少し綻びました。
ありがとうと言い直したとき、ルベリーはどんな気持ちだったのでしょう。
リーンの心がどのように聞こえていたのかは、彼女たちしか知りません。
けれど、あの時ルベリーもリーンも優しい表情をしていたと、すぐ傍で二人を見ていたエレナは感じたそうでした。
掃除の後の放課後、学園祭の日のミリーの都合を聞くために私とネフィリーが向かうと、多くの生徒はまだ下校せずに残って談笑していました。ミリーは窓際の方でルベリーやエレナと一緒にいます。皆の手には配られたばかりのパンフレットがあり、こちらでも私たちのクラスと同様に盛り上がっていたようです。
私はミリーと共に二人のことも呼んで、それぞれの学園祭当日の日程を尋ねました。
「シフト? そっか、シフト……んっと、ワタシは午前中なら空いてる! お昼から先は、その、ちょっと確認しないと」
都合を尋ねた時、ミリーはきちんと把握していなかったのか、どこか歯切れの悪い様子でした。一度エレナと無言で顔を見合わせた後、「とりあえず午前中は本当に大丈夫だから!」とだけ念を押します。
エレナは実行委員の仕事があり、午前は来場者受付、午後はステージの司会進行役を務めるため、私たちと出店を見て回るのは難しいとのことでした。
「そっか。でも、午後のステージはクラスの友達が出るから見に行くよ! そこにエレナもいるんだね?」
「そうね、ちょっと緊張しちゃうわ」
この頃の実行委員は毎日忙しそうでしたが、それ以上に充実していたのでしょう。傍目にはその苦労を感じさせないほどエレナは楽しそうな笑顔で、生き生きとしていました。
ルベリーはまだ、どうするのか決めかねているそうでした。楽しみな気持ちはあるものの、やはり自身の「能力」を思うと簡単には考えられず、不安も大きいようです。遠慮がちに目を伏せます。
「こ、この前のことがあってから……何だか少し、聞こえる音は遠くなった気がする……。けど、ずっと心の声が聞こえてるのは変わらないから、ごめ……ううん、ええと、でも……私なんかのこと誘ってくれて、嬉しかった……です」
楽しめるといいね、と声をかけると微笑みを浮かべ、こくりと淑やかに頷きました。
そうして、私とネフィリーとミリーとの三人で行動することで話はまとまったのです。
私はこの後ティーナへ会いに喫茶店へ向かったのですが、どうやら皆も真っ直ぐに帰宅はしなかった模様でした。ネフィリーとルベリーはそれぞれのクラスに残り、出店の準備の続きを。エレナは講堂で、ステージ発表のリハーサルの立ち合いに。
ミリーはというと、何故かエレナと共に講堂へ行くようでした。疑問に思って訳を尋ねると、ミリーではなくエレナが答えます。
「ミリーは去年のステージ裏のこと知ってるから、参考にしたくって」
そう言った直後にエレナが無言で目配せをし、それを受けたルベリーが困ったように顔を背けた様子だったのが、少々気になりました。






73.嘘を嫌ったウソツキの告白
一日の営業時間を終えて照明を落とした喫茶店は、その内装と相まって静まり返る夜の森のようでした。レジとカウンターの傍だけに明かりが灯っており、その二ヵ所で二人の人影が最後の後片付けをしています。一人はパフィーナさんで、もう一人はティーナでした。
伝票の束を引き出しにしまってレジ周りの仕事を締めたパフィーナさんは、その場からティーナに呼びかけます。
「時間はある? そっちの片付けが終わったらそこの椅子で待っていて。今日のケーキの残り、食べていってちょうだい」
「やった~、いただきます!」
カウンター裏の流しを清掃していたティーナは歓声を上げました。周辺の仕事を全て終えると、ポニーテールを揺らして軽やかな足取りで客席側に回り込みストンと座ります。
パフィーナさんが厨房から持ってきた銀色のバットには、ケーキの切れ端がぽつぽつと数種類乗っていました。その中から一つ、少し焦げ目が付いたチーズケーキの角をちょうどいいサイズの小さなお皿に移し、デザートフォークを並べます。
「今週末はスズライトの学園祭に行くから、お休みなのよね?」
「そうです、お願いしまーす」
差し出されたお皿にティーナはすぐに手を伸ばし、ケーキを一口で頬張りながら間延びした声で返事をしました。
「また今年もミリーちゃん探してくるんですよ!」
「楽しそうでいいわね。ルミナさんに案内してもらうの?」
「いえ、それはルミナの他の友達に気を遣わせちゃいそうなので。クラスの場所と店番の時間は教えてもらったので、そこだけ会いに行ってきます」
「そうなの」
パフィーナさんは頬杖をつき、軽く体を傾けます。
ティーナの顔を覗き込むように、うっすらと微笑みながら瞳を妖しく光らせて。
「貴女はルミナさんのことが嫌いなのだと思っていたわ」
甘味に目を細めていたティーナは、その目を開きゴクンと喉を鳴らしました。デザートフォークの先端が揺れて皿にぶつかり、カツンと小さな金属音を立てます。
「彼女、ここ最近よく来ていたけれど今日までずっと避けていたでしょう? でも平気よ、あの娘自身も誰も気が付いてはいないから」
「いや、あのー、わたしまだ何も言ってないんですけど」
「違っていたかしら?」
「違いますよ、どうしてですか?」
ティーナはフォークを置いて苦笑しました。
「どう、ということもないのだけれど。何となくね」
「えぇ……」
ケロリと答えるパフィーナさんに本気で呆れた様子で、への字に口元を歪めます。
「でも、そうね。強いて理由を言うとしたら、貴女が幸せそうではなかったからかしら」
「はい?」
パフィーナさんが続けた言葉はティーナの意表を突き、間抜けな声が漏れました。
「自分にとっての幸せとは大切な人の幸せだと、面接の日、私の質問に答えてくれたわね。覚えている?」
「……そうでしたね。いきなり変なこと聞く人だな、ここで働いて大丈夫かなって思いました」
「正直者だこと。私は好きよ、貴女のそういう性格」
「………」
そう評されたとき、ティーナはかすかに顔をしかめました。
パフィーナさんは変わらずに薄く微笑んでいます。
「ティーナさんにとっての幸せは、ルミナさんに阻まれる可能性があったのではなくて?」
「まさか。ルミナがそんなことするわけないですよ」
「ええ、あの娘も誰も悪意を持っていないわね。だからこそ複雑で、悩ましいのよ」
「何の話ですか」
「さあ、何の話だと思う?」
進まない問答の中、彼女の前へ無言でもう一皿、今度はブラウニーとバニラ風味のロールケーキの端が提供されました。
それはさながら尋問されているかのようで。
ティーナはケーキに手を出せず、黙って見下ろしました。手のひらに汗が滲みます。
険しく眉を寄せつつも笑顔を作るティーナと対照的に、パフィーナさんは涼しい顔で平然としていました。
「……お客さんの誰かから、何か聞きました? 何が目的ですか?」
「目的も何も、私は単に貴女の話が聞きたいだけなのだけれど」
「今の店長、悪魔みたいですよ」
「まあ。悪魔に会ったことがあって?」
「いや無いですけど! 例えです!」
そう声を上げられても余裕そうに、口元に手を添えてクスクスと笑います。
ティーナは溜息を一つつきました。
「本当に嫌いじゃないです。ルミナは、わたしの親友にとっても友達なんですから」
「友達の友達とは仲良くしなければならない、なんてルール、世の中にはなくてよ? 無理に仲のいいフリをする必要はないの」
「だから無理もしてませんって。素直で優しくて……ルミナのそういうところって、わたしの親友にも少し似てるんです。あの子もルミナを気に入ってます。だから、嫌いになれるわけがないです」
「そう。でも、貴女の親友さんのことは貴女から聞いた話でしか知らないけれど、それって本心なのかしらね?」
パフィーナさんは意地悪な口ぶりで言いました。芝居染みた所作で首を傾げて、仄暗い天井へ目を動かします。
「人間は平気で嘘を吐くでしょう? けど、嘘を生むのは悪意だけではなく、善意のときだってあるわよね? 無理をしているのは優しい優しい彼女、という可能性も考えられるのではない?」
「それは……」
ティーナは言い返そうとしたけれど、言葉が続きませんでした。瞳が揺れて、俯きます。目元に暗い影が落ちました。
反面、パフィーナさんは尚も楽しげで、自分のペースを崩しません。ティーナの不安そうな様子はまるで目に映っていないようです。
「なんてね」
縦に巻いた髪を揺らし、くるりとパフィーナさんが向き直ります。
「他人の気持ちを憶測で語るのは不毛だわ」
「……そうですよ」
「と言っても、貴女にはその意味も権利もあるのよ」
「え……?」
「ティーナさんは赤の他人ではないのだから」
不審がるティーナの目の奥を、ゼリーのような桃色の瞳が真っ直ぐに見つめました。
「お友達が心配になるのは当たり前。貴女の幸せの形を思えば尚更よ。だからその結果、別のお友達に悪い感情を抱くことになったのだとしても責められることはない。私は責めない。むしろ、そうやって思い悩む貴女は可愛らしくって親しみを覚えるわね」
ニコリと屈託なく笑う顔は、一転してティーナを安心させるような表情でした。
元より、動揺の原因もまた彼女ではあったのですけれど。
ティーナの眉間に寄っていた皺が消えて、呆れた苦笑いが戻ってきます。力んでいた手と肩から力が抜けました。
「悪魔みたいって言ってごめんなさい」
「いいのよ」
「悪魔じゃなくて、魔女の間違いでした」
「酷くなっていない?」
「そうですか?」
軽口を言って笑いながらもう一度フォークを手に取り、ケーキの欠片を更に半分に切って口に運びます。甘い味わいが儚く溶けていきました。
「それにしても、ティーナさんは本当にその親友さんのことが大好きね。何かきっかけでもあるのかしら?」
「……面白い話じゃないと思いますよ?」
「人と話すのはどんな話題だって面白いわよ」
「いやいや……ああ、店長は本気でそういう人でしたね」
ティーナは最後の一欠片を飲み込み、フォークを置きます。パフィーナさんはそれを引き取って、バットと合わせてサッと洗い流しました。
蛇口から流れ落ちる水の音が静かな店内に響きます。
「正直者は馬鹿を見る、って言うじゃないですか」
おもむろに切り出したティーナにパフィーナさんは一瞬だけ僅かに目を見張り、水を止めました。
「そんな考えもあるかしら」
「母がよく言ってました。でも、わたしはその言葉が嫌いでした。別に、親のことまで嫌いというわけではないですけど、嫌だなって……でも、世の中はきっとそうなんだろうとも思ってて。……諦めてたんです」
「そう……きっとご両親にも、ご両親の理由があるのでしょうね。人の家庭の教育方針に口は出せないけれど」
「店長も……正直に生きるのは損するだけだって思います?」
上目遣いで問うティーナの視線を、パフィーナさんはすいっと避けます。
「さて、どうかしら。難しい問いだわ。この答え方によっては、私の好感度が下がってしまいかねないものね。困ったわ」
「何ですかそれ、答える気が無いだけですよね。嘘吐きだ」
ごまかそうとしたようでしたが、ティーナは流されませんでした。口を尖らせて指摘すると、パフィーナさんの目線が戻ってきます。けれど結局、先の問いに答えることはありませんでした。
「ふふ。私の一言などに左右されてほしくないのよ。そのようなことは自分の頭で考えなくては。人の意見を参考にするくらいはいいけれど、もう自分の答えを持っているティーナさんには必要ないでしょう?」
「……まだ少し、自信ないですけどね」
「貴女は若いのだから、それくらいがちょうどいいわ」
店長もそんな年じゃないでしょう、とティーナは内心思ったけれど、口にはしません。また笑顔ではぐらかそうとすることが読めていました。
ティーナは、店仕舞い後の店内に最後まで残ることがよくありました。その度に、パフィーナさんとはこうして様々な話をしたそうです。
しかしその話題はほとんどティーナにまつわることであって、パフィーナさん自身の話は滅多にありませんでした。人の話を聞くのが好きだと公言するけれど、正しくは自分の話をしたくないのだろうというのがティーナの見解です。
それならばそれでいいと、ティーナは彼女を聞き手として利用させてもらっていたのでした。パフィーナさんは自分から話をしない代わりに、人の話は何でも受け止めてくれます。いつでも、誰相手でも、どんな話題でも、お客さんの話に耳を傾け続ける日頃の様子からそう捉えていました。
「わたしの親友は、人の嘘を見分けたり人の裏を読んだりが苦手で、真っ直ぐな……本当の正直者です。あの子の純粋さがわたしにはとっても眩しかった。世の中は母の言う通りかもしれないけど、あの子が悲しむのは納得できないし許せません」
それは、気安く吐露するのは憚られる感情。
それでいて、一人で抱え続けるには重い感情。
その重みを外に吐き出すことで、心をほぐしていきます。胸の底に渦巻く淀みを溶かしていきます。ほとんど独り言のつもりであり、パフィーナさんが途中で口を挟むこともありませんでした。
「やりたいこと、こうなりたいって思えることが見つかったのは、全部あの子がいたから。両親の言葉を黙って聞くだけだったわたしが初めてそれに反発して、自分の意見を持てたんです」
本心を打ち明けるティーナの顔は穏やかで、瞳には温かな明かりが灯っています。その明かりごと、瞼を閉じました。
「わたしの中にあるのはこれだけですよ。この気持ちがなくなったら空っぽです。ほら、面白くない」
「そんなことはなくてよ。そう、だから貴女は大切な彼女の幸福を願うのね。素敵なことだわ。きっと彼女も、ティーナさんに救われているはずよ」
「救い、ですか。ほんと何を聞いたんですか……」
目を開けると、パフィーナさんの柔らかい眼差しがティーナに向けられていました。魔女のようと称された先程までとは打って変わって、我が子を見守る母親のようでした。
「ただ、一つ私から忠告するとすれば、その想いも行き過ぎないように……かしら。人の幸福はその人自身にしか決められないのだから。ティーナさんが彼女の幸せだと考えることが、はたして本当に彼女にとっての幸せかどうかはわからないもの」
「はい、それはもう、本当にそうですね」
「ふふ……。やはり、貴女は正直者よ」
「この話の流れでそれを言いますか」
ティーナは少し気恥ずかしそうに眉を下げながら、笑みを零します。
自分に正直でいたかった。
素直に生きられる人でありたかった。
彼女が私に話してくれたことがあります。
この日から何年も過ぎた、ある時のことです。
弱い自分は卑怯で醜い嘘吐きに成り果ててしまったけれど……と、ティーナは自らを評していました。
そんな自分と違う『あの子』、すなわちメアリーはとても綺麗で、強くて、同時に脆くもあり、その光が翳ることがないように守りたいのだと。どれだけの年月が経っても変わらずに、誰よりも大事な人なのだと。ティーナはそう語りました。
その想いはいつでも彼女の中に貫かれていたのでしょう。
出会ったばかりの頃に私へ向けていた本当の心も、打ち明けてくれたことがありました。
今となっては、それは胸中に秘めたままでもよかったはずなのですけれど。そんな隠し事を抱えたまま私との付き合いを続けたくないのだと言って、包み隠さずに当時の思いをぶつけてくれました。
その真っ直ぐさを正直者と呼ばずして何と呼ぶのでしょう。
一度も嘘に頼らず生きられる人などいません。
ティーナは自分を嘘吐きだと言ったけれど、そう思っているのはきっとティーナ自身だけなのでした。
彼女の物語を優しく噛み締めるように、パフィーナさんが呟きます。
「そんなにも愛する人がいるというのは、羨ましいわ」
「それはつまり、恋人いませんってことですか?」
「あら……今の言い方だと、そういうことになってしまうわね。口が滑ったわ」
気が緩んだのでしょうか。珍しく、パフィーナさんが私生活を垣間見せました。その隙をつつくように、すかさずティーナは反撃を始めます。
「でもちょっとそんな気がしてました。店長はどんな人でも好きだって言いますけど、それって全員どうでもいいってことでしょう?」
「ちょっと? 酷い言われようね。貴女は正直というより、遠慮がないのかしら」
「店長には遠慮する必要ないですから。どんな話題でも面白いって言いましたもんね?」
得意げな顔で言い返すティーナに見上げられ、パフィーナさんは虚を突かれたように目を丸くしました。
それもほんの数秒間のこと。すぐに、ふわりと含みのある笑みを浮かべます。
店内の暗がりに浮かび上がり、僅かに発光しているように錯覚する双眸は桃色。
「そうね。面白いわよ、人間は」
一瞬だけ、艶やかに輝きを放ったかのようでした。
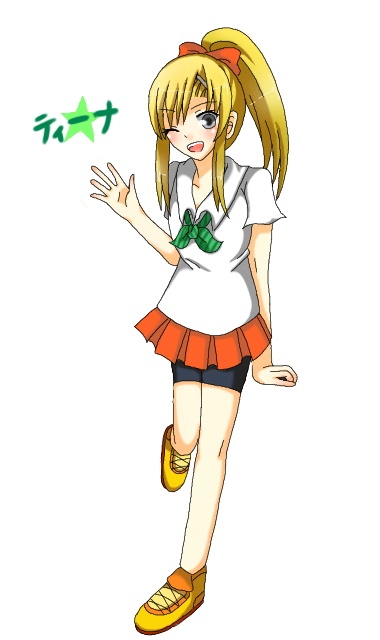

72.隠し事
私は一人、学校から真っ直ぐに商店街へと向かっていました。喫茶店でティーナに会い、メアリーへ手紙の返事を伝えたと報告するためです。
ティーナとは、彼女のバイト先へ行くこと以外にコンタクトを取る手段がありません。これまでも何度か会いに行ってはいたのですけれど、休みの日であったり忙しそうであったりして話せなかった日が続いていました。
手元にパンフレットがあることですし、学園祭の話もしたいと想像します。そうした理由もあってキラを誘っていたのですけれど、断られてしまいました。
「あの手紙の返事のこと、ティーナに伝えに行こうよ。この後一緒に行こう?」
「……オレはいい。悪いがルミナ一人で行ってくれ」
掃除の時間に、手を動かしながら喋ります。周囲には他に人がいるので、互いに声量は抑えめです。メアリーとネビュラの名やスズライト家といった直接的な言葉も口にしないよう気を配ります。
スズライト家は、王様と名前を並べることもできるほどの名家です。彼女たちと面識があるということは、私たちの間だけの秘密にしていました。
「ティーナはオレを良く思ってないからな」
「えっ、そうなの? 何で? 全然そんな風には見えなかったけど」
「良く思われる理由がない。下手をすると嫌われてるくらいだ。……だから、お前も、気を付ける方がいいと思う」
その言葉の意味がよく理解できず、聞き返します。
「……いや、さすがに言い過ぎたか。今のは忘れろ。とにかくオレは行かないから」
キラはそう言ってすぐに取り消しはしたけれど、それきり私に背を向けて話をやめてしまいました。
商店街の出入口のアーチの前で箒から降りて、喫茶店まで歩いていきます。夏季休暇の時期を過ぎたからでしょうか、以前訪れた時と比べて通りの賑わいは大人しくなっているように感じました。
今日こそ話せるといいな、と願いながら黄金色のドアノブを捻ります。出迎えの女性店員に奥のカウンター席へ通されながら店内を見渡したところ、席はおよそ半数が埋まっていますが一通りオーダーは済んでいる様子です。肝心のティーナは見当たりません。
「この頃、よく来てくれるわね?」
席につくと、パフィーナさんがにこやかに話しかけてきました。艶やかな巻き髪とゼリーのような瞳の桃色は年齢というものを感じさせず、不思議な雰囲気を醸しています。
彼女やティーナがよく話しかけてくれるので、この喫茶店は一人で入ってもあまり寂しい気持ちになりません。この日カウンター席の方は空いていて、先客が店を出たことで私とパフィーナさんは一対一になりました。
「美味しくって気に入っちゃいました。それと、ティーナにお話したいことがあって。今日はいますか?」
「あら、運が良かったじゃない。あの娘ならもうじき来るわよ。待ってる間、何にする?」
お小遣いに余裕があるとは言えませんので、店長でもあるパフィーナさんの特製ドリンク一品だけを頼んでティーナを待ちます。従業員用の出入り口からティーナが姿を現したのは、時計の分針が一周する少し前くらいでした。
その制服の、胸元の黒いリボンタイの結び目が通常よりも大きく膨れているように見えて違和感を覚えます。
目を凝らすと、黒く渦巻いていました。
私と目が合った時に、一際強く脈打ったような気がしました。
「ルミナ! いらっしゃい!」
それを微塵も感じさせないほど、ティーナはいつも通りの明るい笑顔で接してきます。
しかし自分の目を何度疑っても、間近で見るほどにその存在感は確かなものとなりました。握りこぶしより一回り小さいくらいの渦が、確かにありました。
「貴女と話がしたいそうよ?」
「あ、前頼んだ伝言のことなら聞いてるよ。ちゃんと手紙の返事もらったって。ありがと!」
「そ……そっか。あの、ティーナは、今何か気になってることとか、悩み事とかあるの?」
「えっ? どうしたのいきなり。別に、特には無いよ? わたしどこか変?」
「う、ううん」
つい第一声で口にしてしまいましたが、ティーナの態度は何も変わりません。これまでにこの渦を色濃く見た時には、当人の様子にも少なからず異変があったものです。こんなにもくっきりと胸中を渦巻く黒が見えるというのに、表情や言動に何の問題もないのは初めてのことでした。
パフィーナさんが厨房の中へと場所を移し、代わりにティーナがカウンターの中に入ります。洗われたグラスの水滴を拭き取って片付けながら、ティーナは口を開きました。
「友達……なんて、ぼかして言う意味も、もう無いか。二人のところまで行ってきたんだもんね」
目の前で揺らめく渦が気になって、落ち着きません。けれど彼女の口調はどこまでも普通で、とても追求できる雰囲気ではありませんでした。
私は何でもないフリをして会話を続けながら、笑顔の裏を探ろうとします。しかし、この私にそうした器用な話術や観察眼が備わっているはずもなく、話の流れを誘導したり秘めた悩みを察したりすることなど到底できませんでした。
「私がキラについていったのも、知ってたの?」
「だいたい何があったかは聞いたよ。ほら、おしゃべりな妹がいたでしょ。ルミナから頼めばキラもちゃんとすると思ったんだけど、……一緒に会いに行っちゃうのは完全に想定外だったな……」
「そうだったの?」
「あ、ううん、いいんだ! 二人とも喜んでたから! 友達ができたんだって、嬉しそうに教えてくれたよ。だから本当に、いいの」
ティーナはかぶりを振って、いいんだよと繰り返します。それに伴い胸元に浮いている渦の回転が少し早まって、起伏も荒々しくなっていき、ドキリとしました。
何がいけなかったのか、実を言うとそれは今となってもさっぱりわかっていないのですが、とにかく急ぎで話題を変えます。
「そ、そうだ、飛び級! 飛び級で学校卒業してるって話聞いたけど、本当なの?」
「え……うん、まあ」
強引だったかもしれません。ティーナは少々戸惑ったように瞬きをして、小さく頷きます。
「でも、ただ早く卒業したかっただけだから、そんな立派なことじゃないよ」
「それでも凄いよ! 賞もいっぱい取ったって聞いたよ。早く卒業してバイトして、やりたいことや夢があるの?」
「夢か……そうだね……」
ティーナは視線を落とし、静かにグラスを下ろして口をつぐみました。
また話題選びを間違えてしまったのだろうかと不安になったとき、ぽつりと零します。
「わたしはただ……あの子を支えたいだけ」
消えてしまいそうな、細い声でした。
リボンタイと渦の色が重なってはっきりとは見えず、確証はありませんけれど、黒い濁りがきゅっと僅かにだけ縮んだように見えました。
「あの子たちに幸せになってほしいだけ……」
「ティーナ?」
それも束の間のことで、不意にパっと顔を上げるとまた元のように笑います。金髪のポニーテールが温かなランプの光を反射しました。
「――どんなに成績が良くたって、魔法ができたってさ、うまくいかないことっていっぱいあるよね」
「う、うん?」
「ふふ。ゴメン」
今度は私が、ぱちぱちと瞬きをします。
ティーナは優しい微笑みを浮かべました。カウンターからこちら側へ身を乗り出します。
「あのさ、そろそろ学園祭の時期でしょ? パンフってもう出てる? 今あったりする?」
「ん、あるよ! ちょうど今日もらったばっかり!」
その話題になったことで、私はすっかりはぐらかされてしまいました。鞄の中からパンフレットを出してテーブルに広げて、それからは次の来客までの間ずっと、学園祭の話をしました。
ティーナはニコニコと笑顔で、今年の予定や過去の学園祭の思い出を沢山聞かせてくれました。渦はティーナの胸の前に留まり、ほぼ静止しています。激しく揺れ動いたり、肥大化したりといったことはもうありませんでした。
「二人は来られないから、毎年わたしが見に行って教えてるの。今年はルミナとキラのクラスのことが一番のお土産話になるよ、きっと!」
結局のところ彼女に何があったのかは一切わからず仕舞いだったのですけれど、私はすっかり胸を撫で下ろしていました。
会計をしに来た人や新しく来店した人たちを何組か接客した後、一度裏へと引っ込んでからカウンター傍まで戻ってきたティーナの胸元には渦が見えなくなっていました。
「実はわたしも、話したいことがあるんだ」
空になったグラスを下げてもらい、そろそろ店を出ようと考えていた時でした。改まって、ティーナが声をかけてきます。
「これ、二人からの預かり物。ルミナに会ったら渡してほしいって。寮の部屋番号がわからなくて送れなかったみたい」
そう言って差し出されたのは、見覚えのあるパウダーブルーの長封筒。宛名や差出人の名前はなく、整った細い文字で、招待状、とだけ書かれています。
「来月、二人の誕生日会があるの。その招待状だよ。詳しいことは中に書いてあるから、帰ったら開けてみてね」
「あ! 見たことある! キラの部屋にも同じのあったよ!」
「……部屋、行ったの?」
「うん、学校の友達みんなで。キラの部屋ならいつでも片付いてるから急に大勢行っても大丈夫なんだって」
「何それー?」
ティーナはクスクスと笑いました。
「あの子が手紙の返事をずっと待っていたのはね、そのパーティの日の都合はどうですかって聞いたところで返事が止まっちゃったからなんだよ」
「そうだったんだ。キラは会いに行った時に何も言ってなかったけど、ちゃんと答えたのかな」
「大丈夫だよ、行くって手紙来てたから。心配だったからわたしもちょっとだけ見ちゃった。キラには黙っててね」
キラはあの後、顔を合わせての会話とは別に手紙でも返事をしていたようです。それを聞いて、彼はやはり几帳面な優しい人だと温かな気持ちになりました。
「パーティってティーナも来る?」
「当然! でもわたしはその日お仕事があるから、案内したりはできないかも」
「お仕事? ここのバイトとは違うの?」
「そ、ちょっとね。詳しくは内緒!」
そう話すティーナは、仕事と言いながらも楽しそうです。何かサプライズを計画しているような含みのある笑顔でした。
「本当に私が行ってもいいのかな」
「ルミナに来てもらいたい、ってあの子たちが言ってるんだよ。他にも色んな人が来るから緊張するかもしれないけどさ、二人は友達として呼んだだけだからあんまり気負わないで。何も予定無かったら顔出してほしいな。わたしからも、お願い」
スズライト家主催のパーティともなると、私には場違いなようにも思えるものです。しかしティーナは、貸し衣装もあるし美味しいご飯も出るし礼儀作法も厳しく気にする必要ないから、と二人の代弁をするように勧めてくれます。
私も、メアリーとネビュラにまた会いたい気持ちや彼女たちの誕生日を祝いたい気持ちは確かにありました。そのパーティがどういった催しなのか想像がつかず、緊張や不安も同じくらい強いですけれど。感情が入り混じり、ドキドキします。
キラにも今日のことを話して二人で一緒に行けば大丈夫かな、と考えながら、手紙を大事に鞄へ仕舞いました。
「わかったよ、来月だね! 帰ったら、二人に手紙出すよ」
「うん! よろしく! わたしも学園祭遊びに行くから、またね!」
ティーナはほっと柔らかく頬を綻ばせます。帰り際には、以前と変わらず笑顔で手をひらひらと振ってくれました。


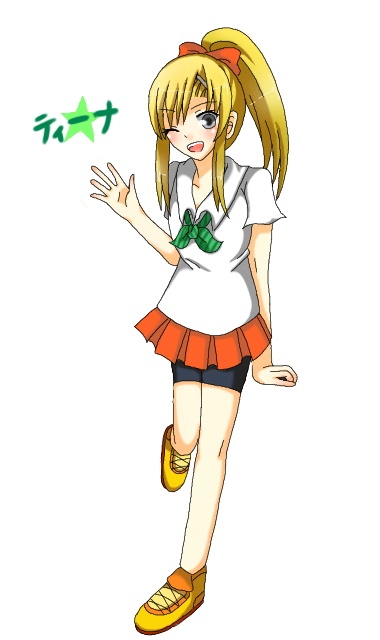

71.知らず知らずに
それは、特別な物語。
ミリーの心の最も深いところに仕舞われた、ガラスのように割れやすい繊細な感情で彩られた思い出でした。
時折、涼やかな夕暮れの風が吹いて静かな泉の水面に波を立て、木々がさわさわと揺れます。
広大な森の中の小さな泉のほとりで、全てを語ったミリー。
シザーはその隣に肩を並べ、黙って耳を傾けていました。
私がミリーから重苦しい霧の気配を感じなくなったと気が付いたのは、ずいぶん経った後のこと。
元より、彼女の心が霧や渦を生じさせているのを見たことはほとんどなかったのです。覚えている限りでは、初対面の日のみ。そしてそれは先日のルベリーの一件と比べ、決して主張の激しいものではありませんでした。
あの黒い霧や渦をミリーの周囲で頻繁に見ることがなかった原因は不明です。それは私自身の問題だったのか、それとも、ミリーが器用に心を取り繕っていたのか。未だに定かではありません。
今更どんなに思い巡らせ、どんな言葉を並べ立てたところで、言い訳でしかないのですけれど。
私とミリーはクラスが違いましたので、学校でも毎日顔を合わせるということはありませんでした。
そうは言っても教室は隣同士ですし、廊下に出たときや登下校のときなどに見かけることはあります。いつ見てもミリーは明るく笑顔で、そこに裏があるようには思えませんでした。
けれど本当は、どうだったのでしょうか。私には肝心なことが何一つ見えていなかったのではないでしょうか。
ミリーの胸の内に「それ」が秘められていることは、ずっと前から知っていたはずなのです。商店街で彼女と知り合った日に一度、紛れもなくそう感じたことがあるのですから。夏休みが明けてからも一度、彼女が零した弱々しい呟きを確かに耳にしていたはずなのですから。
あれは、暗い感情を笑顔で覆い隠すことの上手なミリーが表出させた数少ないサインだったのかもしれなかったのに。
私にはそれに気付けるだけの「能力」があったはずなのに。
私はミリーのために何もしなかった。
何の行動も起こさなかった。
知らなかった。
そのため、彼女が一体どんな思いを抱え込んでいたのか、その淀みが本当に解消されたのかどうか、私には判断ができないのです。
シザーに話を聞いてもらっているとき、パリアンさんやバレッドさんの店で相談をしているとき、その場に私はいません。初めにお断りさせていただいているように、私に語ることができるのは自分の見聞きしたことだけ。そして、それらの出来事が全て終わった後に、当事者である友人たちから伝え聞いた内容だけでございます。
あの日ミリーとシザーが森の中で何を話したのかは、二人の間だけの秘密。
私の知らないところで、ミリーの心を曇らせていたものは取り払われたのです。
私は何もミリーの力になれませんでした。
そのことに、長らく気が付きもしなかったのでありました。
学園祭の開催まで、ついにあと一週間を切った頃。
当日に来場者に配るパンフレットが完成し、皆に配られました。文字もイラストも全てが手書きで、十ページ程度の紙に糸を通して製本した、生徒手作りのパンフレットです。下校前のホームルームは大賑わいとなり、パルティナ先生に軽く注意を受けました。
最初のページを捲ると、校長先生と実行委員長の言葉が掲載されています。その次は校内の地図と各クラスの出店の紹介があり、有志のステージ発表のプログラムに続きました。一グループ十分程度のパフォーマンスが、講堂で丸一日通して行われるようです。
閉会式では最も人気を集めた出店とステージを発表することになっていて、その投票のためのアンケート用紙も綴じ込まれています。そして最後に、自由参加の後夜祭ではキャンプファイアとフォークダンスを行うとありました。
「あー……今年の開会式はミリーちゃんのライブ無さそう」
「ねー。でも仕方がないよ」
「だよね」
教室内のどこからか、そんな会話が聞こえました。どうやら、昨年の開催セレモニーではミリーが歌を歌っていたようでした。
私はステージのプログラムのページを机の上に開きます。同じクラスに、特技のダンスで参加する友人がいたからです。
ずらりと並んだ一覧を上から辿って彼女の名前と発表の時間を探していると、別の友人の名前を先に見つけました。キラの正面の席に座る男の子で、私の席からもすぐ近くです。四人の友人とバンドを組んでライブをするらしく、パンフレットにはバンド名とメンバー全員の名前も細かく記載されています。
彼らのライブは午後のトップバッターで、彼女のダンスは最後から二番目です。私の知人の名は、そのクラスメイト二名のみでした。
プログラムの確認をした私は、椅子から腰を浮かせてその男子生徒に話しかけます。彼は笑顔で振り返りました。
「楽器できるの? 凄いね、知らなかった! どんな曲やるの?」
「東の国のロックンロールだ、有名な曲多いと思うぜ! ちなみにおれはドラム。キラも来いよ? そんで一票よろしくなっ」
「ロックか……、あ。この時間、オレ店番だ。悪いな」
「マジかよオイっ。じゃあせめて投票だけでも!」
「お前はそれで本当にいいのか?」
彼は声高に宣伝するも、淡々としたキラの返事を受けてガクッとコミカルにつんのめります。キラはクールな反応でした。
少し遠い窓際の席の方では、ステージ発表にエントリーする彼女とネフィリーが喋っています。
「この時間に講堂だね。見に行くよ、頑張って。大勢の観客の前で何かするなんて、私は絶対無理。緊張しないの?」
「するに決まってんじゃん!? でもやっぱ楽しいし、わたしの取り柄ってそれくらいだし。頑張る! やるからには、目指せ最優秀賞!」
この放課後、私は二人の傍まで行って、出店を一緒に回らないかと誘いました。当日も最後の調整に精を出したいという彼女とは都合が合いませんでしたが、店番のシフトが一緒でもあるネフィリーは快諾してくれました。
「でも、ミリーもいい?」
「もちろん! もしかして、先にミリーと約束してた?」
「うん。だけど、まだ向こうのシフトがどうなったのか聞いてないんだ。最近何だか忙しそうにしてて、タイミングなくって。今日の掃除の後、また聞きに行ってみる」
「じゃあ私も一緒に行くよ」
「うん」
「前から思ってたけどさ……ミリーちゃんと普通に友達できるの、羨ましいわ」
そう言われて向き直ったネフィリーは、顔に疑問符を浮かべます。
「ネフィリーなんて、去年からずっと仲いいじゃん?」
「う、うん。まあ。クラスが同じだったから」
「そうじゃなくて」
私は昨年までのミリーと周囲の様子を知らないけれど、彼女が言わんとしていることは少しわかりました。芸能活動を休止していても尚、学校中に知れ渡る程の噂を立てられる彼女ですから、皆にどれだけ注目されているのかは想像に難くありません。私はアイドルとしてのミリーを実際に見たことがないため、その凄さに実感を覚えることなく接することができていただけなのであります。
「……ミリーが目立つ人なのはわかってる。私が隣にいていいのかって思うことも、無いわけじゃないよ。だけど私には初めての友達で、ミリーといるのは楽しいもの。……あ、その、この学校で初めての……って意味だから」
ネフィリーはそのように答えました。少々気恥ずかしそうでした。
私がミリーを初めて見たのは、まだパルティナ先生から魔術科の補習を受けていた頃の放課後。皆にとっては、二学年に進級してクラス替えがあってから一ヶ月ばかりの頃です。
その頃に、一緒に帰ろうと隣のクラスに赴いてまで声をかけてきたのはミリーの方だったことを思い出しました。皆で夏休みに集まって遊ぶ計画を立てていた時も、ミリーが率先してネフィリーを誘っていたことを思い出しました。
それはただ友人として自然な振る舞いであって、深い意味はないかもしれませんけれど。
ミリーにとってのネフィリーの存在は彼女自身が考えるよりもずっと大きく、大事な日常の一部になっているのではないかと、私には感じられたものでした。





70.singer(2)
一歩を踏み出すきっかけになったのは、シズクちゃんだった。
本当の願いを押し殺して、歌っちゃいけないんだと思い込む一方で、このままじゃいけないってこともずっとわかってた。ワタシの歌を待ってくれている人はクレアの他にも沢山いて、その人たちに嘘を吐いたままのワタシの態度は不誠実でしかないもん。
そんな中で出会ったシズクちゃんの存在は、立ち止まってしまっていたワタシの心に大きな波紋を広げた。
「あの子は……目が見えてなかったな。確か、手術するって」
シザーが呟く。
ここまで聞いていて、いくらか察しがついたみたいだ。ワタシは頷いた。
「手術、って言葉でね、クレアが重なって見えたの。それで、このまま別れたら絶対にまた後悔する、って思った」
それが過剰反応だという自覚はあったけど、衝動は収まらなくって。
二人の症状はまるで違う。シズクちゃんはクレアじゃない。だから、ワタシがしているのは身勝手な感情の押し付けでしかないんだ。
クレアの病気は、体内に魔力を留めることができないというものだった。ボロボロと崩れ落ちるように魔力が流出していくのを止められず、全身が内側から徐々に弱っていくという、長年治療法が確立できていない難病なんだって。
実際のところ、クレアの容体が悪化したのは彼女自身の身体よりも環境要因が大きかった、って話を後から聞いた。ワタシがお見舞いに行っていなかったあの冬の頃、スズライトに循環している妖精の魔力を何か別の大きな力が食い破ったような乱れが観測されていて、そのせいで発生した不安定な魔力の波がクレアの体にも影響を与えたんじゃないか……って。聞いてもよくわからなかったけど……。
クレアは、ワタシにはただの検査だと偽りながら、本当は何回も施術を繰り返していたらしい。その事実も、そうして何度治療を施しても望ましい成果が出なかったことも、ワタシはずっと知らなかった。
だけど、そんなことは関係ない。クレアが苦しんでいるときにワタシが傍にいなかったのも、何もしなかったのも、どうしようもなく本当のことだから。
この後悔は、薄れていくことはあっても、消えることは一生ないんだろうな。
抱えたまま生きるんだ。
シズクちゃんと一緒に病院へ向かう間、その歩幅に合わせてゆっくりと歩きながら色々な話を聞いた。
目が見えないのは怪我じゃなくて病気で、元はちゃんと見えていたけど、小さい頃のことすぎてもう覚えていないとか。検査と手術のためにこの夏から入院していて、体は健康だから暇で仕方がないとか。
あの子の語る言葉全てが、明るく喋っていたクレアを思い起こさせる。手術なんて怖くない、と元気そうに笑う様子にまで、クレアの笑顔が被って見える。
『ママがレコード持ってきてくれてね、それがミリーちゃんのお歌でねっ、ずーっと聴いてたからもう歌詞見なくたって完璧に歌えるんだよ! すごいでしょ! シズクはね、最初のデビュー曲が一番好きだよ! ホントのホントーに、お歌聞かせてくれるの!?』
『……うん。約束する。でも、今すぐじゃないよ? ちゃんと用意できたら教えるね』
『わかった! 絶対約束!』
シズクちゃんはあんなにも真っ直ぐワタシを応援してくれていたのに、ワタシはクレアと比較するばかりでシズクちゃん自身のことを何も見てなかった。その自分勝手さがわかっていたから、まだ自己嫌悪に苛まれた。
でも、グズグズしている時間はないんだ。
シズクちゃんが無邪気に笑いかける。
『手術の日はね、えっとえっと、来月の最後のお休みの日だから! そんなに先なのにもう入院してなきゃいけないなんておかしいよねー? 早く聞かせてねっ』
ドキリとした。
グズグズしていられない。今すぐにでも心を決めて行動を始めなきゃ、きっと間に合わない。
あまりに急だった。
本当はまだちょっと、自分を許せない気持ちは残ってる。だけど、好機と思うしかない。
そう、これはチャンス。シズクちゃんがチャンスをくれたんだよ。
同じ後悔を繰り返したくない。自分の気持ちをごまかしたくない。ワタシはワタシ自身のために、ワタシ自身が願うままに、シズクちゃんの願いを叶えるんだと決めた。
それがわがままだとしても、もう構わない。ワタシは前に進みたい。
また歌えるようになりたい。
それが今のワタシの一番の願いだ。
細い木漏れ日が泉を照らしている。
シザーの目元にも柔らかな光が落ちていて、気持ちの整理がついたみたいだ。
「ここだけの話にしておいた方がいいか? レルズの奴が心配して、活動休止にした事情知りたがってたみたいなんだけどさ」
「レルズ君が……そっか。そうだね」
彼は、ワタシの歌を好きだと言ってくれた人の一人。知り合ったのはアイドルを休んでからのことだったけど、向こうはそれ以前からワタシを見ていてくれた。多分、今も変わらずに。
きっと同じ疑問を抱いたまま待ってくれている人は、レルズ君の他にも沢山いるはずだよね。そのことからも逃げないで素直に受け入れて、謝って、気持ちを伝えないといけない。やらなきゃないことはいっぱいだ。
「そうしてもらおっかな。いつかワタシが自分の口で、ちゃんと言うよ」
「ん、そか。よし、わかった」
ワタシがそう答えると、シザーは満足そうに微笑んで頷いた。
話し始めは慎重な顔をしていたシザーだったけれど、なんだか今は晴れ晴れとしているように見えるかも。ワタシも今は、その目を逸らさず正面からちゃんと向き合える。
シザーは、ワタシの長話に対して自分の思いをあまり口にしなかった。途中で口を挟むことも一切なかった。
「大丈夫ってのはマジだな。顔でわかるぜ」
感想らしい感想を発したことといえば、一通り聞き終わった後にそう言ったくらい。言葉の代わりに、その目でワタシを見守ってくれている。静かな瞳。なんだか大人みたいだ。
森の空気は穏やかで、優しい風がちょっぴり肌寒い。
水面がかすかに揺れる。
不意に、思い出したようにシザーが顔を上げて、
「なあ、歌ってみてくれないか?」
そんなことを言い出した。
どこか遠くで、鳥が羽ばたく。
ワタシは開いた口が塞がらなかった。
い、今? ここで!?
シザーっていつもいきなり! 何考えてるのかほんとにわかんないなぁ、もう!
「あー、いや、ミリーの覚悟を疑ってるわけじゃないぜ。ただ何つーか、何でだろうな、お前の歌を聞きたい気がしたんだ。まだ駄目だったか」
「う、ううん……駄目じゃない、けど、急だからびっくりしちゃった」
宿題やってきた? と休み時間に聞くみたいにシザーは軽く口にしたけれど、ワタシは授業中に指名された気分だ。シザーからこんなことを言われるなんて、全く考えもしなかった。
「ワタシあれからずっと歌ってない、って言ったよね?」
「そうだな。じゃ練習ってことで。な?」
「うっ、うぅー」
シザーはニッと笑う。ワタシは体を縮こまらせた。
毎日のように歌を歌っていたあの頃から、半年以上の月日が経っている。だから、感覚を取り戻すための練習は確かに必要。頭ではわかってる。
ワタシが今すぐに歌い出せないのは、不安な思いも強いからだった。
単に久しぶりだから上手にできないかもしれないという恐れもあるけど、もっと大きな理由は、期待に応えられないのが怖いということ。
ワタシは心から歌が好きだったわけじゃないし、志だって全然立派じゃない。かつてクレアのピアノがそうだったように、今のワタシの歌が誰かの心に響くのか、って改めて考えると、怖い。
自信がないんだ。
「……できるかなぁ」
「できるさ」
ついポロっと零してしまった弱音を、シザーはさらりと掬い上げた。
優しくて力強い眼差しが、ワタシを見据える。
「ミリーの気持ちは本物だからな。したいって思ってんならできる。好きならできる。好きなんだろ、歌うの」
「……うん」
「俺にはそんなに好きなことも打ち込めるもんもねーから、ミリー達のことが羨ましくなったのかもな。だから教えてくれよ、ミリーの好きなことをさ!」
シザーの晴れやかな声が、眩しい笑顔が、胸の中を温かくしていく。
前までだったら、こんなにも直球で期待を向けられたら暗い影の方に逃げたくなっていたと思う。でも、なぜか今は違った。彼の笑顔には、人の心を照らす力があるみたいだった。
こちらの困惑にはお構いなしと、シザーはどんどんとワタシを引っ張っていく。
「曲は何でもいい、ってのも困るか。そうだな、お前の一番好きな曲か、今歌いたいと思ったのがあればそれがいい」
「そんなの……」
そう言われて、反射的にパっと浮かんだイメージはもちろん、手書きのあの楽譜。他のどんなものより大切な、宝石のように大事にしている楽曲。
音符の一つ一つが、まるでワタシに歌われるのを待ち望んでいるかのように、煌めいて見える。
一番好きな曲だなんて、決まってるよ。ここまでワタシの話を全部聞いた後なら、言うまでもないでしょ?
わかってて聞いてるのかな? と思ったけど、そんな顔ではなさそう。さっきまでは大人みたいだったのに、今は子供みたいに純粋な目を向けていた。
これは、多分……何も深い意味はないよね。シザーだもん。
シザーは知らない。気付いていない。あの日、貴方が初めてワタシの前で笑顔を見せたときに、ワタシがどんな気持ちを抱いたのか。ワタシには、それをシザーみたいに簡単に口に出すことはできないから。
笑ってる方がいい、って言ってくれたね。
嬉しかった。
実はね、あの瞬間ワタシも同じ風に思っていたんだよ。
貴方は笑ってる方がいい、って。
初めて見たその表情をもっと見てみたい、って。
ワタシは倒木の椅子から立ち上がり、パパっと軽くスカートを払った。
透明に澄んだ光の筋が泉の中央に降り注いでいる。
きゅっと唇を引き結んで一歩ずつ進み、光の目の前まできたところで振り向いた。
小さく開けた口から息を吸い、少し止めて。
セーラー服の襟元に右手を添える。
「……聞いててね?」
ワタシの一挙一動にシザーの視線が向かう。
木漏れ日のスポットライトを浴びた姿は、どんな風に見えているだろう。
どうか、魔法をかけることができますように。
クレアを想い、悼み、クレア一人のためだけに綴った詩。この歌はワタシそのものだ。
半年もの間歌っていなかったけれど、歌えなかったけれど、一語一句全て覚えている。
歌い出しは不安だったけれど、少し音が揺らいでしまったけれど、昔と変わらずに声は発せられた。そのことに罪悪感もなくて、肺の動きが右手に伝わったとき、懐かしい感じがした。
不安だったのは初めだけだった。
なんて簡単なことだったんだろう。一体何を怖がってたんだろう。
最初の一音を乗り越えてしまえば、あとはその流れに身を委ねるだけでよかった。流れ出したメロディは自然に、途絶えることなく、先へ先へと紡がれていく。
心も体も解放されていく感覚を覚える。
世界に音が溢れ出す。
真っ白な雲が穏やかに流れる、晴天の空を表したようなバラード。そのしっとりとした旋律に、胸の底で淀んでいた澱がするすると溶けていく。
頭のてっぺんから足の爪先まで行き渡るのを想像しながら、息をたっぷり吸って、吐いて。
伸びやかに、高らかに、どこまでも響かせるように。
森を超え、あの空の向こうにも届くように。
歌いながら、記憶の中にある伴奏を心に思い描く。
聞こえるはずのないピアノの音色が、ワタシの歌声に寄り添ってくれている気がした。
長く息を吐きながら、ゆっくりと右手を下ろす。サビだけのつもりだったのに、気付けばまるまる一番が終わるまで歌い続けていた。
体中に充足感と高揚感が満ちている。
――歌えた。
歌えたんだ。
最後にもう一度、深く息を吸った。森林の清々しい空気が染み渡った。
呼吸を整えながらシザーの方へ意識を向ける。彼はどこか惚けた様子で、数秒ほど遅れてワタシの視線に気付きハッとした。
「あっ、お、終わりか?」
「え? 何その反応、ど、どこか変だったかな……?」
「逆。もっと聴きたかった」
シザーは呟くように口にすると、繰り返した。
「レコードで聴くのと全然違う。すごいな。うん、すげーよ、ミリー」
飾り気のない、素朴でストレートすぎるその感想がワタシの不意を打ち、ギュッと胸をいっぱいにさせる。
シザーの声色は徐々に熱を帯び、両膝に手をつくと身を乗り出してきた。大きく瞳孔を開いた目がいつになくキラキラして見えるのは……ワタシのうぬぼれかも。
そんな風に見えるのも、歌って褒められるのは初めてじゃないのにこんなにドキドキしているのも、全てを聞いてほしいと思ったのも、きっと理由は単純明快だったとわかった。
彼が、ワタシの特別だからなんだ。
だけどシザーのことだから、彼には他意は全然ないんだろうなぁ。
そう考えると、火照った心は少しだけ落ち着きを取り戻した。ワタシのこの内心の揺れ動きが、あのシザーに伝わっているはずもない。
照れ隠しに、ビッと指を突きつける。
「シザーは今、超贅沢なお願いしたんだからね! そこんとこ、ちゃんとわかっといてよ?」
「おう、急に自信満々じゃねーか」
「当然! そうでなきゃ、アイドルは続けられないよ!」
言い切って、堂々と胸を反らした。ちょうど夕焼けのスポットライトが当たった。
羽が生えたみたいに、すっかり心は軽い。
「この続きは、本番のお楽しみね?」
「本番。それって――」
ピクリと、シザーは僅かに目を見張った。
それを見逃さない。
咄嗟に閃く。
「えへへっ、これ以上はまだ秘密! そうだなぁ、ヒントは学園祭? なんて」
ここぞとばかりに、その単語をちらつかせてみせた。
ちょっと意地が悪かったかも。シザーが学園祭を避けようとしているのは、エレナに聞いて知ってるし。
だけど、ワタシはシザーと一緒の思い出が欲しいんだよ。だってワタシたちは、今しか一緒にいられないかもしれないでしょ。同じ場所で同じ時間を共有できることって、奇跡みたいなことなんだよ。
クレアとはできなかった。
もしかしたら、ワタシはクレアの代わりを求めているだけなのかもしれない。でも、そうだとしても、今のこの思いを大事にしていたい。たとえどんな理由でも、もう自分の気持ちに嘘をつかないって決めたから。
それに、こう言ってしまえばワタシだって引き下がれなくなる。覚悟を決めろっ、ワタシ!
「本当のワタシは、全然こんなものじゃないよ! 本番はもっと、もっと、さっきより何倍もいいパフォーマンスをしてみせるから。……だから、シザーにもまた聴いてほしいな?」
シザーの返事はなかった。けど、ワタシは願い続ける。
ここはゴールじゃない。
まだ始まってすらいない。
これからがワタシの本当のスタートライン。
これからもクレアが魅せてくれた世界に生き続けていたいから。
そのための第一歩として、考えていることがあるんだ。
ワタシの新しい門出、大切な人に見守っていてほしいな。
* * *


69.singer(1)
ワタシは歌が好きで、歌っているときは本当に幸せだった。
今でこそ、そう自覚している。
でも元々は、そんなに好きだったわけじゃないんだろうな。ワタシが歌うとみんな褒めてくれるから――クレアが喜んでくれるから嬉しかった、ってだけで。
クレアに届かないのなら、もう歌う理由なんてないと思っていた。少し、疲れたんだ。
シザーもわかってるかもだけど、当時は今以上に、色んな噂がワタシの周囲を取り巻いていた。学業のためにアイドルを休みます、と発表して、それを疑うことなく信じてくれた人が大半だったけど、中にはそのことで馬鹿にしたり見下してきたりする人もいたし。詳しく聞き出そうとする記者さんに道を塞がれて質問攻めに遭ったことも一度や二度じゃない。
だけど全部無視して、全部にごまかしの嘘をついた。クレアとの思い出には、赤の他人に気安く触れてほしくなかった。
本当の事情を知っているのはワタシたちの両親と、所属事務所の人たちと、去年クラス担任だったパルティナ先生……それくらい。あと、パリアンさん――衣装関係の仕事を手伝ってくれててプライベートでも仲が良かったお姉さんも、把握していたらしい。それはこの間知ったんだけどね。
説明する必要がある人にだけは話した。そうしなきゃいけないわけじゃない相手に、こうして打ち明けたのは初めて。
あの日暮れの路地裏で、もしもワタシを見つけて追いかけてきたのがシザーじゃなかったら、今隣に座っているのも違う人だったのかな?
この話を彼に聞いてほしいと思ったのは、あの時に彼が言った言葉を忘れられなかったからなのかな?
ふと、そんな疑問が浮かぶ。
ワタシはずっと静かな水面を見つめ、あの頃の気持ちを思い出していた。
活動休止に至るまでの経緯を全て語り終えたところで瞳を閉じ、小さく息を吐いて、隣へ視線を移す。シザーは言葉を失ったように口を小さく開けたまま固まっていた。
困らせたかな。
そうだよね。
「本当に、聞いてよかったのか」
そう一言だけ尋ねてくる。まだ戸惑っている様子だ。
「平気、お話したいって言ったのはワタシの方なんだから。ごめんね、こんな暗い話しちゃって。気を遣わなくっていいからね? 本当にもうワタシは大丈夫なんだよ」
しっかりと顔を見て笑ってみせたけど、シザーは逆に険しく眉を寄せてしまった。
「……それは嘘じゃないよな?」
「うん。本当。いつまでも泣きべそかいてるワタシじゃないよっ」
「けどそのせいで――、……や、そんなことがあったから、ショックで歌えなくなったんだろ。そんなの……」
「んっと……。そうだね、結果的にそういうことではあるんだけど、微妙にちょっと違うかも?」
ワタシの返答に、シザーは更に眉間の皺を深くして疑問符を浮かべる。だけど、問いかけてはこなかった。
言い方一つ一つに気を配って、ワタシを傷つけないような言葉を探しているみたい。尋ねても構わないことなのかと、ワタシの顔色を窺っているようにも見える。
ワタシが話したくないと言ったなら、きっと彼はそれも受け止めてくれる。ワタシが泣き止むまで隣にいてくれたあの日と同じように、何も言わず。
だけど、だからワタシは、貴方には全て聞いてほしいと思ったんだ。
木々の切れ間に流れる雲を見上げながら、続きを話す。
「ワタシね、ショックで歌うことができなくなったっていうより、歌っちゃいけないっていう気持ちだったんだ。自分でも知らないうちに、そうなってたの」
優しい風が、サワサワと葉を揺らした。前髪が額を撫でる。
自分でもついこの前に理解したばかりの感情。それなのに不思議と、冷静に喋ることができた。
学校へ毎日登校するようになってから、ワタシは確かに歌っていない。でもそれは、決して歌えないとか歌いたくないとかじゃなくって、理由がなかっただけ。
歌の授業もなかったし、ライブや収録がないならボイストレーニングをする必要もないし、一番歌を届けたい人はいなくなってしまったから。むしろ、それでもファンの為には歌わなきゃいけないって気負っていたくらいだ。
だけどそうやって思い詰めて歌った歌なんて、ワタシの歌じゃない。クレアも望んでないはず。そんな風に理由を付けて、しばらくの間は大人たちの優しさに甘えて、言われた通り休もうって思っていたの。
それにあの頃は、学校の中に溶け込もうとするのでいっぱいいっぱいでもあったんだ。勉強が遅れているのも全部嘘の話ってわけではなかったし。補習だけは免れていたとはいえ、ボーダーラインスレスレの成績だった。
でも、心を休めなきゃ、勉強をしなきゃ、って考えていても、気が緩むと休み時間でも授業中でも悲しい気持ちが溢れてきて、涙を零しそうになった。
みんなはワタシに笑顔を望んでいる。
だから、笑顔を作って耐えた。
誰にも気付かれないように、平気なフリをし続けた。
そうして何事もないフリを繰り返していたら、苦しくて胸が潰れそうなときも確かにあったけど、だんだん本当に平気な気になれた。それがいいことだったのか、悪いことだったのかは、わからない。
思い返してみると、ワタシが「ピアニスト」の作詞に躍起になっている間に転入してきたというネフィリーと仲良くなったことは、一番大きなきっかけだったかも。学校で初めてワタシにできた本当の友達ってネフィリーだったんじゃないかな。
あまり積極的じゃない性格で友達を増やせずにいたネフィリーと、良くも悪くもアイドルというフィルターがかかって同級生との間に距離があったワタシは、自然と一緒にいるようになった。
ワタシはたまにしか登校してなかったから、とっくに固まっていた人間関係の輪の中にうまく入り込めていなかったんだ。それから、ネフィリーはワタシのことを噂ですら何も知らなかったらしくて、そのことも都合が良かったのかもしれない。
だからなのか、教室の他の誰といるよりも、ネフィリーの隣は居心地がよかった。向こうも同じように感じていてくれたら嬉しいなって思ってる。
ネフィリーのおかげでワタシの心は少しずつ軽くなって、嘘じゃない本物の笑顔の回数も増えて。
それと反比例するように、クレアのことを思って涙が込み上げてくる回数は減りつつあって。
そんなときだった。
あの日は確か、ルミナと初めて話した日だ。引っ越してきてすぐだったルミナに商店街を案内していた。
その後、ルミナと別れて一人になったワタシは大通りから外れていった。お気に入りの雑貨屋さんを見に行くつもりで、近道を抜けようとしていた。
平日の夕暮れ、見晴らしが悪く狭い道、人通りは少ない。角を曲がるときに、向かい側からやってきた人と鉢合わせる。
そこは街灯の真下で、照らされたワタシの顔がちょうどバッチリ見えてしまったんだろう。その人は口と目を大きく開けると、嬉しそうな歓声を上げてワタシの名を呼んだ。急いで伊達眼鏡をかけ直しごまかしたけれど、もう手遅れだった。
出会ったのは二人組の女の子。王立魔導学校の制服の黒いマントを羽織っていて、二つか三つくらい年上のようだった。
握手をお願いされて、その後にも話しかけられたのはちょっと困ったけど、別につらいことはなかったんだ。二人は気さくで明るくて、話しやすかった。
『本当に街でアイドルに会うことってあるんですね……! 何か買い物ですか? あっ、隠れて来てるんだったら、ちゃんと内緒にするので大丈夫です』
『あたし達、サンローズにカラオケしに行くところなんだ。せっかくだから今ここでちょっとだけ歌聞かせてもらえたり……なんて、やっぱダメよね?』
そう聞かれたときだって、アカペラで一フレーズ程度ならいいかなって初めは思ってた。
ワタシの歌を待っているのは、クレア一人だけじゃなかったんだから。数ヶ月前に比べれば、気持ちはだいぶ落ち着いている。今なら前までのように歌えるかもしれない。そう思って。
なのにどうしてか、息を吸って歌い出そうとした途端にワタシの喉は引きつってしまった。
息を吸い込んだときに、幼い頃のクレアのキラキラした目に見つめられているような気がした。ただ、その瞳は透き通った空色ではなく、雨雲のように黒く濁っていた。
喉元に固い石をぐっと詰め込まれたみたいに苦しくなる。
ぎゅっと体中がこわばり、どんどん胸が塞がって、唇が小刻みに震えて。
こんなこと初めてで、訳がわからなくて、混乱で視界がぐるぐると回る。
俯いてぴたりと黙りこくってしまったワタシを、二人がきょとんとした目で見つめている。ワタシは動揺を悟られないように声を絞り出し、顔を上げて笑顔を作った。
『……ご……ごめん、なさい。ワタシ、行かなくっちゃ』
『ううん、いいよ。あたしこそ変なこと頼んでごめんなさい。気にしないで!』
『帰ってくるまでずっと待ってますね、ミリーちゃん!』
二人の気遣いと応援の言葉が胸に刺さり、居たたまれなさと申し訳なさがたまらなく膨れ上がっていく。
ワタシはすぐに角を曲がって細い脇道に入り、彼女たちが見えなくなったのを確認すると、走って逃げ出した。
そこから先はもう、貴方も知っている通りだよ。二人の姿がすっかり見えなくなるくらい遠ざかってからもワタシは闇雲に何かから逃げ続けて、誰も来なさそうな何もない路地裏に辿り着き、うずくまって泣き顔を隠した。シザーがやってきたのは、そんなときだった。ワタシの様子を気にして、後を追ってきてくれたんだったね。
あの日歌えなかったことは、とてもショックだった。理由もさっぱりわからなくて、何も話せなかった。
どうしてあんな風になってしまったのか、今は言葉にできる。
歌おうとしたときに、もう歌えるって思った瞬間に襲いかかってきた感情の正体は、恐怖だった。
それはクレアを忘れていくことへの恐れ。
クレアのいない客席に向かってもそれまでと変わらず歌えるようになってしまったら、いつかクレアがいたことも忘れてしまうかもしれない。その可能性への怯え。
歌うのは楽しいよ。だけどそれは、クレアに出会いクレアに教えてもらわなければ知らなかった気持ちなんだ。
クレアは音楽を愛していた。中でもピアノを奏でることが大好きで、そのひたむきな姿にワタシは惹かれた。憧れて、真似をして、同じ世界を隣で見てみたいと感じた。
みんなが褒めてくれるワタシの歌の世界というのは、そうやってクレアに分けてもらったもの。歌が好きという思いをワタシに芽吹かせたのは、クレアの力。大勢の歓声も、降り注ぐスポットライトの光も、ワタシが自分の力で手に入れたものじゃないんだ。
だけど、クレアがいなくなった後も、それらは失われていない。
悲しい気持ちになる回数が減って、涙が溢れてくることがなくなって……それで、目まぐるしく移り変わるあの世界に戻っていったら、ワタシはどうなるだろう。
忙しさと楽しさに溺れていって、次第にクレアに歌を届け続けた記憶すら薄れていって、クレアにもらったものを初めから自分だけで得たものだったと勘違いしてしまうんじゃないか。
そんなのワタシが許さない。
ワタシばっかり幸福じゃいられない。
知らず知らずのうちに、そうやって自分自身を締め付けていた。じっとワタシを見つめていた昏い瞳の正体は、ワタシ自身の瞳だった。
周りの人はみんな、ワタシに優しい言葉をくれる。活動休止に至った本当の理由を知っていても知らなくても。可哀想に、とか、応援してるね、とか。
その度に、胸を締め付けられた。だってワタシはそんな言葉をもらっていいような人じゃない。ワタシはまだ半年前の自分を許せないのに。それなのに、誰もワタシのことを責めないの。
ワタシだけが、ワタシの後悔と子供じみた愚かな失敗を知っていた。だからワタシだけは、ワタシを許しちゃいけなかった。
クレアを忘れないために。自分を罰するために。そのためにワタシは歌っちゃいけない――歌えない。
自分で締めたその鎖の存在には長い間無自覚だったけど、多分、しっかり重圧はのしかかっていたんだ。
自責の念に堪え切れなくなっていたワタシの心はいつしか、その感情を押し付けるためだけの、クレアの姿をした虚像を作り出していた。雨雲のような黒に染まった目をしたクレアの幻を見て、その口を通して戒めの言葉を言い聞かせることで、心を保っていた。
でもね、この前そのことをようやく自覚して、そのいびつさがやっとわかって。それで、少し楽になれたの。
――こんなこと願っちゃいけない。”わたし”が許さない。だってそうしたら、多分、そのまま”わたし”は……。
――ミリーの道を決めるのはミリーなの。クレアちゃんの思いも、クレアちゃんだけが決められるの。それはミリーの決めることじゃない。
ワタシの間違いを、はっきり指摘してくれた人がいた。
――死人は何も言わねえだろうが。
クレアが最期に伝えてくれたことは何だったのか、思い出させてくれた人もいた。
それに気付かされたとき、ワタシ今まで何やってたんだろう、って情けなかった。忘れないために、って思っていたことだったのに、実際には真逆の方向に進んでいたなんて。大バカだ。
もう間違わない。
クレアの本当の気持ちを見誤らない。自分の本当の願いに嘘をつかない。
クレアはもう帰ってこないけど。どんなに大事な思い出もいつかぼやけて色褪せてしまうかもしれないけど。それは、とても怖いことだけど。
でも、きっともう二度と忘れない。忘れるはずがないんだ。
ワタシの手には、形となった想いが確かにあるから。沢山の言葉を、手紙として受け取ったから。
それがクレアの本当の気持ちだと、心からの言葉だったと、胸に強く刻む。信じ続ける。
忘れないために、歌い続ける。
歌が続く限り、忘れない。
――わたしは、ミリーの歌にいっぱい元気をもらいました。これからもずっと、ずっと、応援しています。
クレア、ごめんね。
ワタシの弱さのせいで、長い間あなたの願いから目を背けて、遠ざけてしまっていた。ワタシたちの気持ちは重なっていたはずだったのに。
クレアはワタシに歌ってほしいと、ずっと言ってくれていたね。
ワタシも歌いたいよ。
ずっと、ずっと、歌いたかったんだよ。


68.pianist(3)
夜、自室のベッドの上で楽譜を繰り返し捲って、キーボードの音色を思い出しながらハミングする。最後の一枚に貼られたドット柄の付箋と「誕生日おめでとう!」のメッセージが目に入る度に、嬉しさで胸の奥がこそばゆくなった。
三週間先のクレアの誕生日のお返しを何にするか、決めた。
この曲の歌詞とタイトルを作って、歌にしてクレアへ届けよう。
それで、もしクレアから了承が得られたら、ライブのステージでも歌ってみたい。マネージャーさんにもこの楽譜を見てもらって、そのつもりで話を進めていてもらおう。クレアは恐縮するだろうけど、きっと喜んでくれるはず。
それこそが今のワタシにできる最高の贈り物だと、微塵も疑わなかった。
今もまだ後悔してるんだ。
あれは間違った選択だったんじゃないかって。たった一日の特別な日のために他の時間を全てなげうつような選択が、本当に正しかったのかって。
クレアの誕生日には、ライブの予定が重なっていた。年末の特別なライブで、複数のアーティストと合同だったから、どうしても日程をずらすことはできなかった。出演時間がさほど長くないのが救いだった。
日中はまずライブを完璧にこなすこと。それが終わったら、真っ直ぐクレアの元に向かうこと。どちらか一方だけじゃない。両方大切で、両方とも成功させたかった。
ずっとその日のことだけを考えて、三週間の全てを注ぎ込んでいた。
彼女のお見舞いにも行かずに。手紙も出さずに。
陽が沈み、三日月も厚い雲に隠された、真っ黒な空の下。
カーテンの閉ざされた病室に、クレアが眠っているベッドを取り囲むように人が集まっている。
その最も近くにうずくまって、嗚咽し、嘆いている二人の男性と女性には見覚えがあった。
クレアの両親。
異常な空気を嫌でも感じて、立ち尽くす。
扉の傍に立っていた若い看護師さんが、華やかなステージ衣装の上にダウンコートを羽織っただけの格好でやってきたワタシに気付いて振り向いた。院内で「演奏会」を開くことを許してくれて、よくクレアを見ていてくれた、顔見知りの人だった。
彼女が脇に避けて開いた道を、ふらふらとおぼつかない足取りで歩いていく。倒れないように一歩ずつ踏みしめながら、ゆっくり近づいていく。
クレアの顔が見えるはずのところに真っ白な布がかけられているのを見て、頭から冷水を被ったみたいに、全身が冷えていった。
隣で共に眠るように、布団の下から空色のノートがはみ出ている。ワタシは呆然としたまま、ぴくりともしないクレアの傍らからそれを抜き取り、かじかんで真っ赤な手で中を開いた。楽譜用の五本線が引かれたノートだった。
一ページ目から鉛筆で手書きされているのは、ワタシに贈ってくれたあの曲だ。ワタシのもらったものは綺麗だったけど、こっちはあちこちに消し跡や修正の形跡が残っている。続けて捲ると二曲目があった。でも、それは中途半端なところでぷつっと途絶えている。
最後のページに三つ折りの紙が一枚挟んであって。
開いた拍子に、ひらひらと舞いながら床に落ちる。
飛びつくようにしゃがみ込んで、広げた。
――きっとこれが最後の手紙になります。
震える字で、そんな書き出しで綴られていた。
――ごめんなさい。一緒に大人になることはできないと、入院するよりも前からわたしはわかっていました。
――ミリーには笑っていてほしかった。だから、本当のことが言えませんでした。
――自分の体のことを知ったとき、わたしはピアノを辞めるつもりでした。ピアニストになりたいという夢があったけど、それが叶うのはありえなくて全部無意味なんだって、未来が真っ暗に閉ざされたようでした。
――でも、その暗闇から助けてくれたのは、ミリーです。
――ミリーが歌ってくれるから、わたしのピアノを好きだと言ってくれたから、わたしはピアノを楽しみ続けることができました。
――本当にありがとう。あなたは、わたしの太陽でした。
――わたしは、ミリーの歌にいっぱい元気をもらいました。これからもずっと、ずっと、応援しています。
――わたしの大切な友達 ミリーへ。
温かな、眩しい言葉が並んでいて、視界がぼやけた。疑いようもないくらいクレアの想いが込められた文面に、ぽたぽたと雫が落ちてシミが滲んだ。
胸の中で繰り返す。
ワタシは太陽なんかじゃない。それはクレアにこそ似合う言葉だと。
ワタシにはクレアこそが、青空に輝く太陽のような存在だった。
後悔に押し潰されて、体に全く力が入らない。肩に提げていた鞄がするすると滑り落ちて、中身が散らばる。
歌詞を手書きした楽譜がバラバラになって、灰色の冷たい床の上に広がった。
クレアに内緒でこの歌を完成させるため、ワタシはただでさえ少なかったオフの時間を全て……これまでならクレアへ会いに行っていた時間も全て、作詞に費やしていた。
全部無駄に終わったんだ。
何がお礼だ、サプライズだ。他にするべきことが沢山あったはずなのに。
届かなかったプレゼントに意味なんてない。
陽の落ちた病室はどこよりも寒くて、心ごと凍えてしまいそうだった。
クレアと会ったのは、昨年のワタシの誕生日が最後になった。
あの三週間、クレアは一人で何を思っていただろう。どんな気持ちでこの手紙を遺したのだろう。
ワタシが届けられなかったのは、この一曲だけじゃない。
一つ一つのフレーズに込めたワタシの想い。拙い詩ではとても表現しきれなかったワタシの想い。
一体どれだけ伝わっていただろう。
伝えられていただろう。
翌日、年内最後の営業日だった事務所へ事前連絡も無しに一人で赴いた。楽譜を両腕に抱き、泣き腫らしたボロボロの顔を深々と下げる。
「この曲を、ワタシの歌としてリリースさせてください。お願いします。そのためなら何だってします。ワタシには、何ができますか」
ワタシの願いを……ううん、願いと呼ぶにはあまりにも独りよがりなワタシのわがままを、大人たちは聞き入れてくれた。
こんなことをして何になるんだろう? と自分に問う。
きっと何にもならない。
そうわかっていても、歌わずにはいられなかった。
クレアの楽譜を基に音を付け足し、編曲し、出来上がったのは優しいバラード。クレジットの作曲者の欄には、アレンジを担当してくれたプロの名前に続けて「+C」と添えさせてもらった。
その間、ワタシは寮室にこもって歌詞を書き加えていた。もうとっくに新年のお祝いムードは薄れ、冬休みも終わっていたけれど構わず、寝る間も惜しんで一心不乱にその曲と向き合い続けていた。
一旦家に戻ってきて休んだらどうかと、家から一度手紙が送られてきた。それによると、クレアの両親にも気遣われていたらしい。
でも、止めなかった。わがままを通した。
そして、とうとう社長から正式にNGを言い渡されたんだ。今着手している「それ」が済んだ後は当分の間働かせない、って。
こうして「ピアニスト」という曲は異例のスピードで完成し、その一曲を最後にしてワタシはステージを降ろされた。
それきり、一度も歌っていない。
